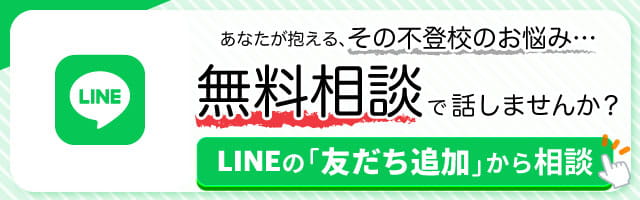この記事を読むのに必要な時間は約 49 分です。
ポイント
- 不登校の子どもが、全く勉強していない
- 勉強はしているけれど、学校のカリキュラムに追い付けているか不安
- 不登校中でも勉強してほしいが、どんな声掛けをしたらいいか分からない
お子さんが不登校になると、親としては勉強の遅れも不安ですよね。
「不登校から復帰してほしい」となると、学校に戻ったあとの授業に追いつけるよう、家でも最低限の学習はしてほしいところ。
この記事を読むと、次のお悩みと解決方法がわかります。
記事を読むとわかること
- 不登校のお子さんの学習にまつわる悩み
- タイプ別「勉強できない」パターンの解決方法
- お子さんに主体的に勉強してもらえる魔法の声かけ
記事を最後まで読むと、なぜ不登校のお子さんの勉強が進まないのか、どうすれば学校復帰後の勉強に困らないかがわかります。
1.不登校で勉強がわからない!勉強の遅れは取り戻せる理由
学校では先生が勉強を教えてくれますが、不登校の場合は、自分で勉強しなければなりません。
また、学校を休んでいる間にも授業は進んでいくので、勉強に遅れてしまいます。
しかし、勉強の遅れは取り戻せますのでご安心ください。勉強の遅れを取り戻せる理由をご説明いたします。
1-1.学校の学習進度はあまり早くない
学校の授業進度はあまり早くはありません。
学校では、先生1人が何十人もの児童に対して授業を行います。
公立学校の授業は、勉強の理解が遅い子にスピードを合わせます。
それに伴い授業進度もゆっくりとなります。
つまり、学校の授業進度はそこまで早くないのです。
不登校となり何日も休んでしまったからといって、取り返せないような差ができてしまったと思う必要はありません。
1-2.学校の勉強に遅れても、追いつくことはできる
自宅学習に取り組めば、学校の勉強に遅れていても追いつくことは可能です。
自分1人のペースで学習を進めると、理解できている箇所は学習にかける時間を学校よりも短縮できます。
学校よりも早いスピードで学習を進めることができるため容易に追いつけるのです。
また、受験を意識していて勉強の遅れが気になっていても追いつくことは可能です。
受験に不要な科目は後回しにして、受験に必要な科目だけを重点的に学習することができるためです。
学校では、受験に不要なことが多い「音楽」や「体育」にも授業時間を取ります。
自宅で自分で勉強する場合は上記の科目を後回しにできるため、効率よく短期間で受験に必要な科目の勉強の遅れを取り戻すことが可能です。
「音楽」や「体育」も大切な科目ですが、受験勉強の遅れを取り戻すことを最重視しているときには「後回しにする」判断も時に必要です。
1-3.勉強の遅れを取り戻して高校や大学に進学できる
不登校であっても、勉強の遅れを取り戻せば高校や大学に進学することは可能です。
不登校で欠席数が多くても、私立高校ならば全日制の高校に進学することができます。
他にも定時制や通信制など状況に合わせて進学先を選択できます。
また、大学の一般受験にいたっては不登校かは関係ありません。
単純に学力試験の結果で合否が判定されます。
そのため、「不登校だから」という理由で高校や大学に進学できないということはなく、勉強の遅れを取り戻せば、お子さんが望む進学先へ進むことが可能です。
2. 不登校で勉強がわからないときに遅れを取り戻す勉強法①:不登校でも勉強しているが進度・学力が不安な場合
不登校でも、次のようなお子さんは学校に行かずとも、自分から勉強をします。
- もともと自宅で学習することが苦でない
- 勉強が好き
しかし、次の2つがあると、いくら家で勉強していても、学校のカリキュラムに遅れをとっていないか不安に思う親御さんは多くいらっしゃいます。
- これまで、学校のテスト・模試を受けていない
- 不登校が長期間にわたって続いている
勉強が遅れるのは気がかりですが、次の2つのポイントをおさえると安心できます。
- 学校は本来、教科書どおりの学習要領を教える
- 学力が不安なら学力テスト・模試を受けてみる
2-1. 学校は教科書どおりの学習要領を教える
結論を言うと、「教科書」の内容が理解できていれば、お子さんの学習状況に問題はありません。
一般的な学校の学習内容:文部科学省による「学習指導要領」が基本です。
私たちが使ってきた「教科書」は、学習指導要領の内容を適切にカバーしています。
つまり、一冊の教科書の内容がわかっていれば、大筋は大丈夫です。
また、学校では教科書に基づいたドリル・問題集が配られます。
配布されたドリル・問題集もスムーズに解ければ、お子さんの学力に心配はないでしょう。
お子さんの学校が教科書などには記載されていない、付加的な知識を教えている場合でも、再登校後に遅れを取り戻すのは難しくありません。
問題があるのは、お子さんが次の場合です。
- 教科書やドリル・問題集の内容を自分で理解できない
- 自力で解決できない疑問点がある
理解が追いついていないため、本来ならばいち早く再登校するのがベストです。
もしも、不登校が長期になる気配があるなら、家庭教師や塾を探す必要が出てきます。
また、学校に相談すると、何かしら力になってもらえる可能性もあるでしょう。
2-2. 学力が不安なら学力テスト・模試を受けてみる
自習が習慣として身についているものの、お子さんの学力が気がかりですか?
そのような場合におすすめするのは、個人的に学力テスト・模試を受けること。
学習の習熟度が点数・数値化されるためモチベーションアップに繋がります。
もし、よい点が取れたら、自信がついて学校復帰できるきっかけになるかもしれません。
学校を通さずに、個人で申し込み可能な各種予備校の学力テスト・模試もあるので調べてみてください。
3. 不登校で勉強がわからないときに遅れを取り戻す勉強法②:1人では勉強に集中できない・頑張れない場合
不登校のお子さんに、勉強するように声をかけても、うまくいきませんよね。
たまたま勉強をはじめたとしても、すぐに集中力が切れてゲームやSNSに逃げてしまうことも。
1人では勉強に集中できない・頑張れないときの対応策は次のとおり。
- 家庭教師を付けてみる
- サポート校を活用してみる
- 不登校専門の学習塾を利用してみる
ポイントは、お子さんを「自分だけ…」と思わせないこと。
勉強を見てくれる人・一緒に頑張る仲間を見つけることで、不登校中の勉強も続けられるようになります。
3-1. 家庭教師を付けてみる
お子さんが「勉強しよう」と言っても、別のことに気をとられるタイプなら、おすすめは家庭教師をつけること。
定期的に学習進度を確認されるため、よい意味でのプレッシャーがかかります。
また、家庭教師の最大のメリットは、わからないことがあるときに気軽に質問できること。
不登校の場合、日中を自宅で過ごすことが多いはず。
家族以外の人との会話は、お子さんにとって適度なリフレッシュにもなりますよ。
3-2. サポート校を活用してみる
人と一緒に過ごしたり、会話が好きなお子さんであれば、サポート校を活用する手もあります。
サポート校の利用には条件がありますが、学習の相談だけでなく進路や人生の相談にも乗ってもらえるメリットも。
自習が進めば受験も視野に入ったり、目標が見つかって不登校を克服できたりと、1人では手にできない様々な可能性が広がります。
こちらもCHECK
-
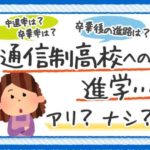
-
【中学不登校】通信制高校に進学で大丈夫?大学進学率やその後を調査!
この記事を読むのに必要な時間は約 46 分です。 この記事を選び大切なお時間を使っていただき、本当にありがとうございます。 私は子どもが中学3年間不登校で、進学先を通信制高校に決めた母親です。 あなた ...
続きを見る
3-3.不登校専門の学習塾を利用してみる
自分から学習するのが難しいのであれば、学習塾を利用して決まった時間に勉強する習慣をつけるのがおすすめです。
- 1対1、少人数制の対面式
- オンライン塾
これら2種類あり、塾の所在地やお子さんが外に出られる状態であるかによって選べます。詳しくは以下の記事を参考になさってください。
こちらもCHECK
-

-
不登校の子どもに塾は必要?利用するメリットデメリット|不登校の根本解決に向けて親御さんができることを紹介
この記事を読むのに必要な時間は約 36 分です。 「子どもが不登校になってしまった…学力を補えるような学習塾に通ったほうがいい?」 「塾に通って学力がつけば、不登校の解決にもつながる?」 ...
続きを見る
4. 不登校で勉強がわからないときに遅れを取り戻す勉強法③:教科書に抵抗アリの場合
次の事柄により勉強ではなく、「学校」への苦手意識があるお子さんもいるでしょう。
- いじめを受けている
- 先生が怖い
- 教室など大人数が苦手
学校に苦手意識がある場合、学校と関わりのある物を避けたがる傾向を持つことも。
- ランドセル
- 筆箱
- 教科書
- 学校配布のドリル・問題集
もしも、お子さんが学校の教科書やドリル・問題集を開きたがらないときは、開き直りましょう!
学校の教材は一切使わず、勉強するのです。
必ずしも学校の教材を使わずとも、学習する方法はたくさんあります。
- 参考書
- ドリル・問題集
- オンライン学習サービス
- 学習用アプリ
私たちが使ってきた紙媒体もよいのですが、オンライン学習サービス・学習用アプリも使ってみましょう。
とくに、算数・数学など概念を理解する必要のある教科は、紙よりもデジタルの方がわかりやすいケースもあります。
また、デジタル端末を使った勉強は、感覚的にゲームに近いです。
お子さんに「学校の勉強をしている」というネガティブな印象を持たせず、学習してもらえます。
余談ですが、筆者もあなたのお子さんと同じ不登校でした。
学校に関わる物はなるべく見たくなかったため、自習用のシャープペンシルやクリアファイルは買い直しました。
勉強道具を一新すると、やる気も出るのでおすすめですよ。
5. 不登校で勉強がわからないときに遅れを取り戻す勉強法④:勉強する理由がわからない場合
お子さんが次のタイプの場合、「なぜ勉強するのか?」を自分で落とし込めていないと、自分から勉強することは難しいでしょう。
- そもそも、学校に行く意味がわからず不登校になった
- 何もかもにやる気が出なくて、学校にも行けなくなった
「なぜ勉強するのか?」この問いへ答えは、大人でもすぐに答えられないかもしれません。
しかし、一度でも自分で「なぜ勉強するのか?」を考え、自分なりの答えを見つけ出せたら、自分の意思で勉強できるようになるはずです。
お子さんが「勉強する理由がわからない」と思っているなら、下の記事をお子さんと一緒に読んでみてください。
こちらもCHECK
-
![[勉強する意味が分からない中高生へ]_アイキャッチ420×420](https://sudachi.support/blog/wp-content/uploads/2020/08/9dfe51f5dbaba664d3fc648d26cd017b-150x150.jpg)
-
【勉強する意味が分からない中高生へ】今すぐスマホをぶん投げて勉強ができるようになる方法
この記事を読むのに必要な時間は約 11 分です。 スダチ(旧逸高等学院)代表の小川です。 中高生のみなさんは、勉強する意味が分からなくて悩んでいる人も多いのではないでしょうか? まさに昔の僕もその一人 ...
続きを見る
お子さんが、自分で勉強することの意味を見つけるまでには、時間がかかります。
日常会話のなかで問いかけて、「考えるきっかけ」を与えてみてください。
このとき、決して無理やり考えさせたり、すぐに答えを求めるのはNG。
無理強いから出た答えは、お子さんにとって「強制されたモチベーション」です。
お子さんが自分から勉強するためには、お子さん自身が答えを見つける必要があります。
会話の雰囲気によっては、親御さんの経験・考えを話すのもよいでしょう。
あなたの考えに賛同・否定のどちらであれ、「自分ならどうするか」と考えるきっかけになります。
6. 不登校で勉強がわからないときに遅れを取り戻す勉強法⑤:体調が悪い場合
体調が悪くて勉強できないこともあります。
体調が悪いとは、誰が見てもあきらかな場合とは限りません。
親御さんには元気に見えても、毎日すごくだるい・調子が上がらないといったケースもあります。
とくに、思春期のお子さんは心と身体の成長スピードが急速です。
成長の早さに身体がついていかず、慢性的にだるさを感じていることも珍しくありません。
体調が悪い場合はどうすればいいのか、次の2つの解決策を紹介します。
- 本人のモチベーションがあってこその勉強
- お子さんのモチベーションを上げるために親御さんも変えてみる
6-1. 本人のモチベーションがあってこその勉強
大前提として、体調が悪いときに無理やり勉強しても、期待できるほどの効果はありません。
無理やり勉強させると、お子さんの中で「勉強=つらいもの」となってしまいます。
また、お子さんが学校に行けず不登校になったのは、漫然とサボっているからではありません。
元気そうに見えても、知らないうちにストレスを感じており、限界に達したため学校に行けなくなったのです。
疲れを回復するために、とことん休むのも重要です。
6-2. お子さんのモチベーションを上げるために親御さんも変えてみる
不登校かつ体調が悪いお子さんの場合、自分から「勉強しよう」と思えるようになるのが大切です。
「なんとなくだるいけど、それでも今日は頑張ってみよう」と思えるようになると、好循環が生まれます。
- 集中して学習したことで、ぐっすり眠れるようになる
- 生活習慣が整う
- 生活にハリが出て、家事を手伝う
結果的に、体調も気分も上向きになることもあるのです。
お子さんが行動を起こすには、本人のモチベーションが何よりも大事です。
しかし、何もないところからモチベーションを生み出すのは、簡単ではありません。
お子さんを変えることはできません。
お子さんを変えるよりもずっと簡単なのは、親御さんが考え方・行動を変えること。
あなたの生活の様子・お子さんへの向き合い方が変化すると、お子さんも影響を受けて「何か頑張ってみようかな」と思えるようになります。
「意識・行動を変えること」といっても、具体的にどうすればよいのか、わかりませんよね。
私たちが展開している【平均3週間で不登校解決プログラム】のオンラインセミナーには、親御さんの考え方・行動を変えるヒントが詰まっていますよ。
無料オンラインセミナー動画をご視聴いただいた方に、無料オンライン相談を実施しています。1対1で顔出しも不要です。ぜひ一度現状のお子さんの様子をお聞かせください。
\無料相談を申し込む/
7.不登校で勉強がわからないのに勉強しない!小学生・中学生・高校生へ親ができる対処方法
子どもが不登校で勉強がわからないのに勉強しないというのは、不登校の親御さんが抱える悩みのひとつです。
ここでは、子どもに勉強してもらうためには、親がどのようにサポートすればいいのか紹介します。
こちらで解説している内容は以下のYouTubeでもお話ししています。
こちらもCHECK
-
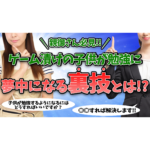
-
【不登校】ゲームばかりで勉強しない子どもを勉強好きにさせる裏技とは?
この記事を読むのに必要な時間は約 19 分です。 今回は、「勉強しない子どもを勉強好きにさせる方法」について解説します。 子供が勉強しなくて困っているというのは、親御さん誰もが抱える悩みだと思います。 ...
続きを見る
7-1.勉強をしなさいと伝えるのではなく愛情を伝える
子どもは、押し付けられると反発する傾向があります。
また勉強をしなくてはならない理由がわかっていないことも多いです。
明確な理由がないのに「勉強をしなさい」と押し付けられると、反発するだけでなく「自分の感情ばかり押し付ける親は信用できない」と心を閉ざしてしまうこともあります。
そのため、子どもを愛していて大切に思うからこそ、勉強は子どもにとって必要なことだと感じていることを伝えましょう。
現状の日本は学歴が重視される傾向にあります。
このまま勉強をしないと、お子さんが夢をあきらめなくてはならない場面に遭遇することもあります。
上記の理由を教えてあげたうえで、「あなたのことが大切な存在で、夢をあきらめるようなことになって欲しくないからこそ、勉強は大切だと伝えるね。」と子どもを愛していることを伝えた上でお話ししてみましょう。
7-2.無理矢理やらせるのではなく子どもが主体的に取り組めるように促す
また、子どもが主体的に取り組めるように促すことも大切です。
親からの愛情を伝えながら、勉強の大切さを教えたのに「あなたのことが大切だから勉強してほしい!」と親御さんの感情を押し付けることはおすすめできません。
「私の今の気持ちを理解するよりも自分の気持ちを押し通すんだ」とお子さんが感じてしまうこともあります。
子どもに勉強の大切さを伝えたうえで、「でも勉強するかしないかは、自分で選んでね」という言葉をかけましょう。
勉強の大切さを明確に教えてくれて、自分の気持ちを認め優先してくれる信頼できる親御さんの言葉は、お子さんが素直に受け入れやすいです。
そしてお子さんは主体的に勉強に取り組んでくれるようになります。
7-3.不登校の支援団体スダチに相談する
「子どもに私の言葉が響くような状況ではない」「声かけしているけれどうまくいかない」そのようなときは、親御さん一人で悩まずにスダチなどの不登校の専門家にご相談ください。
スダチの支援では、その時のお子さんにあった適切な声かけや接し方を親御さんへ日々サポートしております。
これまで「勉強をしてくれない」とご相談をいただいたさまざまな親御さんのお悩みを解決してきた知見がありますのでどうかご安心ください。
お子さんが主体的に勉強に取り組めるような声かけと接し方を日々ご指導しております。
またお子さんが主体的に勉強に取り組むだけでなく、不登校も解決し再登校しています。
親御さんが私たちのフィードバックに合わせて行動してくださっているおかげで、お子さんたちは平均3週間で再登校しています。
無料オンラインセミナー動画をご視聴いただいた方に、無料オンライン相談を実施しています。1対1で顔出しも不要です。ぜひ一度現状のお子さんの様子をお聞かせください。
\無料相談を申し込む/
中学生の勉強の遅れについては、以下の記事でも詳しく紹介しています。
こちらもCHECK
-

-
中学生の不登校は勉強しなくても大丈夫?勉強の遅れを取り戻し高校受験するために親ができる対応方法
この記事を読むのに必要な時間は約 52 分です。 お悩みポイント 中学生で不登校の子どもがいるけど、家で勉強している感じがしない。 中学生だし、やっぱり受験に影響しそうで…。 やっぱり子 ...
続きを見る
8.不登校で勉強がわからないときは遅れを取り戻す前に生活スタイルを見直すことも大切
学校の勉強の遅れを取り戻すために、勉強を頑張ることも大切ですが、まずは生活スタイルを見直してみましょう。
不登校になり乱れた生活習慣のまま勉強を始めても、集中することができない場合が多いです。
規則正しい生活習慣を身につけて、勉強する準備を整えましょう。
8-1.部屋を片付ける
部屋の中に物が散乱してる状態で勉強しても、集中力は長続きしません。
「物が散乱していると人間の集中力は低下する」という調査結果もあります。
調査結果によると、「人間は無意識に散らかった物に気を取られてしまうため、集中するための体力を浪費している」ということです。
散らかっているがために無駄な体力を消費し、体力を勉強に当てることができないのです。
きちんと整理整頓し、勉強に注力できる環境に整えましょう。
参照参考:DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー『デスクが散らかっていると集中力も生産性も低下する 書類を積み上げたくなる誘惑に打ち勝つ方法 』
8-2.体力をつける
実は勉強も体力勝負です。
勉強は長時間同じ姿勢を保つ必要があります。
そのため、姿勢を保つ腹筋や背筋が最低限必要です。
筋力がないと、同じ姿勢を保つことが難しくなり、集中力が続きません。
体力や筋力を確保するためには、日頃から体を動かすことが大切です。
無理のない範囲で、ウォーキングや筋トレなどをして最低限の体力や筋力を確保しておきましょう。
8-3.生活リズムを整える
学校がないと、朝起きるのが遅くなったり、昼夜逆転してしまったりと、生活リズムが乱れやすくなります。
夜遅くまで起きて何かに取り組むような生活リズムになっている場合も多いでしょう。
自宅学習に取り組むときには、学校に通っているときと同じ昼型の生活リズムに戻すことがおすすめです。
昼型の生活リズムに戻すことで次のメリットもあります。
- 図書館に行って勉強するなど外に出るきっかけができる
- 受験を控えている場合は本番に向けてコンディションを整えることができる
- 塾や家庭教師を昼間に受けることができる
- 再登校するときにスムーズ
学校へ通う場合と同じ生活リズムに整えておけば、お子さんが再登校するときもスムーズです。
9.勉強の遅れを取り戻す前に知っておきたい子どもが不登校になった原因
勉強の遅れは気になることですが、その前に一度お子さんが不登校になったきっかけも知っておきましょう。
もしかしたら今お子さんは勉強に取り組めるような心境ではないかもしれません。
まずは、お子さんが不登校になったきっかけを探り、お子さんのつらい気持ちなどを受け入れて認めてあげましょう。
そして親子で一緒に前に進むことが大切です。
9-1.学校の人間関係
学校でのいじめや友人とのトラブルなど、人間関係がきっかけとなり学校に行けなくなるお子さんもいらっしゃいます。
学校に安心できる場所がないと、学校に行きたい気持ちがなくなってしまいます。
上記の場合は、勉強を促す前に、まずは学校でつらいことがあったお子さんの気持ちを受け入れて認めてあげてください。
また、いじめを機に自己肯定感が下がり切っている状態にあります。
そのため次のことを教えてあげてください。
- 子どもがダメな存在だからいじめられたわけではないこと
- 今のままで素晴らしい存在であること
- 自分とは異なる価値観の人が世の中にはたくさんいること
お子さんが悪いからいじめられたのではなく、世の中にはさまざまな価値観の人がいて時にいじめをするような人がいることを教えてあげてください。
そしてお子さんは今のままで素晴らしい存在であることも教えてあげてください。
また、担任の先生に相談してみることも大切です。
クラスでの様子を詳しく教えてくれるため、子どもの気持ちを探るきっかけにもなります。
クラス替えがある場合には、いじめをする生徒とのクラスを分けてくれるケースもあります。
現状を把握するためにも担任の先生にも相談しておきましょう。
いじめをきっかけに不登校になった場合の解決方法は、次の記事でもお話ししています。
こちらもCHECK
-
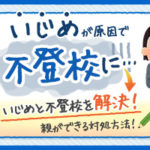
-
いじめが原因で不登校に!不登校を解決するために親ができる対処方法
この記事を読むのに必要な時間は約 34 分です。 子どもがいじめられて不登校になってしまった…どう接したらいいの? いじめと不登校を解決する方法を知りたい。 お子さんがいじめから不登校に ...
続きを見る
9-2.学校に行く気が起きない
「なんとなく学校に行く気が起きない」ということも不登校のきっかけとしてあります。
学校の生活が合わなかったり、今まで頑張っていたのに急に燃え尽きてしまったり、なんとなく学校に行きたくない気持ちが生まれてしまうのです。
このような場合は、まずは心の元気を失くしてしまったお子さんの気持ちを受け入れてあげることが大切です。
また、今まで子どもが取り組んだことの結果に目を向けて褒めていた場合、思う様な結果が出せなかったときに「頑張っていたけれど親に褒めてもらえるような結果がだせない自分はダメな人なんだ」と子どもが燃え尽きてしまうこともあります。
結果には目を向けず、物事に努力して取り組む姿勢に目を向けて、ありのままの姿を褒めてあげてください。
今のお子さんの気持ちを受け入れて、物事の結果でなく、ありのままの姿を褒めることで、子どもの自己肯定感が育ち心の元気を取り戻します。
心の元気を取り戻すと、お子さんは、自発的に勉強だけでなく再登校しはじめます。
なんとなくの無気力がきっかけの不登校については以下の記事で詳しく解説しています。
こちらもCHECK
-
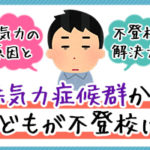
-
無気力症候群から子どもが不登校に?無気力の原因と解決法【高校生・中学生・小学生】
この記事を読むのに必要な時間は約 26 分です。 子どもが無気力症候群気味で不登校になってしまった。解決方法を知りたい。 子どもが無気力になった原因を探りたい。 お子さんが無気力な様子で不登校となった ...
続きを見る
10.不登校で勉強がわからない状態だった子どもが遅れを取り戻し再登校した体験談
不登校で勉強がわからない状態だった子どもが遅れを取り戻し、再登校した体験談を親御さんの話を元に紹介します。
子どもが不登校になったきっかけは、やんちゃな生徒から時々怪我を負わされたり、からかわれたりしていたことでした。
そして「子どもに強くなってほしい」という思いから、助けを求める子どもに対し、突き放すような対応をしてしまいました。
ネットで調べた「子どもに愛情を注ぎ学校はいかなくていい場所と受け入れる」という情報をみて、登校を促さず学校は行かなくていいと思いながら気分転換に親子2人での外出の時間を作ると、子どもは少しずつ登校できるようになりました。
しかし、その後またすぐ不登校に。
そんなときに、YouTubeから、スダチの支援と出会いました。
動画で話している内容を実践してみたところ、子どもの気持ちや言動に前へ進む様な変化が見られました。
そこでスダチの支援を受けることに。
支援では、子どもに伝わりやすい愛情の伝え方や、子どもと正しい信頼関係を築くうえでの行動方法や声の掛け方を具体的な内容でサポートしてもらいました。
日々のフィードバックに合わせて子どもと接すると、みるみるうちに子どもは前向きになり、自主的に再登校してくれました。
今では、学校に行けば行くほど、自分に自信がついている様子です。
そしてずっと着手しなかった学習を習慣化することもできました。「中学は私立難関校に行きたい」とまで言い出すように。
学校では授業で積極的に手をあげて発言もするようになりました。
上記でご紹介した体験談は次の記事でさらに詳しくお話ししています。よろしければご参考になさってみてください。
こちらもCHECK
-
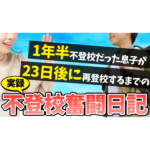
-
【実話】1年半不登校だった息子(小3)が23日後に再登校するまでの奮闘日記
この記事を読むのに必要な時間は約 40 分です。 今回は、「1年半不登校だった息子が23日後に再登校するまでの奮闘日記」という内容でお話します。 これまでこのチャンネルでは、多くの不登校を克服されたご ...
続きを見る
11.不登校で勉強がわからないときや勉強に遅れがあるときのよくある質問
お子さんが不登校になり、勉強がわからないときや、勉強に遅れが出てきてしまったときのよくある質問をまとめました。
11-1.不登校の子どもが勉強がわからないと言う。何から勉強すればいい?
まずは、お子さんにとって何がわからないのかを明確にすることが大切です。
学校で配布されたワークやドリルに取り組み、わからない部分・知識が不足している部分を明確にしましょう。
そのうえで、わからない部分や知識が不足している部分を補うよう重点的に勉強します。
勉強がわからない状態が長く続くと、自己肯定感が下がってしまい、余計に勉強へのやる気が下がることもあります。
次の記事では、お子さんの自己肯定感を育てながら勉強ができるように導く方法を紹介しているので、参考にしていただけると幸いです。
こちらもCHECK
-
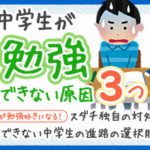
-
勉強ができない中学生には3つの原因!この先の進路の選択肢と勉強好きになる独自のアプローチ方法を公開
この記事を読むのに必要な時間は約 29 分です。 「中学生の子どもが授業についていけず勉強できない…このまま学校を嫌がり不登校になるのでは?」 「子どものやる気に任せた方が良い?このまま放っておいて大 ...
続きを見る
11-2.不登校の子どもが勉強の遅れを取り戻すためには何時間勉強すればいい?また勉強は何をすればいい?
子どもが無理なく習慣化して続けられる時間がおすすめです。
もしも受験を控えているのならば、目安として次の時間も考えられます。
平日:平均3〜4時間
休日:平均8〜10時間
ただし上記は、大学受験生(高校3年生)で考えた場合のため、参考程度にしてください。
勉強方法は、まずは教科書通りの内容を勉強してみましょう。
自分の今の学力を知りたいのであれば、学力テストや模試を受けてみることをおすすめします。
もし、一人で勉強できない場合は、塾や家庭教師も検討できます。
その他、SNSやアプリなどを活用する方法もあります。
11-3.不登校の子どもは塾に通えない?
「学校に行っていないと塾に入れない」といったことはありません。
学びたいという気持ちがあれば、塾に入ることができます。
「学校は合わないけど、塾には行きやすい」という場合もあります。
塾によっては集団指導か、少人数・個別指導などもあります。
不登校のお子さんが通える学習塾については、次の記事でもお話ししています。
こちらもCHECK
-

-
不登校の子どもに塾は必要?利用するメリットデメリット|不登校の根本解決に向けて親御さんができることを紹介
この記事を読むのに必要な時間は約 36 分です。 「子どもが不登校になってしまった…学力を補えるような学習塾に通ったほうがいい?」 「塾に通って学力がつけば、不登校の解決にもつながる?」 ...
続きを見る
11-4.不登校の子どもが勉強をしてくれないのはなぜ?
不登校のお子さんには、勉強をやらなければいけない理由がわからず、勉強をしなくなってしまうお子さんが多いです。
また、「勉強しなさい」と、押し付けられるとお子さんは反発してしまいます。
親御さんが押し付けるスタンスを続けてしまうと親子の関係も悪化します。
勉強の必要性を伝え、お子さんへの愛情を伝え、自主的に勉強してもらうよう促しましょう。
勉強の必要性を伝える際には、選べる進学先が増えるなどの勉強するとどんないいいことがあるのかに加えて、勉強しないリスクについても教えてあげることが大切です。
そうすることでより勉強の大切さを実感でき、お子さんが自分から勉強に取り組みやすくなります。勉強の必要性については次の記事でもお話ししています。
こちらもCHECK
-

-
「勉強しないとどうなる?」親が放っておくリスクと勉強嫌いの理由・解決法
この記事を読むのに必要な時間は約 39 分です。 「子どもが勉強嫌いで全く勉強してくれない!このまま放っておくとどうなってしまう?」 「子どもが勉強してくれるようになる、解決方法を知りたい。」 お子さ ...
続きを見る
11-5.中学生の子どもが学校へ行きたくないという…どうしたらいい?
「学校に行きなさい」と頭ごなしに言ってしまうのはよくありません。
まずは学校で何かつらいことがあったお子さんの気持ちを受け入れて認めてあげましょう。
スダチの支援では、お子さんが「学校へ行きたくない」と思う根本的な原因を脳科学に基づいた視点から解決しています。
現在のお子さんの心境が知りたいときや、早期解決したい場合はぜひスダチへご相談ください。
無料オンラインセミナー動画をご視聴いただいた方に、無料オンライン相談を実施しています。1対1で顔出しも不要です。ぜひ一度現状のお子さんの様子をお聞かせください。
\無料相談を申し込む/
12. まとめ
お子さんのタイプ別勉強法は、次のとおりです。
- 不登校でも勉強しているが進度・学力が不安
教科書の内容は、学習の柱として考える。
必要に応じて、外部の学力テスト・模試を受ける。
- 1人では勉強に集中できない・頑張れない
家庭教師・SNS・サポート校を活用。
勉強を見守る、一緒に勉強する仲間を見つけることで、1人にさせない。
- 学校への苦手意識が強い・嫌いで教科書も見たくない
教科書は使わず、市販の参考書・問題集やオンラインサービス・学習用アプリなどを活用する。
- 勉強する理由が分からない
「なぜ勉強するのか?」「勉強した場合・しなかった場合の将来像」を一緒に考えてみる。
- 体調が悪い場合
一旦、無理はさせずに休ませ、子どものモチベーションが湧くまで待つ。
子どもに勉強の大切さと、愛情を伝え、子どもが前へ進めるようサポートしましょう。