この記事を読むのに必要な時間は約 26 分です。
「不登校の子どもが家庭内で暴力を振るうようになって困っている」
「どのように解決していけばいいのかを知りたい」
不登校の子どもの中には、徐々に親に暴言や暴力を振るうようになるケースもあります。
そのまま放置してしまったり、適切な対処ができないとエスカレートしたり、このまま不登校が長期化することもあるため、早めの対応をすることが大切です。
この記事では、不登校で暴力を振るう子どもの特徴や原因・親ができる解決策を紹介します。子どもの不登校や家庭内暴力を解決したい親御さんはぜひご覧ください。
【平均3週間で不登校解決プログラム】を展開する小川涼太郎監修のもと、お話しする内容は次のとおり。
記事を読むとわかること
- 不登校で暴力を振るう子どもの特徴と傾向
- 不登校の子どもが暴力を振るうようになる原因
- 暴力を振るう問題と不登校を解決するための対応方法
- 暴力と不登校を放置した場合のリスク
スダチでは、不登校になったお子さんを平均3週間で再登校に導いています。
お子さんへの声かけや接し方を少し変えていただくだけで、お子さんは主体的に再登校を果たしています。
さらにみなさん、学校でも問題を主体的に乗り越えられるように成長なさっています。子育てに悩んでいる親御さんは、ぜひ一度ご相談ください!
\無料相談を申し込む/
1. 不登校で暴力を振るう子どもの特徴3つ
不登校の子どもの中には、家庭内で暴力を振るってしまう子もいます。
どんな子どもが暴力を振るいやすい傾向にあるのか、当てはまる特徴3つをご紹介します。
1-1. 家庭内と学校で振る舞いが違う
家庭内と学校で振る舞いが違うケースが多いです。
たとえば、家庭では暴力を振るっていたり部屋が散らかっていたりするような子どもでも、学校では大人しくしていることがあります。
大人しくしていたくてしているわけではなく、自分を表現する方法がわからないから大人しくしています。
自分を表現できず、他人の前ではさまざまなことを我慢しながら過ごしているため、そのストレスをご家庭で暴れて解消することがあります。
結果として、家庭内での暴力につながってしまうのです。
1-2. 親に依存してしまっている
親に依存している子どもは暴力を振るってしまう傾向があります。
依存と聞くと甘やかされている印象をもつかもしれません。
しかし、厳しい親のもとで過ごしている子どもが依存しているケースもあるので注意が必要です。
たとえば、子どもの行動を制限して「〇〇しなさい」などと厳しくしていると、子どもは揉めることを恐れて親の言う通りにします。
言う通りにしなければいけない状態だと、自分の意見をもつことができなくなります。
やがて子どもは自分で考えることをしなくなり、親に依存するのです。
親に言われたことしかできないようであれば、依存していると考えて良いでしょう。
そして親の言われた通りに生きている中で、学校で何か問題が発生して不登校になることがあります。
「親に言われた通りに生きていたのに、こんなにストレスを感じるはめになった」と全てを親のせいにしようとすることも。
そして、その思いを暴力として発現するのです。
一方、親が子どもを甘やかしているケースでは、子どもにとって親は「思い通りになる存在」です。
しかし、学校のクラスメイトはそうではありません。
これにより学校に行きたがらなくなり、溜まったストレスを親への暴力で発散しようとすることもあります。
1-3. 受け身タイプで積極性があまりない
自分の意見を伝えるのが苦手で、積極性がない子どもも家庭で暴力を振るう場合があります。
受け身タイプの子どもは、学校で嫌なことを押し付けられたりしても、自分の望みを周囲に言えない傾向があります。
自己肯定感が低く、自分の考えや意見に自信を持つことができないためです。
- 「ここで断ったら嫌われてしまうのではないか」
- 「自分の要望をどのように伝えれば相手が嫌な気持ちにならないだろうか」
常に上記の不安や心配を抱えていることも多く、学校に行くだけで大きなストレスを感じている傾向があります。
そのため、自分のことを嫌うことがない親の前では、暴力や暴言を吐き、ストレスを発散する場合も多いです。
2. 子どもが不登校で暴力を振るうようになる原因3つ
不登校の子どもが全員、暴力を振るうわけではありません。では、なぜ子どもが暴力を振るうようになってしまうのでしょうか。
考えられるきっかけ3つをご紹介します。
2-1. 熱中して取り組める趣味がない
不登校の場合には、家庭でしかストレス発散ができません。
人との関わりが家庭にしかないからです。
もちろん、絵を描くなど1人でできる趣味などでうまくストレスを発散できる子もいます。
しかし、趣味がない場合にはストレスが溜まる一方になるでしょう。
結果として、親や兄弟との関わりの中で発散することになるのです。
ストレス原因の根本的な解決ができない状態が長く続くと、暴言がはじまりやがて暴力につながってしまいます。
2-2. 親自身が子離れできていない
親自身が子離れできていないことが、子どもの暴力につながることもあります。
たとえば、甘やかしてなんでも親がしてあげたり、親が我慢することで帳尻を合わせていたりしているケースです。
逆に子どもに厳しく「〇〇して」となんでも指示しているような場合も子離れできていないと言えます。
これらの状態では子どもはなんでも親任せになったり、親の言いなりになったりしてしまうのです。
自分で考える習慣がないので、何か問題が起きても1人では解決できません。
問題が解決されない状態が長く続くと、うまくいかない悲しみや悔しさを親のせいにするようになります。
そしてその怒りを暴力や暴言で表すのです。
また、子どもの反抗期は親ばなれのためのものです。
反抗期に親が子離れすることで、子どもも親ばなれができます。
反抗期に不登校になってしまったお子さんへの対応方法については、以下の記事を参考にしてみてください。
こちらもCHECK
-
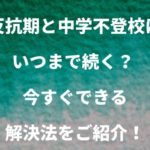
-
反抗期と中学不登校はいつまで続く? 今すぐできる解決法をご紹介!
この記事を読むのに必要な時間は約 39 分です。 この記事を選んでいただき、 そして大切なお時間を使っていただき本当にありがとうございます。 中学3年間不登校 ...
続きを見る
2-3. 子どもが親の上に立ってしまう
子どもが親の上に立ってしまうような、正しい親子関係を築けていない状況のとき、暴力の解決は難しいです。
子どもが親のことを下に見ているため、親の威厳がない状態で褒めたり正しいことを教えたりしても伝わりません。
尊敬していない上司から何を言われても、心に響かないのと同じです。
子どもにあなたの言葉を伝えたいのであれば、日々子どもに対し毅然とした態度で接し、正しい親子関係を築くことが大切です。
親としての立場を取り戻せば、子どもと話ができます。
子どもの言いなりになったり、暴力を我慢したりする必要はありません。
親子の立場が逆転している場合の対処方法については、以下の記事をご覧ください。
こちらもCHECK
-
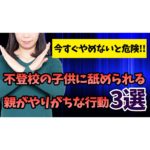
-
【今すぐやめないと危険】不登校の子供に舐められる親がやりがちな行動3選
この記事を読むのに必要な時間は約 11 分です。 今回は「不登校の子供に舐められる親がやりがちな行動3選」というテーマでお話します。 現代では、残念ながら子どもに舐められてしまっている親御さんが非常に ...
続きを見る
3. 不登校で暴力を振るう子どもへの接し方・解決方法4つ
ここまでの内容でわかるように、子どもが暴力を振るう原因には、子どもの自己肯定感が低いことや、うまくいっていない親子関係にあります。
お子さんの自己肯定感を育てながら、親子関係を改善していく方法を解説いたします。
3-1. 子どもが自分で感情のコントロールをできるようにする
子どもが自分の感情をコントロールできるように、自立を促しましょう。
子どもが何かしらの課題を抱えたとき、親はついつい解決の手助けをしてしまいます。
しかし、目の前の課題を親がすぐに解決することよりも、子どもが自分で考えて課題を解決できるようにすることが重要です。
課題にぶつかったときには、癇癪を起こさず向き合う力が求められます。
感情のコントロールも課題解決能力の一部なのです。
だからこそ、たとえ子どもだけで課題の解決がうまくいかない時でも、安易に手助けすることは避けましょう。
安易な手助けは子どもが親の上に立つ構造を生みかねないからです。
もちろん、命の危険があるときなどは助けるべきです。
しかし、そうでない場合には心を鬼にして見守り、子どもの感情的な自立を促していきましょう。
3-2. 正しい親子関係を築き子どもの自己肯定感を育てる
子どもが親の上に立ってしまう親子関係では、子どもの自己肯定感が育ちません。
自分がしていることが正しいのかどうかを教えてくれる人がいないからです。
正しい親子関係を築いて子どもの自己肯定感を育てるためにも、次のことを意識してみてください。
- 子どもに対しダメなことはダメだと毅然とした態度で教える
- 子どもの良いところに目を向けてたくさん褒め愛情を伝える
子どもは、正しいことはたくさん褒めてくれて、ダメなことはダメだと怒らずに教えてくれる親のことを信頼します。
自分が生きていく上で大切な判断基準を得られますし、失敗しても許されることで愛情を感じるからです。
信頼している親からたくさん褒められたり、正しいことを教えてもらったりすることで、子どもの自己肯定感が育ちます。
自己肯定感は多少のストレスには負けない強さとなり、登校への勇気に変わっていくのです。
「親が自分の味方である」という安心感が、再出発の後押しになります。
3-3. 急かさず子どもの口から言葉を引き出す
会話をするときは急かさず、子どもが自分の言葉で話すことを促してください。
子どもにとって「自分の発言を待ってくれる親の存在」「話を聞いてもらった体験」は大きな力になるからです。
話している最中に子どもが口ごもっても「はっきり言いなさい」などと声をかけるのは避けましょう。
懸命に話す内容を考えている子どもからすれば、すぐに結論を出そうとする親の発言は自分を否定しているように聞こえます。
そのため「どうして自分の気持ちをわかってくれないのだろう」「いつも感情的に否定して、親は自分勝手だ」と感じ、暴言や暴力で自分の考えや気持ちを表そうとすることがあります。
もちろん、子どもだけで考えるのが難しい内容の場合にはサポートしましょう。
その際には答えを提示するのではなく、子どもが物事を多角面から考えられるような声かけをするのがポイントです。
3-4. 質問には子どもが自分で考えるように促す回答をする
子どもが質問してきたときには、自分で答えを出せるように促してください。
答えを教えるのではなく、考える視点や選択肢を与えることが大切です。
たとえば、外食するお店を決めるときに「何がいいと思う?」と質問されたとしましょう。
この場合には「お肉とお魚どっちがいい?」「軽めのものがいい?しっかり食べたい?」などと選択肢を提示してあげましょう。
「お肉でいい?」などと限定して聞いてしまうと、子どもは考えず「じゃあそれでいい」と答えてしまうからです。
子どもは自分で考えずに決めたことは「親が決めたことだから」と考えるので、責任をもちません。
だからこそ、何かうまくいかないことがあると「親のせいだ」と考え、親に対して暴力を振るうのです。
考える力を伸ばせるようにサポートして、判断したり責任をもったりできる子どもに育てていきましょう。
4. 不登校で暴力を振るう子どもを放置してしまうとどうなる?
不登校で暴力を振るう子どもへの対処方法がわからず、そのまま放置してしまった場合のリスクについても解説させていただきます。
4-1. エスカレートする可能性が高い
適切な対処をせず放置してしまうと、暴力がエスカレートしてしまいます。
暴力を我慢すれば、子どもは親を思い通りにできると感じ、さらに言うことを聞かせようとするでしょう。
暴力で何でも解決できると思い込んでしまうのです。
子どもに干渉せず関わりをもたないようにする場合も同様です。
「親は自分を見てくれない」と感じてストレスとなり、親を振り向かせようとしてさらに困らせるような暴力暴言を振るったり、ストレスを発散しようとして暴れたりします。
エスカレートする前に、なるべく早い段階で対処することが重要です。
暴力を振るい始めたばかりの子どもは「暴力はいけないことだ」とわかっています。
「わかっているけどやめられない罪悪感」に悩まされている子どもを、助けてあげましょう。
このまま放置して暴力を振るうことが日常になると、罪悪感が薄れて改善が困難になります。
お子さんを救ってあげるために親御さんが早めに行動をおこしていきましょう。
4-2. 不登校の子どもが暴力を振るうときには専門家の力を借りることが重要
不登校の子どもが暴力を振るう状況のときは、親御さんひとりで対処しようとせず専門家の力を借り、二人三脚で現状の問題を解決していきましょう。
多くの不登校の子どもを支援してきた専門家であれば、知見に基づき、親に暴力を振るうような子どもの不登校も解決に導くことが可能です。
- 「この状況を誰に相談すれば良いのかわからない」
- 「子どもにどのような言葉をかけて解決していけばよいのかわからない」
その場合は、スダチへご相談ください。
【3週間で不登校解決プログラム】を展開しているスダチでは、親に暴力を振るっていた小学校6年生の男の子が支援開始から17日で再登校に成功しています。
その他不登校が長期化し、親御さんへの暴力や暴言が日常化していたお子さん方もたくさん支援させていただき、問題解決に導いてきました。
不登校の根本原因へアプローチし、正しい親子関係を構築できるようご指導させていただきます。再度不登校になることなく、お子さん方は、主体的に学校へ登校しています。
また、オンラインの無料相談も実施しております。もちろん1対1で顔出しも不要です。
現状のお子さんの様子をぜひお聞かせください。一緒に解決に向けて前進しましょう。
\無料相談を申し込む/
5. 不登校で暴力を振るう子どもをもつ親御さんからのよくある質問
不登校で暴力を振るう子どもをもつ親御さんが、抱えがちな悩みについて回答します。
5-1. 発達障害で不登校の子どもが家庭で暴れる…どうしたら良い?
発達障害のお子さんは、次の理由から自己肯定感が低下しやすく不登校になりやすいことがあります。
- 頑張っているのに周りの子どもと同じように行動できない
- 発達障害ならではの独自のこだわりがあり集団生活に大きなストレスを感じる
- 自分の特性を周りの友人に揶揄われたり貶されたりする
学校生活で上記のストレスを抱えることにより、そのストレスが爆発し、信頼できる親の前で暴れてしまうのです。
だからといって家庭で暴れていいわけではありません。
正しい親子関係を築きながら、子どもの自己肯定感を育ててあげることが大切です。
子どもの自己肯定感が育つと「人は人、自分は自分」「自分ならば大丈夫」と考えられるようになり、不登校が解決するきっかけにもなります。
また、ストレスをうまく発散していく方法についても教えてあげることが大切です。
発達障害と不登校の関係や解決方法については、以下の記事で解説しています。こちらもあわせてご覧ください。
こちらもCHECK
-
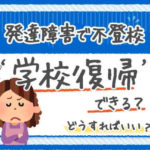
-
【発達障害と不登校】「ふつう」ができない【理解とサポートがカギ】
この記事を読むのに必要な時間は約 52 分です。 子どもの不登校について調べていると「発達障害かも」と書かれていることもあり、気がかりですよね。 この記事は、次のお悩み・疑問を持っている ...
続きを見る
5-2. 不登校気味の中学生の子どもが友達に暴力を振るっているようだ。
親御さんはお子さんを大切に思い、愛情を注いで育児をされているでしょう。
しかし、お子さんが親御さんからの愛情をうまく受け取れていないこともあります。
とくに中学生で思春期のお子さんは反抗期でもあり、親御さんとの接触を避けるため、愛情を受け取る機会がすくなくなってしまうのです。
愛情がうまく受け取れていないと「親は自分のことをどうでもいいと思っている」「この親は信頼できない」「親に怒られてばかりで自分はダメなやつ」と感じてしまいます。
このようなご家庭内で感じた不満を発散するために、学校で暴力を振るう場合もあります。
親子の信頼関係を築きなおし、子どもに伝わりやすい方法で愛情を注いでいきましょう。
5-3. 不登校になりやすい家庭の特徴は?
不登校になりやすい家庭には以下の特徴が挙げられます。
- 子どもに対して過保護・過干渉
- 子どもを感情的に怒ってしまう
- 子どもに対して無関心
特徴ごとに実践すべき解決策が異なります。詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。
こちらもCHECK
-

-
不登校になりやすい子どもの親や家庭の特徴とは?小学生の事例をご紹介
この記事を読むのに必要な時間は約 35 分です。 お問い合わせ 不登校になりやすい子どもの特徴は? 子どもが不登校になりやすい親や家庭の特徴は? 本記事では、不登校になりや ...
続きを見る
6. まとめ
不登校の子どもが親御さんへ暴力を振るう場合、正しい親子関係が築けていないケースが多いです。
お子さんが受け取りやすい方法で愛情を伝え、親子の信頼関係を構築していくことが重要です。
まずは、毅然とした態度でダメなことはダメと伝え、良いところはたくさん褒めてください。
厳しくしすぎたり甘やかしたりするのではなく、正しく良し悪しの判断軸を伝えることで、子どもは親を信頼します。
この信頼関係が子どものストレス耐性やチャレンジ精神を育て、再登校への鍵となるでしょう。
スダチでは「親子関係」「子どもの自己肯定感を育てること」に焦点を当てて、支援を実施しています。
まずはお子さんの現状を聞かせていただければ幸いです。
親御さんの愛情がどうしてお子さんに伝わっていないのか、また、どのような接し方でどのような言葉をかけていけば良いのかをお伝えさせていただきます。
不登校解決のための無料オンラインセミナー動画を視聴していただいた方には、無料相談を実施中です。
顔出し不要のオンライン相談なので、お気軽にご利用ください。
\無料相談を申し込む/






