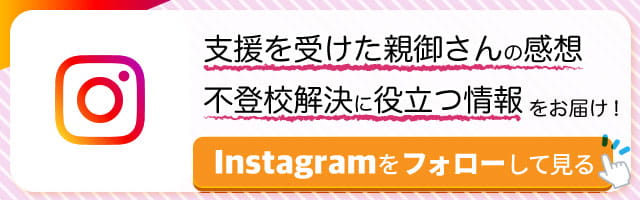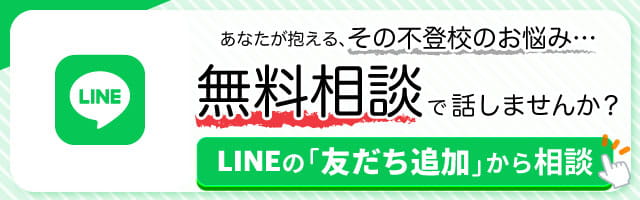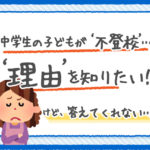この記事を読むのに必要な時間は約 14 分です。
子どもが学校に行かない。理由はわからない。このままではダメだとわかっているけども言い合いになるだけ。
この記事に辿り着いた方は「せめて卒業はしてほしい」、「学校にいけないなんてこの先の社会で不安」、「親としてどうすべきかわからない」と頭を抱えているのではないでしょうか。
この記事では、このような現状に対して親御さんが今すぐできる2つのことをご紹介します。
1. このままじゃ卒業できない!?義務教育の卒業条件に関するよくある誤解
まず不登校の中学生は卒業できないのか?という疑問についてお答えします。
ご安心ください。答えは“No”です。
理由は日本の教育方針にあります。日本の義務教育は年齢主義であり、年齢で学年が決まり、学年により履修内容が決まります。
不登校でも義務教育期間中は留年することがありません。必ず卒業できることが日本の義務教育の仕組みです。
2. 不登校は繰り返される
2-1. 不登校の再発率
ここで少し厳しい現実をお伝えします。不登校の再発率は70~80%と言われています。これは在学中の不登校再発率だけではなく、中学卒業後の進学先でも不登校が再発してしまう確率が高いことを示しています。
卒業は終わりではなく、新しい環境への第一歩なのです。
2-2. 根本的原因の解決
不登校の原因として友達、勉強、先生の悩みなどが挙げられます。しかしそんなにわかりやすい理由であるならば、より簡単に不登校を解決できるはずだとは思いませんか。最近の不登校の原因は複雑化しており”なんとなく行きたくない”というお子さんもいます。
「原因がわからないなら対処できないじゃないか!」と頭を抱える親御さんも少なくありません。
3. 不登校は悪くない?
3-1. 不登校は逃げである
“不登校は逃げ”客観的にはそう見えてしまうかもしれません。「ほかの人は頑張って登校しているのに!」「やるべきことから逃げている!」 不登校は我慢して登校している子どもたちや、またそのような思いを持って登校してきた大人からも、反感を買うことがあるかもしれません。それによって周りの目が怖くなり、罪悪感から不登校を繰り返すという悪循環を招いてしまいます。
3-2. “逃げ”は生きるために必要
では逃げることは悪いことなのでしょうか?「逃げると癖になる」、「継続は力なり」、「あきらめないことが大切」。そう教えられてきた我々日本人にとって、“逃げる”という行為にあまりいい印象を持てない方も多いのではないでしょうか。
しかし“逃げる”という行為は私たち人間にとって不可欠であり、これまでの人類は“今回は相手が強敵だ”と思ったら迷わず逃げることで繁栄してきました。しかし近年の日本ではどうでしょうか?いじめに耐え切れず自殺をしてしまったり、残業時間200時間越えによる過労死に陥ってしまうなど、“逃げる”という選択肢を選べなかった人々の末路は悲劇的なものです。
3-3. 怠けている→× 生き方をさがしている→〇
この記事で一番お伝えしたいことは“不登校の子どもは怠けているわけではない”ということです。
お子さんは「このままじゃいけない」、「このまま学校に行ったところで幸せになれるのか?」、「今の学校(環境)に自分の居場所はあるのか?」、「そもそも自分は何なのだろうか?」、と親御さんの想像以上に悩んでいます。しかしそれをうまく伝えられず、周りの誤解によって不登校がさらに悪化することもあります。
親御さんはまず子どもは自分なりの生き方をさがしているということを理解してください。その点を踏まえるとお子さんに対する「怠けるな!」、「甘えるな!」、「我慢しろ!」という言葉はかなり酷だと思われるのではないでしょうか?
お子さんが不登校になってしまうと、将来が心配になりますよね。
著名人の中にも不登校やひきこもりを経験している人がたくさんいます。不登校になったきっかけと、その後の対策を以下の記事でまとめていますので、一度目を通してみてください。
こちらもCHECK
-

-
不登校・ひきこもり経験のある著名人9人を紹介!芸能人の経験から学ぶ「お子さんへできる支援」
この記事を読むのに必要な時間は約 34 分です。 「うちの子が不登校になってしまった。このまま人生終わりなのだろうか?」 「芸能人や著名人で不登校を乗り越えた人はいる?」 お子さんが不登 ...
続きを見る
4. 親御さんが今すぐできる2つのこと
4-1. その1 情報収集
4-1-1. ネットサーフィン~ポジティブな波に乗る~
情報収集の手ごろなやり方としてネットサーフィンがあります。
ネットサーフィンと聞くとだらだらネットで遊んでいるという印象を受けるかもしれませんが、ここでは必要な情報を自分で選ぶということを意味します。情報を集めるという観点ではネットだけではなく書籍などの情報に触れられるものを利用することも一つの方法です。
ここで一つ質問です。インターネットで不登校と検索するとポジティブな情報とネガティブな情報ではどちらが多く表示されるでしょうか?
もちろん言うまでもなくネガティブな情報が多く表示されます。不登校という言葉自体にネガティブなニュアンスが含まれることも原因かもしれません。これではインターネットのネガティブな波に呑まれてしまいます。
ネットで情報収集される際は、今は生き生きとしている不登校経験者についての記事など不登校に対して前向きな情報をさがしてください。ポジティブな情報を目的に工夫して検索してみると、世の中には元不登校○○として様々な活動を行い、“私でも出来たからあなたもできる!”と人々に勇気を与える方もいます。
不登校という経歴は場合によって、人生における劇的なストーリーの一部として味方になることもあるのです。
4-1-2. まず親御さんが余裕を取り戻す
情報収集によって得られる効果はもう一つあります。
不登校を乗り越えた人たちの存在を知ると「うちの子もきっと大丈夫」と感じられるようになるかもしれません。同じ悩みを抱えている人がいることを知るだけで、気持ちが少し楽になることもあります。
また、さまざまな不登校経験者を知ることで親御さんとしてできることは、学校に行かせることだけではないということに気付くのではないでしょうか。不登校のお子さんの気分に振り回され、感情的になってしまったり、逆に言いたいことを言えなくなってしまったりすることがあるかもしれません。
思いあたる点がある親御さんは、子どもを学校に行かせなければならないと思うあまり、選択肢が限定されてしまっているかもしれません。 まずは情報収集をすることで、視野を広く持ち余裕を持ちましょう
4-2. その2 提案
4-2-1. 進学だけじゃない!卒業のその先を親御さんが見せてあげる
不登校に対する視野が狭いと、どうしても「学校に行かないと就職がない」というような曖昧な説得をしてしまう場合があります。
しかし情報収集を通じて、不登校に対する様々な視点を持てるようになると「今学校に行かないならこういう道もあるらしいけど、どう?」と提案できるかもしれません。
4-2-2. 選ばせる教育が子どもを自立に導く
提案するときに一つ注意することがあります。
子どもが提案に興味を示さなかった場合でも、「せっかくこの子のことを考えているのに...」と気を落とさないようにしましょう。たまたまその提案がお子さんに合わなかっただけなのかもしれません。食いつきが悪ければ次の提案を考えてみましょう。
あくまで最終的な選択権は提案された子どもにあります。この選ばせるという方法が子どもの主体性を育てることになります。
学校にきちんと行き、親の言うことをまじめに聞いてきた、なのになぜか自分のことを自分で決められない大人もたくさんいます。
そう考えると不登校という現状は子どもの主体性を育てる絶好の機会ともいえるのではないでしょうか。
5. まとめ 叱咤激励は承認の上しか成り立たない。まずは認めてあげること
いかがでしたでしょうか?今回は情報収集→提案という方法を紹介させていただきました。情報収集については非常に取り組みやすい内容になっていますので空き時間にお試しください。
提案については実践していただくと、最初はお子さんから煙たがられるかもしれません。しかし繰り返し提案をしていくと、お子さんは“どんな時もお父さんとお母さんは応援してくれる、自分の存在自体を認めてくれているんだ”と実感してくれる時が来ます。
その時に初めて、今までうまく伝わらなかった愛情、言葉が伝わるのではないでしょうか。不登校は悲劇ではなく親子ともに成長するチャンスなのです。