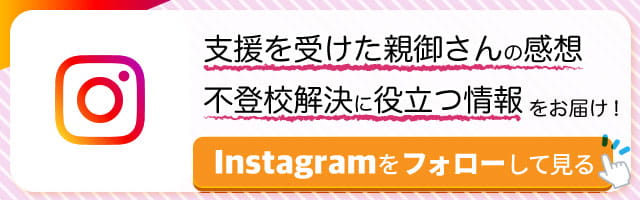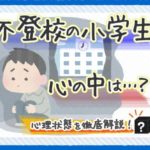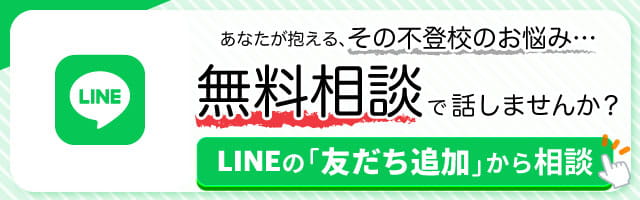この記事を読むのに必要な時間は約 28 分です。
- 子どもに不登校の原因を聞いても「わからない」と言われてしまう
- 原因がわからないため、親としてもどうすれば良いかわからない
不登校の原因は1つではないため、何が原因で不登校になってしまったのか判断するのは難しいものです。
学校に行けない理由がわからなくても、対処方法を知れば、不登校を解決していくことは可能です。
記事では、学校へ行けない理由がわからないとき、親御さんができる具体的な対処方法をお話ししています。
また、最も多い理由も9つご紹介しているため、今のお子さんの心境を探ることもできます。
最後まで読むと、今お子さんが学校へ行けない理由がわからなくても、不登校の根本解決に向けて一歩踏み出すことができます。
【平均3週間で不登校解決プログラム】を展開する小川涼太郎さん監修のもと、お話しする内容は次のとおり。
記事を読むとわかること
- 不登校の原因がわからない理由
- 不登校の原因がわからない場合の対処法
不登校の原因がわからない場合に、親としてどのようにサポートすれば良いかがわかるようになります。
不登校を解決したいときは、スダチにお任せください。お子さんの様子を日々ヒアリングさせていただき、そのときのお子さんに適した接し方をフィードバックしております。
フィードバックに合わせ親御さんが行動してくださっているため、みなさん平均3週間で不登校を解決しています。
\無料相談を申し込む/
1.学校にいけない9つの不登校の原因・理由
不登校には様々な原因があります。
ここでは、文部科学省の調査を基に、不登校の原因別に解説します。
9つの不登校原因はこちら。
- 学業の不振
- 友人関係
- 家庭環境
- 入学、転編入学、進級時の不適応
- 進路への不安
- 学校の決まり
- クラブ活動、部活動
- 先生
- いじめ
では、順番に詳しく見ていきましょう。
1-1. 学校に行けない不登校の原因・理由①学業の不振が原因の場合
最も高い割合となっているのが、学業の不振です。
全体の19%を占めています。
学校は成績の良し悪しで子どもの順位付けが行われるため、成績が悪いと「自分は価値のない人間だ…」と感じてしまい、学校に居づらくなってしまいます。
そのような子どもは、授業の内容が理解できていないことが多いです。
授業の内容が理解できないと以下のような負のサイクルに陥ってしまいます。
授業の内容が理解できない⇒前の授業が理解できていないため、次の授業も理解できない⇒どんどんついていけなくなる⇒テストで良い成績が取れない⇒自己肯定感が下がる⇒学校に行く気がなくなる
このような負のサイクルに入ってしまうと、親としてはなんとか子どもにやる気を出させようと、「なんでこんな点しか取れないの!」「ちゃんと勉強しなさい!」「将来困ってもいいの!?」といった声かけをしたくなることもあると思います。
1-2. 学校に行けない不登校の原因・理由②友人関係が原因の場合
2番目に高い割合となっているのは、友人関係です。
全体の17%を占めています。
学校という何十人の子どもが同じ教室で過ごす中、友人関係が複雑になってしまうことは仕組み上仕方ないところがあります。
もちろん人間なので、合う/合わないはありますし、ケンカをすることもあるでしょう。
そういった友人関係の中で、友達とぶつかってしまい、学校に行きづらくなってしまうことがあります。
友人関係というのはとても難しく、当の本人が何かをしたわけでなくても、友達の輪に入れてもらえなくなることもあります。
1-3. 学校に行けない不登校の原因・理由③家庭環境が原因の場合
3番目に高い割合となっているのは家庭環境です。
全体の15.6%を占めています。
なぜ家庭が原因で不登校に?と思った方も多いと思います。
どのような流れで不登校になるかは、以下の通りです。
親からの過度な期待や家庭環境の複雑さから、家庭での居場所がなくなる⇒子どもに過度なストレスがかかる⇒外での疲れを家で回復することができない⇒エネルギー不足で不登校になる
という流れです。
不登校になりやすいご家庭の特徴は次の記事でも解説しています。
こちらもCHECK
-

-
不登校になりやすい子どもの親や家庭の特徴とは?小学生の事例をご紹介
この記事を読むのに必要な時間は約 35 分です。 お問い合わせ 不登校になりやすい子どもの特徴は? 子どもが不登校になりやすい親や家庭の特徴は? 本記事では、不登校になりや ...
続きを見る
1-4.学校に行けない不登校の原因・理由④入学、転編入学、進級時の不適応が原因の場合
4番目に高い割合となっているのは入学、点編入学、進級時です。
全体の13.5%を占めています。
環境の変化に上手く馴染めなかった結果、不登校になってしまうことはあります。
環境が変わることは、子どもにとって大きなストレスになります。
環境が変わる度に友人関係を作り直すことは簡単ではありません。
1-5. 学校に行けない不登校の原因・理由⑤進路への不安が原因の場合
5番目は進路への不安です。
全体の8.9%を占めています。
漠然とした将来への不安から、不登校になってしまうことがあります。
これは、やりたいことがなく、勉強への意欲もわかず、未来への希望もなく、無気力になってしまった結果、というケースが多いです。
個人的には、「学歴が高い=偉い=幸せ」という価値観が子どもを苦しめてしまっていると考えています。
確かに、学歴が高いことで有利になることはたくさんあります。就職で有利になることも間違いありません。
しかし、人それぞれやりたいことも幸せと思う価値観も異なります。
それを画一的に“学歴”という1つの物差しで測ることが本当に正しいのでしょうか。
子どもの幸せはどこにあるのか、その問いを常に持ち、子どもと接することが大切だと考えています。
1-6. 学校に行けない不登校の原因・理由⑥学校の決まり等が原因の場合
6番目は学校の校則です。
全体の3.8%を占めています。
子どもは、校則が嫌で不登校になるわけではなく、校則の意味に納得ができないことから嫌気がさしてしまい、不登校になってしまいます。
先生としては、その校則に何の意味があるかを説明する義務があるはずですが、「決まりだから」という理由でまともな説明がされないこともあります。
理由がないものに子どもが納得できるはずがありません。
1-7. 学校に行けない不登校の原因・理由⑦クラブ活動、部活動が原因の場合
7番目はクラブ活動や部活動です。
全体の1.8%を占めています。
部活動での先輩との上下関係、過度に厳しい練習、顧問の先生のパワハラなどにより、部活動に行くことが辛くなり、不登校になってしまうというケースです。
「無理に部活動を続ける必要はないよ」という声かけを子どもにしてあげましょう。
親として子どもの意志を尊重していることを伝えてください。
親の期待に応えたいという思いから、限界まで部活動を続けてしまうケースは実際にあります。
良くある危ないパターンは、親の夢を子どもに押し付けてしまうことです。
例えば、子どもにプロ野球選手になってほしいという思いから、子どもに野球を押し付けてしまうというのはよくある例です。
それ以外にも、“継続できない=悪”という考えから、部活動を辞めることに否定的になってしまう親も多いです。
確かに、継続する力は社会に出ていく上でも重要なスキルです。
しかし、学校に行けなくなるほど追い込まれてしまっては元も子もありません。
自分が苦も無く続けられること、もっというと、楽しいと思って続けられるものを探すことが大事だと考えています。
日本では、苦しみに耐え忍ぶことが美徳とされる価値観があります。
このような価値観が、多くの子ども達を苦しめてしまっているように思います。
個人的に、今の時代は「苦しみに耐える」よりも「楽しみを見つける」ことが重要と考えています。
昔と違い、様々なキャリア・生き方が認められる時代が来ています。
自分の好きなことを仕事にしている人がたくさんいます。
1-8. 学校に行けない不登校の原因・理由⑧先生が原因の場合
8番目はこちらです。
全体の1.1%を占めています。
先生が原因の場合は、以下の記事にて詳細に記載しております。
1-9. 学校に行けない不登校の原因・理由⑨いじめが原因の場合
最後はこちらです。
0.4%と非常に低い割合になっております。
いじめが原因で不登校になってしまうことについて、理由の説明等は不要だと思いますので、対策について述べられればと思います。
単にいじめへの対策というと、かなり話が広がってしまうため、ここでは親としての対応に絞って考えたいと思います。
まずは、何が起きても味方であることを子どもに伝えましょう。
いじめられている子どもにとって学校は地獄です。
自分の味方は誰もいないような気持ちになり、孤独を感じています。
そんな中、親が味方でいてくれることは、子どもの気持ちをすごく楽にしてくれます。
2. 理由なく不登校になることはある
ここまで様々な原因について述べましたが、結論として、理由なく不登校になることはあります。
不登校になる原因というのは、本人も分からないことが多いのです。
理由としては、不登校の原因は1つではないケースが多いためです。
不登校は複数の原因が重なり合うことで起きてしまいます。
上記で述べた様々な理由が1つ、2つと重なっていくことにより、子どもは学校へいく意欲を失ってしまいます。
3. 不登校の原因がわからない時の対処法
子どもが不登校になった原因はわからないことが多いです。
「なぜ学校に行けないのか。」「なぜ自分が不登校になっているのか。」お子さん自身原因をわかっていないケースもあります。
不登校の原因がわからないときの対処法として大切なことは次の通りです。
- 子どもの気持ちを受け入れる
- 子どもが安心して前へ進める環境を用意する
2つのことを意識するための行動方法を以下でご紹介します。
4. 学校に行けない原因がわからない時にやってはいけないことは?
お子さんが学校に行けない原因がわからないとき、次の4つのことを行うのは避けましょう。
- 子どもを無理やり学校に行かせる
- 不登校は悪いことだと子どもに言う
- 不登校の子どもを見守り続ける
- 不登校となったきっかけの理由を無理に追求する
お子さんが不登校のとき、親御さんと正しい信頼関係を築けていないこともあります。
お子さんの気持ちを認めず無理矢理学校に行かせると、親子の関係に亀裂が生じます。
親子関係が悪化すると不登校の解決がさらに難しくなる可能性もあります。
また、不登校のことを悪く言ったり、不登校はいけないことだと叱ったりすることも避けていただきたいです。
お子さんは、学校へ行けないことに罪悪感を感じ、自分自身を責めていることがあります。親御さんから「不登校は悪いこと」とさらに責められてしまうと、お子さんは自己肯定感を完全に失い塞ぎ込んでしまいます。
さらに、お子さんを見守り続けて、不登校を放置することはおすすめできません。
不登校の原因がわからないとき「子どもの負担にならないように」とお子さんを見守っている状況かもしれません。
見守り続けることは、不登校を放置した状態が続いてしまうことになります。
不登校を解決したいと思っているのならば、見守るだけでなく親御さんが一歩踏み出して解決に向けて行動しましょう。
また、お子さんに対して原因を追及しないことも大切です。無理に原因を追究しようとすると、悩んでいるお子さんの心を追い詰めてしまう場合もあります。
5. 学校に行けない原因がわからない時にやるべきことは?
学校に行けない原因がわからないときにやるべきことは次の2つです。
- 「学校に行きたくない」「学校に行けない」「自分がよくわからない」という子どもの気持ちを認めて受け入れる
- 子どもが愛情やエネルギーをチャージできる居場所を作る
お子さんのつらい気持ちを認め受け入れて、どのような状況であっても親は味方であることを伝えましょう。
「この親がついているから前へ進んで大丈夫なんだ」とお子さんがエネルギーや愛情を蓄え前へ進めるような家庭環境を作ることが対処法です。
また、学校に行けない原因の本質は「お子さんに愛情がうまく行き届いていないこと」「お子さんが愛情をうまく受け取れていないこと」にあります。
お子さん合った伝わりやすい方法で愛情を注ぐことが大切です。
お子さんを甘やかし過ぎることはよくありませんが、正しい親子関係を築きながら家庭でお子さんに愛情をチャージしてあげること、そしてお子さんが安心して前へ進める居場所を作ってあげることを意識しましょう。
6. 学校に行けないどんな原因でも共通してあるのは”エネルギー不足"
不登校の原因が明確な場合、分からない場合、どちらにせよ共通しているのは、子どもの“エネルギー不足”です。
つまり、どのような原因であれ、子どもがエネルギーを蓄えられる環境を作ることが大事になります。
7. 親としてできる対策は元気を与えること
親としてできることは、家庭を子どものエネルギーが蓄えられる環境にすることです。
学校、塾での勉強、部活動など、子どもは常に多くのエネルギーを必要とされる環境があります。
エネルギーを蓄えられる場所がないと、子どもはエネルギー不足に陥ってしまいます。
最もエネルギーの回復場所としてふさわしいのは、家庭です。
家庭をそのような環境にするためには、親の子どもへの接し方が最も重要になります。
以下にて、子どものエネルギーを奪う声かけ、エネルギーを蓄える声かけをまとめました。
子どものエネルギーを奪う声かけ
- 理由も説明せずに「やめなさい」と言う
- 子どものチャレンジに「できるわけないでしょ」、「もっと現実を見なさい」と言う
- 何かにつけて「私に言うとおりにしなさい」と言う
- 「普通は〇〇だから、そんなことするのはおかしい」と言う
- 「△君に比べて、あなたはダメな子ね」と言う
子どものエネルギーを蓄える声かけ
- 小さなことでも「ありがとう」と感謝の気持ちを伝える
- 「どんなことがあってもあなたの味方だよ」と伝える
- 子どものチャレンジに「あなたならできるよ!」と伝える
- 失敗したときにも「ナイストライ!次も頑張ろう!」と伝える
親の日々の声かけ次第で、家庭がエネルギーの回復場所になるかが決まります。
親が自分を認めてくれていると思うと、自己肯定感が育ち、子どもは親といることが心地よく感じられます。
逆に否定されていると感じると、家庭での居心地が悪くなってしまいます。
とはいうものの、肝心の親が会社や家庭環境で疲弊してしまっている場合も多いです。
まずは、親御さんが元気になる必要があります。
8. よくある質問
お子さんの不登校の原因がわからないときによくある質問にお答えします。
8-1.学校に行けない不登校の理由はどんなものがある?
不登校には7つの傾向が見られることがあります。不登校の傾向がわかればお子さんの気持ちや不登校となったきっかけの理由を探る手がかりになるかもしれません。
不登校のきっかけやお子さんの気持ちを知りたいときには、不登校の傾向をご参考になさってください。
8-2.不登校になりやすい家庭は?
不登校の原因はさまざまですが、根本にあるのは「親の愛情が子どもにうまく行き届いていないこと」にあります。
親御さんはお子さんにたくさんの愛情を注ぎ育児なさっていることと存じます。
しかし時に、お子さんが愛情をうまく受け取れていないこともあります。
そのため、お子さんに伝わりにくい方法で愛情を伝えているご家庭、親がお子さんに無関心で愛情を示していないご家庭は、不登校になりやすいと言えます。
不登校になりやすい家庭や親の特徴については下記記事で詳しく解説しています。
8-3.不登校はなぜ増えた?
文部科学省の発表によると不登校は8年連続で増加しています。不登校は1966年の統計開始以降、過去最多になりました。
なぜ不登校が増えているのか、考えられる理由は2つあります。
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により外出や学校に通うことが難しくなっている
- 生きづらさの低年齢化が進んでいる
人間関係や、やらなければならないことで悩むのは大人だけではありません。
子どもも同じです。
クラス内の人間関係に疲弊する子どももいれば、勉強や部活に疲れてしまう子どももいます。自分や他人を比較して悩む子どももいます。
大人たちが社会生活で疲れて悩むように、お子さんも疲れや悩みを抱えてしまい、不登校に繋がってしまうケースがあります。
上記のように悩むきっかけはさまざまですが、原因の本質は親の愛情がうまく行き届いておらず、お子さんの自己肯定感が大きく低下していることが考えられます。
お子さんに愛情が行き届き自己肯定感を育てることができれば、社会生活でどんな壁に直面しても、自分の力で乗り越えることが可能です。
不登校が増えた原因が明確に分析できなくても、お子さんに伝わりやすい方法で愛情を注ぎ、自己肯定感を育てることが大切です。
また、どんなときも味方でいることを示し、お子さんが安心して前へ進める居場所を作りましょう。
5. まとめ
子ども自身が不登校の原因がわからない場合は多くあります。
そこで気を付けるポイントは、“必要以上に追及しない”ことです。
子ども自身も原因がわかっておらず、どうすれば良いか分かっていません。
無理に追及されるほど、子どもはエネルギーを奪われてしまいます。
大事なことは、原因の追究ではなく、子どもがエネルギーを蓄えられる環境を用意してあげることです。