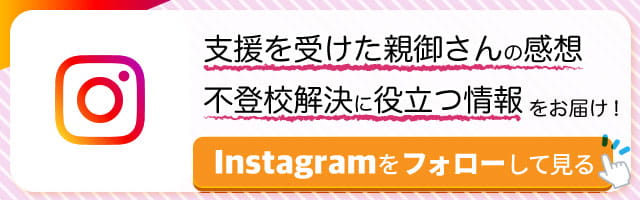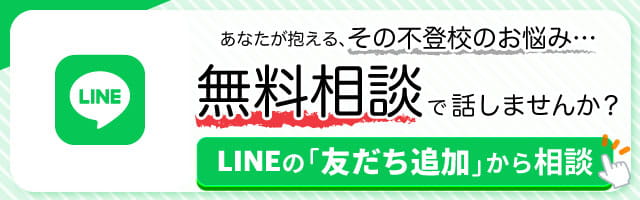この記事を読むのに必要な時間は約 55 分です。
お悩みポイント
- 不登校だった中学生の特徴は?
- 不登校だったお子さんの経験談は?
本記事では不登校だったお子さんの特徴や経験談について紹介しています。
また、不登校だったお子さんの将来についてもお話しています。
親御さんが不登校の子どもの特徴や経験談、将来を知ることは不登校のお悩み解決に役立てることが可能です。
それだけでなく、実際に不登校だったお子さんの体験談もご紹介します。
この記事を読めば不登校のお子さんとの今後を考える手がかりがつかめます。
この記事でわかることは、次の3つです。
・中学生時代の不登校経験は、子どもの人生に良くも悪くも影響する
・不登校を後悔するかしないかは「今と過去の自分を受け入れられるか」
・子どもが求めているのは「心のケア」「人とのつきあい方」「勉強のサポート」
将来、子どもが中学生時代を振り返ったときに「不登校だったから…」と後悔しないためのサポート方法についてもお話しています。
子どもの「その後」を心配している親御さんの不安が少しでも軽くなれば幸いです。
\スダチの無料相談を確認する/
以下では、中学生の3年間不登校が続く時の進路について、道標を提示しています。
ご参考になさってくださいね。
こちらもCHECK
-
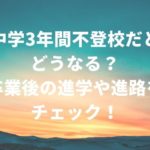
-
中学生の3年間不登校だとどうなる?卒業後の進学や進路をチェック!
この記事を読むのに必要な時間は約 56 分です。 中学3年間不登校だとどうなってしまうの? 3年間不登校のとき、高校やこの先の進路はどうなるの? 結論から申し上げると、中学の3年間不登校 ...
続きを見る
1. 不登校だった中学生の「その後」の実態と心情は?
短期的に見れば中学校卒業後の進路選択、
長期的に見れば中学校卒業後から続く人生…
と、不登校経験はなにかしらの影響を与えます。
そして、不登校経験の「影響の大きさ」や「影響がプラス・マイナスになるか」は、
子ども本人の不登校に対するとらえ方・解釈の仕方次第です。
不登校という「つまずき」を乗り越える・学ぶことができれば、
子どもは不登校経験をチカラに変えて成長することができます。
もし仮に、似たような状況になっても、問題解決のために努力できますし、
少なくともはじめから諦めてしまう可能性は低くなると言えます。
反対に不登校という「つまずき」を乗り越えられない・なにも学ぶことができなかった場合、
不登校体験は「挫折」として、子どもの心に深く残ります。
不登校期間が長引くほど学校復帰が難しくなるのと同様に、
不登校に対する「挫折」を放っておくほど、「その後」に与えるマイナスの影響も大きくなります。
不登校に対するとらえ方・解釈の仕方を思春期の子ども1人の力で得るのは至難のワザ。
そこで必要になるのが、親御さんのサポートです。
不登校経験が子どもの「その後」に与えるマイナスの影響を小さくするためにも、
経験者たちの実態や求められている支援を把握したうえで、子どもには今のうちから可能な限りのケアとサポートを行っていきましょう。
2. 中学生時代に不登校だった人の将来はどうなった?
ここからは、中学生時代に不登校経験があった人たちの「その後」を見ていきましょう。
この調査は、文部科学省が平成23年〜24年(2011年〜2012年)に行った調査です。
調査の対象は、平成18年(2006年)時に中学3年生で不登校だった子どもたち。
5年後、20歳を迎えた段階での現在の状況・不登校当時のこと・卒業後の状況を調べています。
2-1. 中学生時代に不登校だった人たちの「その後」からわかること
20歳を迎えたかつての不登校経験者たちも、ごく当たり前に「今」を生きています。
不登校だった人たちも、働いていたり勉強を続けているのです。
学校に通っていた人たちとなんら違いがないことが見て取れるのではないのでしょうか。
20歳現在の就業・就学状況
- 就業のみ ……………34.5%
- 就学のみ ……………27.8%
- 就学・就業 …………19.6%
- 非就業・非就学……18.1%
(専業主婦・主夫、会社経営者含む)
半数以上の約55%の人が仕事に就いて働いており、
約48%の人が学生として学んでいることがデータ上の数字からわかります。
雇用形態は以下の通りです。
20歳現在の就業状況
- 正社員 ………………………9.3%
- パート・アルバイト …32.2%
- 家業手伝い・会社経営…3.4%
就学先の内訳はこちら。
20歳現在の就学先
- 大学・短大・高専 ………22.8%
- 高等学校 ………………………9.0%
- 専門学校・各種学校等…14.9%
この追跡調査では、単なる就業・就学の状況だけではなく、
中学校卒業後と20歳の今を比較して自分が成長したと認識している点も調べられています。
それぞれ成長した点に違いがありますが、
就業もしくは就学・就業者は、就学のみの人に比べて、
成長したと感じられることの数をより多く挙げているのが特徴です。
就業・就学状況と成長したところ
- 就業・就学者
自分で働いて収入を得る、学力が身についた、将来への希望が持てる、
身体の健康、自分に自信が持てる - 就業者
自分で働いて収入を得る、生活リズムが整う、人と上手く付き合える、
家族間の関係改善、身の回りのことをじぶんできる - 就学者
学力が身についた、将来の希望が持てる
就業者の方がより自分への自信を取り戻していることが特徴的です。
仕事は学校の課題とは違い、単純にこなすだけで済むものではありません。
成果を出すことで「自分にもできることがある」と実感し、
さらに対価として金銭をいただくことが自分への自信にもつながることで、
自分が成長していると認識しているのでしょう。
2-2. 中学生時代に不登校だった人たちが中学校卒業後に進んだ道は?
上記は、20歳を迎えた時点の状況でした。
ここからは時代を遡り、中学生時代の当時の状況を見ていきましょう。
中学3年時に進んだ“進路”
- 高等学校などへの進学………約85%
(就学のみ、就学+就業含む) - 進学せずに就職………………………6%
- 進学も就業もしない ……………8.4%
8割以上の人が高等学校への進学を選択しています。
高い進学率は世間一般の「中学を出たら高校に進む」という流れに沿ったものもあるでしょう。
他にも、適応指導教室やフリースクールなどの不登校支援による効果もありますが、
高等学校は全日制ではなく通信制を選べるなど、
子ども本人が自分に合う進学先を選べることが影響しているとも考えられます。
また、高等学校卒業後の大学・短大・専門学校への進学率も20%を超えています。
「不登校だから高校に進学できない」「大学に入れない」ことはないのです。
2-3. 高校からは思い通りの進路に…とも限らない
中学校卒業時の進路について希望どおりだったか・違っていたかを調査した結果、約半数ずつで答えが別れました。
中学校を卒業したとき、希望どおりの進路に進めた?”
- 希望どおりの進路だった…43.8%
- 希望とは違っていた ………54.3%
なんと、本来希望していた進路には進めなかったと、半数以上の人が感じているのが実情です。
最終的に進学を決めたのは自分自身のはずなのに、希望とは違うことになったのはなぜなのでしょうか。
2-4. 希望した進路に進めなかったのは、不登校の影響?
「希望していた進路に進めなかった」人たちのうち、
「不登校」が影響していると感じている割合は、7割を超えます。
希望どおりの進路でないことに“不登校”が影響している?
- 影響がある …………76.5%
- 影響していない……23.5%
「希望どおりの進路に進めなかったのは、不登校がなにに影響したからなのか」を
聞き取り調査の回答から見ていくと、進路選択と勉強面に強く影響していることがわかります。
不登校による勉強不足は、「その後」の高校生活でも「勉強についていけない」感覚を生じさせるなど、長期的な後悔を生み出すことになるのです。
数字が示すように、希望する進路に進めなかったことには不登校が影響すると考えて間違いはないでしょう。
こちらもCHECK
-

-
不登校は何人に一人?人数や割合、増えすぎている実態は?小学生・中学生・高校生ごとに不登校になった子どもたちの今を知る!
この記事を読むのに必要な時間は約 25 分です。 「子どもが不登校になってしまった…実際のところ不登校の子どもは何人に一人いるのかを知りたい」 「不登校の子どもは増えている?割合や現状を知りたい」 不 ...
続きを見る
3. 「その後」を迎えた人たちの特徴、中学生時代の不登校経験を「どう思っている?」
「自分が不登校であったことを、どのように思っているか?」
この問いに対してもっとも多かった回答は「行けばよかった」という後悔です。
不登校で学校に行かなかったことを、今、考えると…
- 行けばよかった …………37.8%
- しかたがなかった………30.8%
- 行かなくてよかった……11.4%
- 何とも思わない …………17.0%
大きく分けて、不登校を「後悔している」「後悔していない」の2パターンに分かれます。
ここからは2つの違いを見てみましょう。
3-1. 「後悔している」人の特徴
後悔している人たちの多くは、学校に行きたかったけど、行けなかった人たちです。
とくに後悔していることは、学力・勉強面と進路。
20歳を超えてもなお、学校に通っていなかったから
「自分は一般常識が欠けている」「対人関係に乏しくて未熟」だと、
自分の短所の原因を不登校に求めがちです。
過去を悔いる気持ちが強いため、不登校にならなかったら
「もっといい学校に行けた」「ふつうの人と同じように…」と、
今の自分に対して劣等感を抱えています。
不登校当時から現在にかけて、不登校であることを「問題と感じている」ほど、
現状に対してマイナスの影響が大きくみられます。
以下では、不登校を後悔しているお子さんの実際の声をご紹介いたします。
学力や勉強に関する後悔
- 学校や会社で一般常識が欠如していると感じた
- 行きたい学校があったのに学力不足で進学できなかった
- 高校に進学したが学力不足で周囲について行けない
友人に関する後悔
- 留年などで同級生と学年が別になり寂しかった
- 不登校だったため学生時代の友人が少ない
- 不登校だったため学友との楽しい思い出が少ない
- 不登校だったことで周囲に劣等感を持ってしまう
進路に関する後悔
- 進路の選択肢が狭くなったと感じる
- 進路を選ぶ際に「自分では勉強不足だ」と落ち込んでしまった
- 進路を選ぶ際に不登校がマイナスになったと感じた
思い出に関する後悔
- 不登校だったため学校の楽しい思い出が少ない
- 同年代と学校時代の思い出を共有できない
- 同窓生の間で浮いてしまう
3-2. 「後悔していない」人の特徴
後悔していない人たちは、休んでいた・苦しんでいた時間があったからこそ今の自分があると、
過去の自分も今の自分も肯定的に受け入れています。
本音を言えば「後悔することもある」けれど、
乗り越えることができたと実感することで、
自分が不登校であったことに意味を見出しているケースも少なくありません。
ツラい期間に出会った人、支えてくれた人たちへ感謝の気持ちを抱いていること、
多くの人とは違う経験ができたなど、不登校経験を“学校に行けなかった”という視点以外から見ていることも特徴です。
不登校であることを「しかたがなかった」「とくに問題と感じていない」ほど、
現状へのマイナスの影響は小さく、場合によってはプラスにはたらいているとも見て取れます。
以下では、不登校がプラスに働いたと感じているお子さんの声をご紹介します。
成長に関するプラス
- 不登校があったからこそ今の自分があると前向きに思える
- 不登校を乗り越えられたおかげで精神的に強くなれた気がする
- 今の自分がいるのは不登校を経験したからこそだと思っている
成長に関するプラス
- 不登校があったからこそ今の自分があると前向きに思える
- 不登校を乗り越えられたおかげで精神的に強くなれた気がする
- 今の自分がいるのは不登校を経験したからこそだと思っている
視野に関するプラス
- 不登校になったことで物事の視野が広がったと感じている
- 不登校になったからこそ学べたことがあった
- 不登校になる子どもの気持ちを理解できるようになった
- 進学の良い面や悪い面を冷静に見極めることができた
出会いに関するプラス
- 不登校になったことで新しい友人に出会えた
- カウンセラーなど周囲が自分を支えてくれて感謝している
- あらためて親の愛情に気づけた
経験に関するプラス
- 学校ではできない経験を積めた
- 不登校という経験が自分の経験値になった
その他のプラス
- 不登校だったが今は仕事もして友人もいるので充実している
- 無理して学校に行ったら心を壊していたと思うので不登校で自衛できた
- 学校に行ったからといって今より良い人生だったかわからない
4. 不登校経験者の体験談
不登校を後悔するかプラスにするかはお子さんによって違います。不登校のお子さんがどう思っているのか更に詳しく知っていただくために、体験談を2つご紹介します。
4-1. 不登校を後悔していない人による体験談①
中学時代に不登校だった私は学区の離れた高校に進学しました。かなり離れた地域にあった高校だったので、クラスメイトはおろか同学年の人たちは誰一人進学先に選ばなかった高校です。
高校では充実した時間を送れましたし、かけがえのない友人もできました。私が不登校でなければ、離れた地域にある高校に進学しようとは考えなかったでしょう。中学時代の不登校を後悔したことはありません。
4-2. 不登校を後悔している人による体験談②
中学の時に不登校になりました。当時を思い出すと「後悔している」と「あれで良かった」という気持ちが半々です。
後悔していることは、学校行事をあまり楽しめなかったこと。運動会や修学旅行、文化祭など学校行事を友人と思い切り楽しんでみたかったです。同年代の会話で「学生の楽しい思い出」が出てきても、それらが楽しいということすらわからないので、残念だったという気持ちがあります。
ただ、後悔ばかりではありません。不登校で良かったと思えることもありました。
不登校で良かったと思ったのは、カウンセラーや同じ悩みを持つ友人たちと出会えたことです。親が自分に愛情を注いでくれていることにも気づけました。不登校だったからと言って悪いことばかりではなかったです。
5. 中学生時代に不登校経験があっても「その後」を後悔で終わらせないためには?
当時、不登校だった子どもたちが求めていたことを読み解くと、
今現在、不登校の子どもに必要な支援や、求められていることが見えてきます。
中学3年生の時、当時の子どもたちから求められていた支援は多岐にわたりますが、
大きく分類すると3つに分けられます。
不登校の子どもの「あればいいのに」は?
・心理的な支援
回答者の3割以上がもっとも求めていたのが、心のサポート。
「心の悩みについて相談ができれば…」と、自分の心情を安心して出せる場所を必要としていました。
・友人関係を改善するための支援
こちらも3割の子どもたちが求めていたことです。
上記が自分の心の悩みを打ち明けることに対して、こちらは相手に自分の感情を伝える方法など、
人間関係構築や人づきあいにまつわることの手助けとして求められていました。
・進学のための学習支援
回答者の2割が求めていた支援です。
不登校を後悔する人の多くが勉強面や学歴にコンプレックスを抱える現状を見ると、
勉強の遅れを取り戻すことに加え、進路対策のサポートも必要であることがわかります。
いわば学校生活・学生生活を送るにあたっての、すべてにかかわることで支援が求めれています。
とはいえ、親御さん1人で子どもの“声”に、すべて応えようとする必要はありません。
今は不登校への支援体制も多くあるので、
スクールカウンセラーや適応指導教室、相談センターなど、外部のサポートも利用しましょう。
外とのつながりをつくることで家以外にも居場所ができますし、
他人との関わりをきっかけに不登校や生活状況が改善する可能性も高まります。
6. 子どもが「その後」を後悔しないために、親御さんができること
不登校経験がどう影響するかは、子ども本人の不登校に対するとらえ方・解釈の仕方次第です。
過去の事実を受け入れて現状を認識し、今からどうすることが最善なのかと考えられるほど
“不登校”をすんなり受け入れられれば理想的でしょう。
しかし現実問題、不登校真っただ中の子どもが
「不登校だったけど、学びや出会いがあった」「ツラい経験もムダにはならない」と
考えることは容易にできることではありません。
例えるなら、
大キライな食べ物をムリやり食べさせられてパニックになっている人に、
「大キライなものでも毎日食べられるくらい大スキになろう!」と言っているようなものです。
まずは、子どもが“今”の現状を受け入れられるよう、心身を回復させてあげてください。
心身のエネルギーが回復すれば、子ども自ら折り合いをつけられるようになります。
お子さんの今後のために、親御さんのできる対応を6つご紹介します。
6-1. 対応①専門家に相談する
不登校のお子さんがその後を後悔しないために、専門的な支援を得意とする民間団体のサポートを受けることがおすすめです。
さまざまなお子さんの不登校を解決してきた団体であれば、今不登校のお子さんがどんなことを求めていて、解決するためにどんな行動を起こせばいいのかがわかります。
そして、お子さんの状況に合わせた適切な支援を行い、不登校を解決することが可能です。
スダチの支援では、脳科学に基づいた視点でそのときのお子さんに合わせた最適な接し方をサポートしております。
親御さんがフィードバックに基づき、積極的に行動してくださっているおかげで、お子さんたちは、平均3週間で不登校を解決しています。
無料オンラインセミナー動画をご視聴いただいた方に、無料オンライン相談を実施しています。1対1で顔出しも不要です。ぜひ一度現状のお子さんの様子をお聞かせください。
\無料相談を申し込む/
6-2. 対応②お子さんの気持ちを理解する
お子さんの気持ちを理解し、受け入れてあげることが大切です。
理解して受け入れてあげることにより「親に気持ちを認めてもらえた」「この親がいれば前へ進んでも大丈夫だ」とお子さんは安心して前へ進むことができます。
不登校のお子さんは自分の気持ちを上手く伝えられない状態にあります。お子さんが気持ちを伝えられるように、日常会話や行動を通じて触れ合いを増やすことが重要です。
たとえば、一緒にテレビを見たり、料理をしたりして、少しずつ会話をするのも良い方法です。
スポーツなどを通して親子の共通体験を増やし、そこからお子さんの思いを引き出しても良いでしょう。
会話や行動を通じてお子さんの気持ちを理解するよう努めることが重要です。
6-3. 対応③お子さんに親の気持ちを伝える
不登校のお子さんに親御さんができることは「何よりも大切な存在であること」「いつも味方でいること」を伝えることです。
親御さんが明確に言葉にしてお子さんへの気持ちを伝えることで、お子さんは「親に自分の気持ちや不安を話しても大丈夫かもしれない」という安心感を持ちます。
お子さんの不安を解消するためにも、気持ちは積極的に伝えてあげてください。
6-4. 対応④お子さんの家以外の居場所を探す
不登校のお子さんの居場所は自宅だけです。不登校の期間が長引くとお子さんは社会の中に自分の居場所がないように感じてしまうことでしょう。自宅以外にも「あなたの居場所はある」と伝え、実際に居場所を作ってあげることが重要です。
社会と関われるお子さんの居場所としては、同じようなお子さんが通うコミュニティや民間団体の集まり、習い事などが考えられます。お子さんの興味の方向性なども考えながら、居心地の良い場所を作ってあげてください。
ただ、不登校になっているお子さんの場合は外に出ること、人と関わることに対して臆病になっていることも少なくありません。新しい居場所に馴染むまで、参加を無理強いすることはやめましょう。お子さんが主体的に新しい居場所に参加できるよう、親御さんは居場所の選択肢を与えることを意識なさってください。 選択肢の中からお子さんが主体的に選べるようにしましょう。
不登校のお子さんが社会とのつながりを持てるコミュニティや、居場所の作り方については次の記事でお話ししています。こちらも参考にしていただけると幸いです。
こちらもCHECK
-

-
学校以外のコミュニティは何がある?不登校の子どもが交流できる居場所の探し方を紹介
この記事を読むのに必要な時間は約 31 分です。 「不登校の子どもが参加できる学校以外のコミュニティはどんなところがある?」 「学校以外のコミュニティに参加するのは、不登校解決につながるの?」 お子さ ...
続きを見る
6-5. 対応⑤お子さんの勉強する機会を作る
不登校のお子さんは学校で毎日授業を受けるわけではありません。そのため、学力に関する悩みを抱えがちです。不登校を後悔している声には実際、「勉強の遅れ」や「学力の問題で希望先に進学できなかった」などがありました。
お子さんが「頑張りたい」と思えたときに困らないように、勉強の機会を作ることをおすすめします。家庭教師や塾、通信講座など、お子さんにあった勉強方法を一緒に探してあげてください。
勉強の機会を設けておくことで、やりたいことができたときにお子さんの助けになることでしょう。また、勉強を通し一つ一つの課題をクリアすることによりお子さんの自己肯定感も育ちます。
お子さんが勉強に取り組んでいる際は、結果に目を向けるのではなく、頑張って取り組む姿勢に目を向けて、お子さんをたくさん褒めてあげましょう。
6-6. 対応⑥お子さんに「進学できる選択肢があること」を伝える
不登校だと進学は難しいと考えているお子さんもいます。不登校でも進学できる高校や大学はたくさんあります。「中学不登校だからといって進学できないわけではない」「進学という選択肢を選べる」ということを、親御さんはしっかり伝えてあげてください。
たとえば高校の場合、出席日数を問わない高校や学力試験のない高校などもあります。毎日通学しなくても良い高校や、不登校児を積極的に受け入れている学校などもあります。
中学不登校でも「受験できる」「歓迎してくれる学校がある」「いつでも社会と関われる」と伝え、お子さんの将来を応援してあげることが重要です。
中学生で不登校になったときの高校受験の選択肢は以下でお話ししています。
こちらもCHECK
-

-
不登校でも高校受験できる!内申書・欠席日数・学校選びまで徹底解説
この記事を読むのに必要な時間は約 29 分です。 お悩みポイント ・子どもが不登校で…高校受験なんてできるの? ・内申点、欠席日数、学校選び…気になることが多くて… ・仮に合格したとして ...
続きを見る
高校生で不登校になったときの大学受験の選択肢は以下でお話ししています。
こちらもCHECK
-
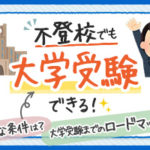
-
不登校でも大学受験できる!大学受験に必要な条件とロードマップ!
この記事を読むのに必要な時間は約 34 分です。 高校生の子どもの不登校が続いている…。大学受験するには転校しかないの? 子どもの不登校を解決する方法が知りたい。 結論から申し上げると、今高校生のお子 ...
続きを見る
7. 「その後」を後悔しないために行動すると見えてくること
親子・家族との関り合いで心のエネルギー回復をしつつ、
外とのつながりも維持していくことは、結果として不登校問題の解決にもつながります。
不登校問題が解決したとなれば、子どもは1つ「つまずき」を乗り越えたということ。
多感な時期に困難と向き合い、ツラいこと、苦しいことを自分なりに乗り越えた経験は、
「その後」の人生において大きな糧となります。
中学時代を振り返っても「不登校経験があったら今の自分がある」と
自信を持って言えるようになるでしょう。
8. 中学生時代に不登校を経験した私の「その後」
実は私も、今から約10年…15年前…小学生と中学生時代に不登校を経験しました。
ふつう、10年以上も前のことを「あぁ言われたから、こうだった」と覚えていたり、
「だから私は…」と引きずっている人は滅多にいないように思われるかもしれません。
ところが私は、ずいぶん長いこと自分が不登校であることに負い目を抱えていました。
けれども近頃は、こう思えるようにもなりました。
「多少の遠回りはしたけれど、これはこれでいいのかもしれない」
たしかに未だに「あの時ああしていれば…こうしていれば…」と後悔することも事実です。
後悔からの空想話はそこそこに、過去に起こった事実だけを事実として受け入れ、
その後にどう意味づけるのか。どう解釈するのか。
現実に目を向けることから、すべてがはじまり、少しずつ前に進めるのではないかと思います。
9. 中学不登校生の特徴に関する質問
補足として中学不登校生の特徴についてよくある質問をご紹介します。
9-1. 不登校の親の特徴は?
次のような特徴に当てはまる親御さんのとき、お子さんが不登校になりやすいことがあります。
- 子どもを感情的に叱っている
- 過干渉だったり管理しすぎたりしている
- 子どもを放置しすぎている
お子さんが不登校になりやすい親御さんの詳しい特徴は、次の記事でも解説しています。
こちらもCHECK
-

-
不登校になりやすい子どもの親や家庭の特徴とは?小学生の事例をご紹介
この記事を読むのに必要な時間は約 35 分です。 お問い合わせ 不登校になりやすい子どもの特徴は? 子どもが不登校になりやすい親や家庭の特徴は? 本記事では、不登校になりや ...
続きを見る
9-2. 子供が不登校になりやすい家庭の特徴は?
お子さんの不登校の根底にあるのは愛情の問題です。親御さんはお子さんのことを大切に思っていることと存じますが、時にお子さんに愛情がうまく行き届いていないことがあります。また、お子さんもうまく愛情を受け取れていないこともあります。
そのため、親御さんの愛情がうまく行き届いていないご家庭のとき、お子さんが不登校になりやすいと言えます。
9-3. 不登校になる子供の特徴は?
不登校になる子どもには次のような特徴があります。
- 主張が強すぎる
- 人にどう思われているか気になる
- 親に対してわがままが多い
- 寝起きが悪い
- 無気力である
前述の子どもは対人関係や家庭環境、本人の気持ちなどが影響して不登校になりやすいと考えられます。
10. まとめ
中学生時代は、人生で1度しかありません。
多感な10代に、不登校であったことは「その後」になにかしら影響を与えますが、
「後悔するか」「後悔しないか」は「その時とその後」の本人次第です。
子どもが「その後」を振り返って、後悔しないためにできることは…
まずは子どもが“今”の現状を受け入れられるように、心身のエネルギー回復を!
そのためにできることが、次の3つです。
・子どもを褒めて、子どもの自己受容力・自己肯定感を高める
・生活習慣を正しくする
・子どもに考える時間を与える
子どもが自分で自分のことを見つめ、受け入れられるようになれば、
自分の頭で考えて、自然と不登校と折り合いをつけられるようになります。
生活習慣が正しいと、外とのつながりもつくりやすく、学校復帰へのハードルも下がります。
心理的・人付き合いの方法・勉強面は外部の支援も活用しましょう。
親御さん1人で子どものあれこれを解決しようと、ムリをしないでください。
子どもが外とのつながりを持っていることが不登校解決のきっかけになる場合もあるため、
スクールカウンセラーや教育センターなどを積極的に利用しましょう。
不登校の中学生をお持ちの親御さんが心配している、子どもの「その後」について、
この記事がなにかしらの手助けやヒントとなれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。