この記事を読むのに必要な時間は約 55 分です。
「子どもが学校を怖がり教室に入れない状況が続いている…」
「子どもの気持ちを優先してあげた方がいい?今の状況を見守っていれば解決する?」
学校で何かストレスを感じることを抱えている時、学校に行くことが怖くなってしまうお子さんもいます。
お子さんの気持ちを受け入れず無理に行かせてしまうことは避けた方が良いですが、今の状況を見守っていると不登校が長引いてしまうため注意が必要です。
お子さんの気持ちを受け入れながら、「学校が怖い」と感じる根本原因の解決に向けて適切な対処をしていけば、お子さん自身が恐怖を乗り越えていけるようになります。
平均3週間で再登校に導くサービスを提供する小川涼太郎監修のもと、お話しする内容は次のとおりです。
記事を読むとわかること
・子どもが学校を怖がる理由
・子どもの怖い気持ちを和らげるために必要なこと
・学校が怖い子どもに対して親ができること
・学校が怖い子どもに対してしてはいけないこと
お子さんの抱える気持ちを解決していきたいときの参考にしていただけたら幸いです。
スダチでは、いじめや失恋、人間関係などがきっかけで学校に行くのが怖くなってしまい、不登校になったお子さんを再登校に導いてきました。
スダチの支援を受けていただいたお子さん方は、自己肯定感がどんどん育ち「怖い」と感じていた問題も、自ら乗り越えて再登校を果たしています。今では学校生活を楽しんでおられます。
「学校が怖い」「教室が怖い」という感情を抱え続けてしまうと、このまま不登校が長期化してしまうかもしれません。
一度スダチへご相談いただき、お子さんの抱えるつらい気持ちを根本解決していきませんか?
顔出しなしで参加できる無料オンライン相談も実施していますので、根本解決の方法や、再登校に向けたアプローチをお話しさせていただけたら幸いです。
1.「学校が怖い」と感じる学校恐怖症の子どもはたくさんいる
学校は、様々な人と関わりながら新しい物事を学ぶ場です。人は、知らないことや新しいことに対して「不安」な気持ちを抱える傾向にあります。
その知らないことや新しいことがうまくできなかったとき、不安な気持ちが大きくなり「学校が怖い」「教室に入るのが怖い」と感じてしまうこともあります。
特に、以下のお子さんは、学校で起きた問題がとても大きなものに思えてしまいより恐怖を感じてしまうかもしれません。
- 「うまくできないといけない」と考える真面目で完璧主義なお子さん
- 自己肯定感が低く「自分にはできない」という気持ちが大きいお子さん
- 人の気持ちの変化に敏感で相手の問題も自分の問題に感じてしまう繊細なお子さん
真面目であったり、周囲をよく見ることができたり、人の気持ちを汲み取ったりができるお子さんほど、不安や恐怖を抱えてしまう場合があり、そのようなお子さんは多くいらっしゃいます。
2.「学校が怖い」と感じる学校恐怖症をそのままにしていると不登校につながることも
お子さんが学校に恐怖を感じている場合、「子どもの気持ちを尊重して見守ってあげたい」と感じるかもしれません。
しかし見守っていると、お子さんの抱える不安がどんどん大きくなってしまい、不登校の長期化につながります。
学校では日頃から問題が起きるものですし、解決できず積み重なっていくことでさまざまな気持ちが絡み合い身動きが取れなくなってしまうものです。
「学校が怖い」と感じるお子さんの気持ちは否定せず、受け入れて認め、安心させてあげたうえで、根本原因の解決に向けて行動していくことが大切です。
3.学校に行くのが怖いと感じる6つの理由|「教室に入るのが怖い」と感じるのはなぜ?
お子さん自身もなぜ学校を怖いと感じているのかよくわかっていないことも多いです。
複数の要素が複雑に絡み合っていて、お子さんだけでは整理しきれないことがあるからです。
お子さんが学校に行くのが怖いと感じる主な理由6つをご紹介します。
3-1.いじめや友だち関係に原因があるケース
学校での友だち関係がうまくいっていないと、クラスの居心地が悪く学校に行くのが怖くなってしまいます。
- いじめられている
- クラス内にいじめがあり、教室の空気が怖いと感じている
- 周囲に馴染めず孤立してしまっている
こういった状況のとき、クラスメイトとの対人関係に恐怖を抱えている場合があります。また、うまくなじめない自分はダメな人間だと自己肯定感が下がり切っているケースも多いです。
世の中には、さまざまな人がいます。
そのため自分とは考え方が異なる人や波長の合わない場所は、どこにでもあるものです。中にはいじめをするような人もいるかもしれません。
考え方が合わない人がいたり、なじめない場所があったりしても、それは誰にでもあることのため、お子さんが悪いわけではなくお子さんはそのままで大丈夫であることを伝えてあげましょう。
また、仲良くできない場合でも「ただ合わないだけ」と捉えることが大切だと教えてあげてください。
上記を教えてあげて、お子さんが物事を俯瞰して考えられるようになったり、「今のままの自分で大丈夫なんだ」と思えるように促してあげましょう。
お子さんの考え方が変化し自己肯定感が育つと「怖い」と感じる気持ちがなくなり、苦手な環境でも自分らしく堂々と振る舞えるようになっていきます。
そのほかお子さんが友達を作り、クラスに馴染んでいくためにできる親御さんのサポートについては、次の記事でもお話ししています。
こちらもCHECK
-

-
学校・クラスに馴染めない高校生の子どもへ不登校になる前に親ができる対処法
この記事を読むのに必要な時間は約 36 分です。 「子どもが学校に馴染めない様子だ。どのように対処していけばいい?」 「このまま行き渋りがはじまったり高校を辞めたいと言いだしたりするのではないか?」 ...
続きを見る
3-2.先生との関係性に原因があるケース
先生と打ち解けられず苦手意識を持っているケースです。
- 上下関係がよくわからず先生とどう接したらいいか戸惑っている
- 注意を促された時に恐怖を感じてしまう
特に中学生以降になると、大人のマナーとして先生への接し方を注意されることが多くなります。友だちに対する時と同じやり方が通用せず、距離感の取り方がわからず不安を抱えるお子さんもいます。
また、ご家庭でダメなことはダメだと教えてもらう環境がなかったり、失敗する前に親が先回りしている状況だったりすると、学校で注意された時に萎縮してしまいやすいです。
上下関係や目上の人に対するマナーを教えてあげることも大切です。また、失敗することは決して悪いことではなく、大切な成長の機会だと教えてあげましょう。
お子さんが主体的に動いて失敗するような機会をたくさん作ってあげることも大切です。
3-3.勉強に苦手意識があるケース
勉強に苦手意識があり、わからないことが多いと、授業やテストが不安になってしまいます。
また、テストや成績は、結果が定量的な数値として出てしまうため、周囲と自分を比較しやすい状況です。それによりさらに不安が大きくなってしまうかもしれません。
家庭教師や塾なども利用を検討しながら学習をサポートしていくことが大切です。また、「いい成績をとることよりも、頑張って取り組んでいることが素晴らしいこと」と、お子さんの努力の過程に目を向けて褒めてあげましょう。
3-4.学校の仕組みや集団生活になじめないケース
そもそも学校の仕組み自体に疑問を抱き、そのルールに従わないといけないことに恐怖を持っているケースもあります。
特に小学校に上がりたてのお子さんの場合には、このケースが多いです。
集団行動が苦手で周囲から浮いてしまうことを過度に怖がるお子さんもいます。
学校のルールがなぜそうなっているのかを説明してあげると、納得して怖い気持ちが和らぐこともあります。
3-5.発達障害などが隠れているケース
学習障害や発達障害の傾向によって学校に馴染めないことを苦痛に感じていたり、学校で受けたストレスが原因で適応障害を起こしているケースです。
お子さんの特性に合わせた医学的なサポートが必要になることもあるため、医療機関にも相談しながら、お子さんにあった接し方を知ることも大切です。
発達障害の傾向が見られるお子さんは、周囲にうまくなじめない自分を責めてしまっていることもあります。
そのため、お子さんの得意なことに目を向けてたくさん褒めてあげたりして、自己肯定感を育てることが大切です。
スダチでも、発達障害の傾向が見られ不登校だったお子さんが、再登校を果たした事例をたくさん見てきました。
詳細については、次の記事も参考にしていただけると幸いです。
こちらもCHECK
-

-
ADHDの子どもは不登校になりやすい?発達障害の子どもが学校へ行きたくないと思う理由と再登校へ導く方法
この記事を読むのに必要な時間は約 34 分です。 「ADHDの子どもが不登校になってしまった」 「うちの子がADHDと診断されてしまって、学校生活が不安」 不登校のお子さんを持つ親御さん ...
続きを見る
こちらもCHECK
-

-
【子どもが朝起きられない】中学生・高校生の子どもが朝起きない原因|起立性調節障害・発達障害との関係【不登校になる前に親ができる対処法】
この記事を読むのに必要な時間は約 52 分です。 「中学生・高校生の子どもを、朝起こしても全然起きない…」 「朝起きない中学生・高校生の子どもが、不登校気味になってきた…」 ...
続きを見る
こちらもCHECK
-
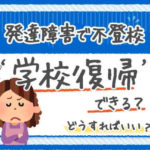
-
【発達障害と不登校】「ふつう」ができない【理解とサポートがカギ】
この記事を読むのに必要な時間は約 52 分です。 子どもの不登校について調べていると「発達障害かも」と書かれていることもあり、気がかりですよね。 この記事は、次のお悩み・疑問を持っている ...
続きを見る
3-6.親子関係が原因になっているケース
お子さんに対して過干渉、過保護であったり、お子さんが親御さんの顔色を伺っているような状況だったり、親子関係が原因になっていることもあります。
過干渉でなんでもお子さんのことを聞き出してあれこれ口を出すと、お子さんは「失敗したらダメなんだ」と失敗を極度に怖がるようになってしまいます。
また、過保護でいつも親御さんが先回りしているケースだと、お子さんは自分で考えて行動してきた経験がありません。
親御さんがいない学校で、自分の言行に自信を持てず大きな不安を抱えてしまう場合があります。
他にも、親御さんがお子さんを感情的に叱ってしまうと、お子さんはいつも親御さんの顔色を伺うようになります。親の言うことが正解で、自分の行動はダメなんだという気持ちになってしまい、自分に自信を持つことができません。
親としてはお子さんを心配してなんでもしてあげたくなったり、お子さんが大切で将来を心配するからこそ時に感情的に怒ってしまったりするかもしれません。
お子さんの自己肯定感を育てて社会の中で主体的に生活していくためには、適切な距離感を保った正しい親子関係が必要です。
- 感情的にならずに子どもの意見や考え方は否定せず受け入れて認めてあげる
- そのうえでダメなことはダメだと毅然とした態度で教えてあげる
- いつも子どもの行動に目を向けて正しいことはたくさん褒めてあげる
上記を意識して、正しい親子関係を構築しましょう。
4.学校が怖いと感じる気持ちを和らげる対処法
4-1.学校へ行くのが怖いという感情を紐解いてみる
お子さんが怖いと感じている理由を1つずつ紐解いてみましょう。
- わからない:授業がわからない、どうやってクラスメイトと話せばいいかわからない
- 嫌だ:勉強したくない、〇〇ちゃんが嫌い、集団で過ごすのが嫌、悪口を言われるのが嫌
- ひとりぼっちで寂しい:誰も理解してくれない、誰も頼れない
などの感情が隠れていることが多いです。
されたくないことをされてしまったり、わからないことに向き合わなければいけなかったりして、どんどんと負の感情が溜まっていくと苦手意識が強くなり恐怖を感じるのです。
何か特定のことが怖いというより、様々なことに対する負の感情が積み重なって、恐怖に変わってしまうのです。
例えば、
- 授業内容を理解できずつらい思いをする
- 先生に授業中に指されるのが嫌になる
- 友だちに馬鹿にされたくないと悔しい思いをする
- 授業が苦痛になって勉強する意味がわからなくなる
このように負の感情が溜まっていくと、学校に行ってもつらいだけになり学校が怖くなってしまいます。
まずはその流れを知っておくだけでも、お子さんに寄り添って話せるようになります。
4-2.一人で抱え込まないように促す
お子さんが一人で抱え込まないように、話を聞いてあげることを心がけましょう。
お子さん自身も学校が怖い理由がよくわかっておらず、どうしたらいいか戸惑っていることが多いからです。
「今日は学校どうだった?」など何気ない会話から、お子さんが学校に対してどんな気持ちを抱いているのか引き出してあげましょう。
親御さんと話しているうちに「〇〇が嫌だ」など、恐怖の裏に隠れている気持ちが出てきます。
気持ちを話してくれたら
- 「〇〇が嫌だったんだね」
- 「今話してくれたような気持ちでいっぱいになって怖かったんだね」
と気持ちを代弁してあげると、お子さんが自分の気持ちを自覚できるようになります。
なぜ怖いのかを理解できたり、自分の気持ちを理解して受け入れてくれる親がいるとわかるとお子さんは安心し、乗り越えるための気持ちの土台ができあがります。
お子さんが前進するきっかけをつくるために、怖い気持ちを紐解くサポートをしてあげてください。
4-3.学校以外の安心できる居場所をつくる
学校を怖いと感じているお子さんは、リラックスできず疲れやすい状態です。
ご家庭が、お子さんが安心して過ごせる場所となるよう、正しい親子関係の構築は欠かせません。
また、お子さんが自らの意思で前向きに取り組むようであれば、興味のある習い事などをはじめてみて、安心して集団生活を過ごせる居場所を作ってあげましょう。
ただし無理に学校以外の居場所をつくる必要はありません。「学校へ行ってないのだから、せめて塾や習い事だけは通ってほしい」という気持ちからお子さんへ押し付けないように気をつけましょう。
親御さんが押し付けてしまっているご状況のとき、お子さんは「親の望む習い事や塾へ通っているのだから、やるべきことはやっている」という錯覚を起こしてしまいます。
本来目指すべき学校への再登校という目的を見失ってしまう場合があります。
また、無理矢理通わせている場合「親が行けと言うから行っている」と、お子さんの他責思考にもつながりやすいです。現状の不登校や学校で発生した問題も、他人のせいにしてしまいやすくなります。
お子さんが、主体的に再登校したり、これからも学校での問題を主体的に解決したりして、社会の中で自立していくためには、他人のせいにする考え方を消していかなくてはなりません。
自分の責任で自分で物事を選択し進んでいく力を身につけていく必要があります。
また、習い事へ行ったり休んだりを繰り返してしまうケースも多いため、親がなんとか行かせて、行かないものへお金を払っている状態になってしまいます。
この状態は、良い親子関係を築く際の妨げになる場合もあります。
上記を踏まえて、無理に学校以外の居場所をつくる必要はありません。お子さん自らの意思で通いたいという場合には、検討してあげましょう。
「社会の中に自分の居場所がある」と感じられると、「学校だけが全てではない」と捉えられるようになっていきます。
また、自らの意思で取り組んだことが伸びていくと、自己肯定感も育まれていくものです。
自己肯定感が高まると「学校生活も意外と大丈夫かもしれない」という気持ちが生まれ、前進するきっかけとなります。
5.学校が怖いと感じる子どもへのNGな対処法
5-1.学校に行くことを強制する
「このまま不登校になってしまうのではないか」とお子さんを心配する気持ちから、無理矢理にでも学校へ連れていってしまうことがあるかもしれません。
しかし、「学校が怖い」と感じているお子さんに対して学校へいくことを強要してしまうと、「こんなにつらい思いをしているのに、親は自分の気持ちをわかってくれない」と親子関係に亀裂が入ってしまいます。
「恐怖を感じるほどつらい気持ちを抱えていたのに学校へ通っていたのはすごいことだよ」とお子さんの気持ちを受け入れて、いままで頑張っていたことを褒めてあげましょう。
そのうえで「問題を解決できるようにサポートするからね」とまずはお子さんの気持ちに寄り添うことが大切です。
5-2.怖い理由を問い詰める
「なぜ怖いと感じるの?」と問い詰めるようなことは避けましょう。
お子さん自身、なぜ怖いと感じるのか、どうして教室に入るのが怖いのか理由がよくわかっていないこともあります。
学校になにかうまく行かないことやストレスを感じることがあり、結果として怖いという感情に結びついているのでそのことに気づけるよう声かけしていくのがおすすめです。
また、
- 苦手な物事、うまく行かない物事は誰にでもあり、何かできないことがあっても決して悪いわけでない
- 何か苦手なことやできないことがあっても、親御さんにとってお子さんが大切な存在であること
これら2つを伝えてあげて、学校を怖がっていることについてお子さんが自分を責めないようにしてあげることが大切です。
5-3.見守ってしまう
学校を怖いと思っている子どもをそのままにしておくと、不登校やひきこもりになる可能性が高いです。
お子さんの気持ちを尊重するために見守りが推奨されることがありますが、問題を根本解決しないままだと、お子さんは不安や恐怖を抱え続けることになってしまいます。
不登校やひきこもりの長期化につながってしまうため、スダチでは見守りはおすすめしておりません。
また見守りを重視して、フリースクールなどお子さんが無理なく所属できる環境を選んだとしても、フリースクールなどはこの先社会に出てからの生活と大きく仕様が異なるのが現実です。
大学へ進学したり、就職したりした際、今までの生活と大きなギャップがあり、再び不安や恐怖を抱えてしまうことにつながります。
そのため、お子さんが将来幸せな社会生活を送るためには、見守りではなく根本解決に向けたアプローチの実施が必要です。
5-4.親が今後の行動を決めてしまう
お子さんがこれからどうしていくか決められない時でも、親御さんが今後のことを決めてしまうことは避けましょう。
学校が怖いと感じてしまう根本的な原因には、お子さんの自己肯定感の低さがあります。
自己肯定感が低いと自分の言行に自信を持てず、学校での問題を解決していく力がないため恐怖を感じてしまいます。
- 学校が怖いなら転校した方がいい
- もう学校へ行かなくてもいい
など今後のことを決めてしまうと、一旦は進んだように見えても、問題が根本的に解決していない状態です。
再び新しい環境で問題が発生したとき、解決するための行動ができず恐怖を感じてしまいます。
また、自分で物事を選択してきた経験がないと、自分の気持ちや行動に自信を持つことができず、一向に自己肯定感が育ちません。
選択に失敗をしてもそこから学んでいけば、ほとんどの場合は大丈夫です。そういった経験がお子さんの自信に変わっていきます。
まずはお子さん自身が決めて行動するようにしてあげることが大切です。
6.学校が怖い子どもに対して親ができること
6-1.スダチなどの専門機関へ相談をする
お子さんが怖い気持ちを乗り越えるために、どうしたらいいのかについてはスダチなどの専門機関の力も借りていきましょう。
現代の日本では子育てについて学ぶ機会がなかなかないので、「親である私が子どもを守ってあげないと」と考えがちですが、決してそんなことはありません。
わからないことは専門機関にアドバイスを求め、正しい対処法を知っていくことが大切です。
正しい対処法や再登校までの道標を知ることで、親御さん自信も不安を解消しながら前へ進めます。お子さんをポジティブに明るい気持ちでサポートできることにもつながるでしょう。
スダチではお子さんの現状をヒアリングした上で、お子さんの自己肯定感を育てるために必要な親御さんの働きかけをアドバイスしています。
親御さん自身がお子さんをサポートする形なので、信頼関係を築けて新しい問題が起きても親子二人三脚で乗り越えていけるようになるのが特徴です。
「学校が怖い」と訴え行き渋りが続いているときには、一度スダチへ現状の不安を相談してみませんか?1対1で顔出し不要の無料オンライン相談も実施中です。
6-2.怖い気持ちを受け入れてあげる
お子さんが学校を怖いと感じる気持ちは、否定せずに受け入れてあげましょう。
「みんなは通えているんだし怖いところじゃないよ」など他人と比較して怖いところではないと伝えることも避けた方がよいでしょう。
人それぞれ性格や生き方は異なるため、不安や恐怖を感じる事柄も異なります。どのようなときでも親御さんはお子さんの気持ちを受け入れて味方でいてあげてください。
お子さんが感じている怖い気持ちを受け入れて認めてくれる親がいるとわかると、恐怖が和らいでこれからどうしていくか真剣に考えられるようになります。
6-3.頑張っていることを見つけてわかりやすく褒めてあげる
お子さんが頑張っていることに目を向けて、どんなに小さなことでも言葉にして褒めてあげてください。
むしろ親御さんが些細なことにも目を向けていることを伝えると、お子さんは「親はいつも自分を見ていてくれる」と安心します。
日頃から親御さんに肯定的な声かけをしてもらうことでお子さんは安心し、恐怖を乗り越えやすくなります。
また、認めてもらえた安心感から自己肯定感が育つと、学校で否定的な感情になってしまいそうな場面でも自分の気持ちを立て直していけます。
お子さんが「自分にはこの親がついているから大丈夫だ」と感じられる状態を目指していきましょう。
お子さんの目を見て、時にはスキンシップも交えながら伝えてあげるとより伝わりやすくなります。
6-4.正しい親子関係を築く
間違ったことは毅然とした態度で教えることで、お子さんを甘やかすことなく褒め言葉を伝えられるようになります。
間違いを教えてもらえるとお子さんは何が正しいのかがわかり、学校でも親御さんに教わったことに自信を持って振る舞えます。
自分のために正しいことを教えてくれる親御さんを信頼するようになり、信頼する親御さんから褒めてもらえることでさらに自己肯定感が育っていきます。
自己肯定感は学校生活はもちろん、これから社会に出た時もお子さんを支えてくれるでしょう。
怖いと感じるような場面に直面しても、怯まずに挑戦していけるようになります。
7.学校がどうしても怖いときの学校以外の選択肢
自己肯定感を育てて根本原因を解決しても、どうしても恐怖を乗り越えられないケースもあります。
例えばひどいいじめに遭っていた場合には、加害者を見た時や学校へ行ったときに恐怖が蘇ってしまうことがあるかもしれません。
もしもお子さんがそのような状況の時に考えられる選択肢を紹介いたします。
7-1.学校が怖いと感じる小学生・中学生への選択肢
7-1-1.フリースクール
フリースクールは、いじめなどによって学校に通うのが難しくなったお子さんを受け入れている施設です。
不登校のお子さんの心理を熟知しているスタッフがいるため、学校に強い恐怖を持っているお子さんも過ごしやすいでしょう。
校長先生の許可を得れば、学校に行かずフリースクールに通っている時でも出席日数としてカウントしてもらうことも可能です。
また、義務教育である小中学校では、出席日数に関わらず卒業できますので、進路については高卒資格の取得方法を検討しておけば十分です。
ただし中には好きな時に行って好きなことをして過ごせるフリースクールもあります。
そのような生活に慣れてしまうと一般的な学校へ通う際、仕様が大きく異なることからお子さんがギャップを感じる場合もある点に注意が必要です。
小中学生が通えるフリースクールについて知りたい方は、次の記事も参考にしてみてください。
こちらもCHECK
-

-
フリースクールとは?授業内容、かかる費用と不登校の相談先や解決方法
この記事を読むのに必要な時間は約 66 分です。 「子どもが不登校になってしまった…フリースクールに通わせるべき?」 「フリースクールはどんな学校?不登校解決につながるの?」 お子さんが ...
続きを見る
こちらもCHECK
-

-
不登校の小学生はフリースクールに通った方がいい?【不登校は解決する?かかる費用や授業内容】
この記事を読むのに必要な時間は約 40 分です。 「小学生の子どもが不登校になってしまった…学校以外の選択肢を考えたほうが良い?」 「フリースクールに通えば、子どもの不登校は解決する?」 ...
続きを見る
こちらもCHECK
-

-
不登校の中学生が通えるフリースクールとは|高校受験を目指せる?授業内容や費用、不登校の解決方法
この記事を読むのに必要な時間は約 39 分です。 「中学生の子どもが不登校になってしまった…フリースクールに通った方がいい?」 「フリースクールに通えば、このまま子どもは高校受験を目指すことができる? ...
続きを見る
7-1-2.適応指導教室
適応指導教室は不登校になっているお子さんを対象に、カウンセリングや学習支援を行う機関です。
教育委員会が設置している公的機関で、地域によっては教育支援センターと呼ばれることもあります。
1日のカリキュラムがしっかり決められていることも多く、学校に近い過ごし方をします。
再登校を促すというよりも居場所を提供する側面が強いことは覚えておきましょう。
7-1-3.学習塾・家庭教師
お子さんが勉強自体は好きな場合や、今後の進路のために学力の維持をしておきたい場合には、学習塾や家庭教師の利用もおすすめです。
不登校のお子さんを対象としたサービスもあり、一からの学び直しやメンタルケアに対応してくれるものも多いです。
サービスの選び方や利用がおすすめなケースについては、次の記事でお話ししています。
こちらもCHECK
-

-
不登校の子どもに塾は必要?利用するメリットデメリット|不登校の根本解決に向けて親御さんができることを紹介
この記事を読むのに必要な時間は約 36 分です。 「子どもが不登校になってしまった…学力を補えるような学習塾に通ったほうがいい?」 「塾に通って学力がつけば、不登校の解決にもつながる?」 ...
続きを見る
こちらもCHECK
-
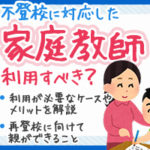
-
不登校に対応した家庭教師の利用はおすすめ?|家庭教師の選び方や不登校の根本解決方法
この記事を読むのに必要な時間は約 27 分です。 「子どもが不登校のとき、不登校に対応した家庭教師を利用した方がいい?」 「家庭教師の選び方や、不登校解決につながるのかを知りたい」 お子 ...
続きを見る
7-2.学校が怖いと感じる高校生への選択肢
7-2-1.通信制高校
通信制高校は年に数日の登校とオンライン授業を行う学校で、高卒資格の取得もできます。
登校日が少ないため、友だち関係に苦手意識がある場合に選ばれやすい選択肢です。
ただ、オンライン授業がメインのコースを選ぶと、外出する機会が少なくなるため、ひきこもってしまわないようにすることが大切です。
通信制高校のカリキュラムや卒業後の進路などについては、次の記事でお話ししています。
こちらもCHECK
-
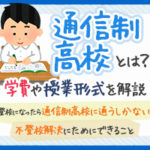
-
通信制高校とは?入学の条件、学費、単位取得の仕組みや卒業後の進路、不登校の解消に役立つのかも紹介
この記事を読むのに必要な時間は約 52 分です。 「子どもが不登校になってしまった…この先の進路として通信制高校を選択肢にいれた方が良い?」 「通信制高校はどんなところ?学費や入学条件、卒業後の進路は ...
続きを見る
7-2-2.定時制高校
定時制高校は夕方頃から授業を受けるタイプの学校です。1日の授業数が少ないため、4年ほど在籍するお子さんもいます。
朝起きることや長い時間集中するのが苦手なお子さんに向いているでしょう。
ただ、朝起きられない原因には起立性調節障害などが隠れていることもあります。詳しくは次の記事も参考にしてみてください。
こちらもCHECK
-

-
【子どもが朝起きられない】中学生・高校生の子どもが朝起きない原因|起立性調節障害・発達障害との関係【不登校になる前に親ができる対処法】
この記事を読むのに必要な時間は約 52 分です。 「中学生・高校生の子どもを、朝起こしても全然起きない…」 「朝起きない中学生・高校生の子どもが、不登校気味になってきた…」 ...
続きを見る
7-2-3.他の高校
今お子さんが通っている高校とは別の全日制高校に通う方法です。
学校により異なりますが、主に次の条件を満たすことで転校や転入ができます。
- 転校先の高校に空きがあること
- 学力試験に合格すること
- 現状で高校に在籍していること
学校に通えるところに住んでいること
全日制高校への転校を検討される場合には、次の記事も参考にしていただけると幸いです。
こちらもCHECK
-

-
不登校でも全日制高校に進学・転校もできる!全日制高校に入るポイント
この記事を読むのに必要な時間は約 43 分です。 「不登校でも全日制高校に進学・転校できる?」 「不登校の子どもの転校先や進学先の選択肢を知りたい」 お子さんが不登校になり、出席日数が足りなくなってく ...
続きを見る
7-2-4.通信制サポート校
通信制サポート校は高校生が通えるフリースクールの一種で、学習支援をメインに扱っている学校です。
通信制サポート校だけでは高卒資格の取得ができないため、通信制高校と併用するのが一般的です。
通信制高校の授業についていくのが難しい場合などに利用されています。
また、大学受験や就職試験などのサポートも実施してくれるケースもあり、お子さんの進路の幅を広げるのにも役立ちます。詳しくは次の記事をご覧ください。
こちらもCHECK
-

-
高校生がフリースクールに通うメリットとデメリット【高卒資格は取得できる?おすすめスクール6選】
この記事を読むのに必要な時間は約 59 分です。 「高校生の子どもが不登校になってしまった…フリースクールに通った方がいい?」 「フリースクールに通えば、高卒資格を取得できる?」 高校生 ...
続きを見る
7-2-5.就職する
中卒の学歴のまま就職してしまうのも一つの方法です。
就職試験で不利になる側面もあるものの、夢中になれるものややりたい仕事にすぐ取り組めるのは大きな魅力でしょう。
ただお子さんが「勉強が嫌いだから働きたい」と言っている時には注意が必要です。
業務をスムーズにこなすためには勉強が必要であることも伝えてあげて、本当に就職する道で良いのか親子で話し合うようにしましょう。
7-2-6.高卒認定の取得と大学受験を目指す
お子さんが主体的に自宅学習できる場合には、学校には通わずに高卒認定資格を取得して大学受験を目指すことも可能です。
なかなか成績が伸びなくても「実は集団授業が苦手なだけで自宅学習なら集中できた」というお子さんもいます。
また、もし自宅学習が苦手なお子さんでも次のルールを守ると、集中できるケースもあるので参考にしてみてください。
- 勉強する部屋にはスマホやゲームを持ち込まない
- 朝起きて日光を浴びたら集中力が高いうちにすぐに勉強に取り掛かる
- ジョギングや筋トレなど強度の高い運動で頭をリセットする
- 50分集中して10分休憩など学校の授業のように適度に休憩を取り入れる
- 勉強中は何も食べず飲み物も水かお茶にする
8.「学校が怖い、教室が怖い」と言っていたお子さんが再登校を果たした体験談
同級生から酷いいじめを受けたことで学校が怖いと感じてしまい、不登校になっていた中学2年生の事例をご紹介します。
もともとADHDや学習障害を抱えており、苦手なことに集中できなかったり、授業についていけなかったりして苦しんでいる状態でした。
その状況の中、同級生から酷いいじめを受けて学校への恐怖心が強くなり、不登校になってしまっていました。
スダチが支援に入る前にも、他の支援機関を利用していましたが、再登校には至っていませんでした。
7ヶ月ほど不登校が続いていた時にスダチの支援を開始。最初は反発して荒れることもありましたが、自己肯定感が育っていくにつれて落ち着いていきました。
最終的には35日ほどの支援で再登校に成功し、「学校が楽しい」と喜んで学校に通えるようになったそうです。
この事例をはじめとして、スダチでは親御さん直筆アンケート等も掲載していますので、気になる方は次のページもチェックしてみてください。
9.学校が怖い子どもについてよくある質問
9-1.学校恐怖症とはなんですか?克服する方法はありますか?
学校恐怖症とは、学校が怖いと思う病気のことで、国際的にも認められている症状です。
お子さんは学校が怖くどうしたらいいのかわからない状態で、本人の努力では解決が難しいことが多いため、親や家族のサポートが欠かせません。
頑張りを褒めてあげたり間違いを毅然とした態度で教えてあげたりして、お子さんの自己肯定感を育ててあげることで解決できることもあります。
9-2.登校拒否と不登校はどう違うのですか?
登校拒否と不登校の違いは以下の通りです。
- 登校拒否:学校へ行くことをなんらかの理由で拒否していること
- 不登校:30日以上学校へ通っていないこと
登校拒否も不登校も学校に通えていない点では同じですが、日数に違いがあります。
登校拒否が30日以上続くと不登校と呼ばれます。
9-3.子どもが人が怖いと感じているようです…どうすればいいですか?
まずはご家庭で落ち着ける環境を整えてあげることが大切です。
正しい親子関係を築き、お子さんの自己肯定感を育てていくとお子さんにとってご家庭が落ち着ける場所になります。
ご家庭で安心して過ごし、気持ちが落ち着いてきたら怖いと感じる気持ちに向き合って、原因は何なのかを探っていきましょう。
どうしても学校が怖いという気持ちが強い場合には、認知行動療法など医学の力も借りることや学校以外の選択肢も検討してみてください。
9-4.子どもが教室に入れない‥どうしたらいいでしょうか?
まずは無理に教室へ入れようとせず、教室に入れないことを認めてあげて、教室に入れずつらい思いをしているお子さんの気持ちに寄り添ってあげることが大切です。
その上で、
- 頑張りを褒めてあげる
- 間違いを毅然とした態度で教えてあげる
この2点を行うことで自己肯定感を高めていくと、自然と子どもから前進し始めるので安心してください。
また、親御さんが「また楽しく学校に通ってほしい」と思っていると伝えることで、お子さんは「親は自分に期待してくれているんだ」と希望を持てます。
ただ、強制されるとお子さんが反発してしまうため、親御さんの気持ちを伝えつつ、最終的にどうするのかはお子さんに選んでもらうようにしましょう。
10.まとめ
一度学校が怖いと感じると学校生活を楽しめなくなり、徐々にストレスが溜まっていきます。
最初は登校できていたお子さんも不登校になってしまうリスクがあるため、なるべく早めに怖い気持ちを解消してあげることが大切です。
学校を怖いと感じるきっかけはいじめや失恋など、お子さんによってさまざまです。
ただ、その原因を辿っていくとお子さんの自己肯定感の低さが根底にあることもあります。
自己肯定感が低いと、自分で考えて行動するのが苦手で学校で起きる問題を解決できず、それが恐怖の原因になります。
お子さんの自己肯定感は決して生まれつきのものではなく、親御さんの働きかけによって育てていけるので安心してください。
スダチは親御さんの働きかけを少し変えるだけで、お子さんの行動がガラッと変わった事例をたくさん見てきました。
「学校が怖い」と感じる根本原因を解決していきたい場合は、無料オンライン相談にて一度お話しできたら幸いです。






