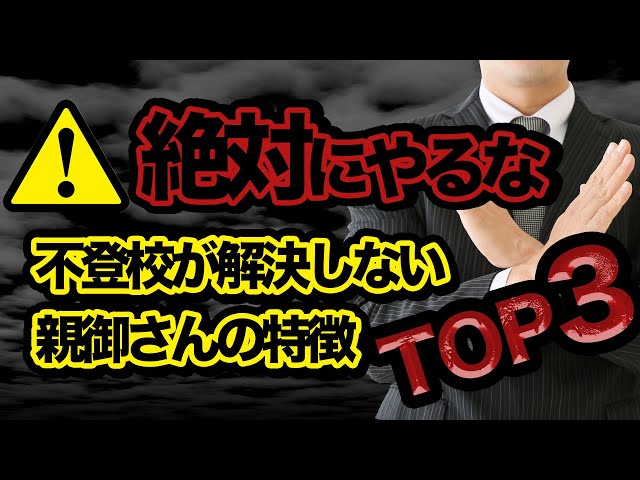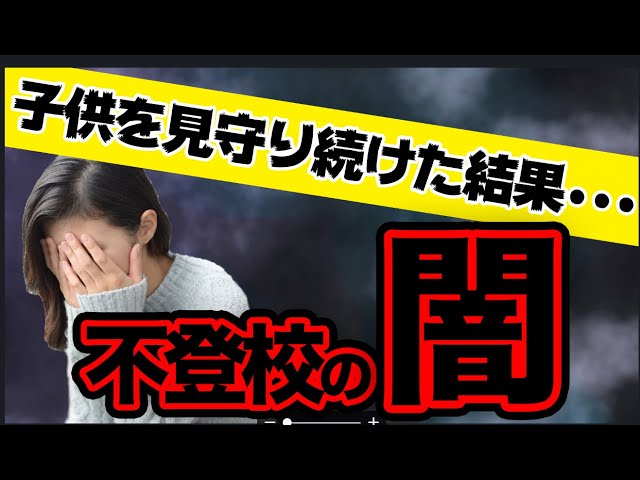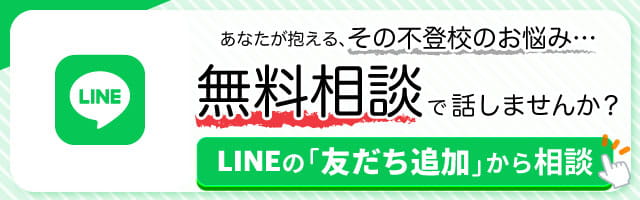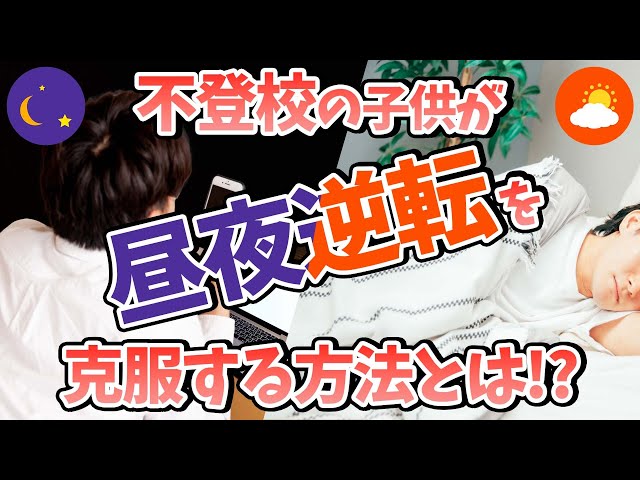この記事を読むのに必要な時間は約 36 分です。
お悩みポイント
- 子どもの不登校を解決したくて、できることを探している
- 何かサポートしてあげたいけど、サポートって一体何をすればいいの?
- 私だけで子どもを支えきれるかどうか…
子どもが不登校になると、親御さんの誰もが「不登校を解決したい」と思うもの。
ところが、いざ解決しようとなると、「何をしたらいいのか、わからない」「サポートで不登校が解決するのか不安」と、戸惑いますよね。
突然ですが、執筆者の私も、あなたのお子さんと同じ不登校でした。
この記事は、【3週間で不登校解決プログラム】を展開している小川 涼太郎(おがわ りょうたろう)さん監修のもと、不登校の子どもに必要なサポートを紹介します。
具体的な内容は次のとおりです。
記事を読むとわかること
- 不登校の子どもに対して、親は何をすればいいのか
- もっとも効果的なことは何か
- 小中高の教育課程、勉強や体調に生活の視点から見たサポート
記事を読み終えるころ、あなたは子どもにとってよき理解者であり、不登校解決のサポーターに近づいています。
お子さんに何ができるのか、イメージしながら読んでくださいね。
1. 不登校のサポートは親と子それぞれに必要!
親御さんができることは、大きく分けて次の2つです。
- 親御さんもサポートを受ける
- 子どもを取り巻く環境を整える
親御さんが1人で不登校のお子さんをサポートしていては、いずれ親御さんのメンタルが耐えきれなくなります。
そのため、まずは親御さんがサポートを受けることがポイントです。
1-1. 親御さんもサポートを受ける必要があるワケ
「不登校の子どもをサポートする“あなた”を、支えてくれる人はいますか?」
あなたは間違い無く、「子どもが不登校という現状を変えたい」の思いでこの記事を読んでいることでしょう。
きっと、今までにも色々と調べて試してきたはずです。
では、調べて試してきた結果は、どうでしたか?
この、見えない辛さは、ずっと続きます。
あなたが、たった1人で子どもの不登校を解決しようとしている限り。
まずは、あなたから相談という行動を起こして、サポートを受けてみてください。
悩みを理解し支えてくれるサポーターがいることがわかったら、今度はあなたの番です。
子どもが不登校から抜け出せるよう、あなたがサポーターになるのです。
1-2. 環境を整えてあげるとは?
サポートを受け始めたあながたすることは、子どもを取り巻く環境を整えること。
とくに、大事なのは家庭環境です。
「不登校は学校のことなのに、どうして家が関係するの?」
疑問の答えは、次の2つにまとめられます。
- 家庭環境が整わない限り「身も心も休まらない」
- 子どもを取り巻く環境は「心の機能の発達」を左右する
1-2-1. 家庭環境が整わない限り「身も心も休まらない」
不登校の子どもの多くは、心に強いストレスを抱えています。
このストレスは、他者から受けた言動から生じているとは限りません。
「ちゃんと学校に行かないといけないのに…」と、自分で学校に行けない自分を責めることもまた、心を傷つけます。
身も心も休めるためには、まず子ども自身が「不登校の自分」を受け入れないといけません。
そして、子どもが現実と向き合うには、次のようなサポーターが必要です。
- “ちゃんとできていない”自分だとしても、受け入れてくれる
- 今の“あるがままを受け入れてくれる”
不登校であるという現実を責めても、未来は変わりません。
まず、あなたが「今は不登校だけど、きっと克服できる」「不登校の経験はバネにできる」と、不登校の見方を変えてみてください。
現実を受け入れられる家庭環境が整えば、子ども自身による自責の念はやわらぎ、前に進むゆとりが生まれます。
1-2-2. 子どもを取り巻く環境は「心の機能の発達」を左右する
家庭環境を整えることはストレスからの回復を早めるほか、心の機能の発達にも関係します。
心の機能とは、物事の感じ方や捉え方など指します。
心の機能がそれぞれプラス・マイナスに育ったケースの例は次のとおり。
心の機能がプラス
- ネガティブな経験からも学び、前に進むためのパワーに変える
- 小さなことをコツコツと粘り強く続ける
- 逆境のなかでも「乗り越えられる」と希望を持てる
心の機能がマイナス
- ネガティブな経験を掘り起こしては、言い訳に利用する
- コツコツ頑張れないため、一発逆転を狙う
- 辛いことがあると「ずっと続く」と思っている
心の機能がプラス・マイナスのとき、不登校はどう捉えられるでしょうか?
子どもが不登校になると、親御さんも心の機能がマイナスになりがちです。
ネガティブな感情になるのは決して悪いことではありません。
大事なのは、ネガティブな感情に飲み込まれたまま引きずらないこと。
ネガティブな感情は伝染しやすいため、あなたが子どもの不登校に対して落ち込んだままだと、子どもも同じ状態に陥ります。
考えてみてください。
子どもを支えるはずのサポーターが悲観的で、子どもを不登校から抜け出せられますか?
※YouTubeサイトへ移動します
不安もあるかと思いますが、不安の感情はそのままに、次のように想像してみてください。
- 「この子の不登校経験から、何かわかることは?」
- 「一緒に不登校を乗り越えるには?」
あなたが少しでも前向きになると、子どもも前を向けるようになりますよ。
2. 不登校のサポートのキーポイントは【子育て】
子どもを取り巻く環境、家庭環境を整えることが不登校の解決には欠かせません。
とくに、家庭環境のなかでも注目すべきポイントは、親子関係です。
親子の結びつきが健全かつ強いほど、子どもは安心感を得られるため、不登校という逆境をスムーズに乗り越えられます。
今ある親子関係を健全かつ強いものにするため、カギとなるのが子育てです。
これまでの子育てを見直してアプッデートすると、子どもとの結びつきが健全で強固なものになります。
子どものサポーターである、あなたに注目してほしい子育てのポイントは、次の3つです。
- これまでの親子関係のあり方を見直す
- 子どもへの効果的な接し方を学ぶ
- 日々の生活の中で育て直しを実践する
2-1. これまでの親子関係のあり方を見直す
親子関係のあり方を見直すとは、これまでの子育てをふり返ること。
このような機会だからこそ、子育てをふり返ることで、次の2つをチェックできます。
- 家庭環境が子どもにとって本当に安心できる場所か?
- 親子の結びつきは健全で強いものか?
例えば、次の方針で子育てをしており、子どもが不登校になったらどうでしょう?
- 子育ての方針:人生における苦難は自力で乗り越えてほしい
子どもが不登校なり、心配はするものの、方針によりサポートは無いに等しいでしょう。
「成長すれば、時間が経てばそのうち…」と、「待つ」ことも考えられます。
※YouTubeサイトへ移動します
さて、子どもの力のみで不登校を乗り越えるのは、可能でしょうか?
たしかに、自分の力で困難を乗り越えることは大切です。
ただ、子どもの成長、言い換えれば時間の経過・なりゆきに期待しすぎると、子どもはSOSの出し方を知らないまま大人になる恐れもあります。
本来、困ったとき、助けてほしいときに助けを求めるのは、恥ずかしいことではないはず。
あなたのお子さん・今の親子関係は、「助けて」が言えますか?
改めて子育てをふり返ると、後悔する点が出てきたかもしれません。
ひととおり反省したら、前進しましょう。
\ 親子関係をセミナーで学びませんか? /
2-2. 子どもへの効果的な接し方を学ぶ
親子関係のあり方を見直したら、子どもへの接し方をアップデートしましょう。
子どものサポーターであるあなたに、今日から意識してほしいポイントは2つです。
- 無条件の愛で接すること
- 甘い対応はしないこと
2-2-1. 無条件の愛で接すること
無条件の愛と言われても、パッと想像できませんよね。
先に、無条件の愛とは反対の、条件付きの愛を確認しましょう。
- いい大学に行ってほしいから、塾に通わせる
- テストでほめるのは、点数
- 「〇〇ができないなんて、ありえない!」
条件付きの愛は、親の誰もがやりがちな接し方です。
条件付きの愛を受け続けた子どもは、一体どうなるのでしょう?
「◯◯しないと認めてもらえない」「◯◯ができない自分には、価値がない」と、自分に刷り込みます。
不登校に対しても同じです。
あなたが「不登校なんて…」と思っていると、子どもは自分を「学校に行けないダメな人間」と思い込みます。
あなたが不登校の子どものサポーターとしてできることは、子どもに無条件の愛情を持つことです。
“あるがままの子どもを受け入れて信じること”が、今後を変えるきっかけにも繋がっていきます。
2-2-2. 甘い対応はしないこと
無条件の愛と甘い対応は別物です。
子どもとの接し方で、次の点がおざなりになっていませんか?
- お互いにあいさつをせず、口を聞かない
- 生活習慣が乱れているが、本人の責任だから放っておいている
- 子どもからの「〇〇を買ってくれたら学校に行く」を信じて買い与えている
残念ながらこれらは、子どもに対して甘い対応。
なぜなら、人としての礼儀や習慣を野放しにしており、子どもからいいように扱われているためです。
「親」とは子どもを無条件で愛しながらも、社会生活のイロハを教える存在です。
きょうだいや友だちとは別の立ち位置からのコミュニケーションが求められます。
親として、締めるべきところはビシッと締めましょう。
こちらもCHECK
-

-
学校に行きたくない!子どもの不登校は「甘え」ではなく「甘え」である。でも「甘やかしすぎ」はNG
この記事を読むのに必要な時間は約 32 分です。 ポイント 不登校は甘えが理由なの? 親のしつけが悪かったのだろうか? 甘やかしはいけないから無理矢理学校へ行かせた方がいいの? &nbs ...
続きを見る
2-3. 日々の生活の中で育て直しを実践する
子どもへの効果的な接し方のポイントは次の2つでした。
ポイント
- 無条件の愛で接すること
- 甘い対応はしないこと
実は、2つのポイントは知っただけでは何の効果もありません。
効果がほしいなら実践が必要です。
上手くいかないときもありますが、それでもトライアンドエラーを繰り返してください。
例えば、朝のあいさつがないなら、朝の声かけからトライしてみませんか?
ドア越しから「おはよう」のひと言をかければクリアです。
1日ごとの小さな積み重ねや毎日の繰り返しは、いずれ習慣になります。
親子関係や家庭環境の築き直しにも繋がり、今後を大きく変える可能性を秘めているのです。
こちらもCHECK
-

-
【3週間で不登校解決】子どもから「学校に行くよ」を引き出す方法
この記事を読むのに必要な時間は約 28 分です。 お問い合わせ お悩みポイント ・不登校を解決するには、結局のところ何をしたらいいの? ・学校に行けない理由がどうしても気に ...
続きを見る
3. 【小・中・高】ごとの不登校サポートのコツ
ここからは、子どもの成長に合わせたサポートのコツを紹介します。
- 小学生の子どもの不登校サポート
- 中学生の子どもの不登校サポート
- 高校生の子どもの不登校サポート
3-1. 小学生の子どもの不登校サポート
小学校低学年の場合、親御さん(とくに母親)と離れることに対して、強い不安感を抱いていることも。
強い不安が要因で学校に行けなくなることは珍しくなく、とくに、生まれつき不安になりやすい子どもには多く見られます。
子どもが抱える不安を小さくするには、あなたと子どもの愛着(アタッチメント)がポイントです。
愛着(アタッチメント)の特徴は、次のとおり。
- 特定の他者との間に結ばれた、強い絆
- 別名:情緒的な絆
- 子どもと親の愛着が強いほど、心に安定した安全基地を築けるため、対人関係を広げやすい
もしも、「子どもとの愛着(アタッチメント)が弱いかも…」と思っても、大丈夫。
愛着(アタッチメント)は、無償の愛情によるコミュニケーションによって、今からでも強くできます。
こちらもCHECK
-
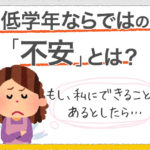
-
【小学生の不登校】低学年ならではの原因「不安」と向き合う方法とは
この記事を読むのに必要な時間は約 28 分です。 疑問&お悩み 小学校低学年の子どもが不登校になったけど、どうしてなの? 不登校の小学生を持つ母親だけど、なにをすればいい? 低学年の小学生が学校復帰す ...
続きを見る
3-2. 中学生の子どもの不登校サポート
中学生は思春期にあたり、身体と心に大きな変化があらわれる時期です。
不安定で不確かな状態であるため、不登校であろうとなかろうと子どもへのサポートは必須と言えます。
また、反抗期でもあるため、こちらが手をつくしても反応がないことも…。
親御さんもジレンマを感じやすく、骨の折れる期間でもあります。
サポーターとして大切なのは、繋がりを維持すること。
「私たちは、あなたのことを気にかけているよ」という、繋がりを絶やさないでください。
繋がりがなくなると子どもは、「不登校になったから、自分は見捨てられたのではないか?」と自分の存在を疑ってしまいます。
時期的に、成績や進路が気になるかもしれませんが、まずは親子で一緒に不登校を乗り切ることが先決です。
手始めに環境を整えることを意識してみてください。
子どもが「自分は独りじゃないんだ。気にかけてくれる人がちゃんといるんだ」と、少しでも希望を持てるようになると不登校解決に近づきますよ。
こちらもCHECK
-
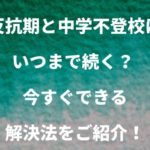
-
反抗期と中学不登校はいつまで続く? 今すぐできる解決法をご紹介!
この記事を読むのに必要な時間は約 39 分です。 この記事を選んでいただき、 そして大切なお時間を使っていただき本当にありがとうございます。 中学3年間不登校 ...
続きを見る
3-3. 高校生の子どもの不登校サポート
高校生は思春期の終盤で、子どもと大人の境界に立っています。
自立に向けてのサポートも必要ですが、まずは不登校からの脱却を目指しましょう。
高校生で不登校になった場合、大きく分けると以下の2パターンが考えられます。
- 高校ではじめて不登校になった
- 小学生もしくは中学生の頃も不登校だった
前者は、高校生ではじめて不登校という挫折に直面したパターン。
後者は、一時は不登校が治ったように見えて、本当は不登校の挫折から抜け出せていないパターンです。
共通点は、不登校が挫折になっていることです。
あなたは覚えていますか?
不登校は捉え方次第で、成長のためのバネにできます。
「今さら不登校解決なんて…」と諦めないでください。
あなたが今のうちから効果的なサポートをすれば、学校復帰に間に合う可能性はあります。
高校に留年や退学があるのは事実ですが、子どもの将来を考えたら「遅すぎる」ことはないでしょう。
「あのときの不登校経験があったから、今の自分があるんだ」
今、きちんと不登校を克服できれば、子どもがしなやか折れない心を持つこともできます。
こちらもCHECK
-
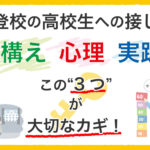
-
【不登校の高校生への接し方】心構え・心理・実践の3つで不安は解消
この記事を読むのに必要な時間は約 31 分です。 お悩みポイント 高校生で不登校の子どもと、どう接すればいいのかがわからない 子ども自身、今の状況で一体、何をどう考えているのか… 早く学校に戻ってほし ...
続きを見る
4. 不登校期間中の勉強・体調・生活のサポートはどうする?
ここでは、次の3点のサポートを紹介します。
- 勉強面のサポート
- 体調面のサポート
- 生活全般のサポート
3つとも学生の日常生活に関わっています。
サポートできること・本人に任せることのメリハリをつけながら、取り組みましょう。
4-1. 勉強面のサポート
勉強面のサポートは、しておいて損をすることはありません。
もともと勉強嫌いでないなら、興味のある事柄を広く深く学べるチャンスです。
反対に、勉強嫌い・授業が「わからない」ため不登校になったのであれば、以下に挙げる外部の力を借りましょう。
- 教育支援センター(適応指導教室)
- フリースクール
- 塾
- 家庭教師
- 通信教材
- サポート校(通信制高校に通う高校生向け)
学習面のサポートは学校の授業に追いつかせるのではなく、単元や学年を遡って勉強できる環境がおすすめです。
確実に理解できるところから取り組めるため「わかった!」という感覚が取り戻しやすく、勉強への苦手意識も薄れていきます。
通信教材など自ら勉強をする必要があるタイプを選ぶなら、この機会にあなたも勉強をはじめませんか?
お互いに勉強する姿を見せ合うと、机に向かう習慣づくりの手助けになりますよ。
こちらもCHECK
-
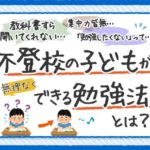
-
「不登校で勉強がわからない…」勉強の遅れは取り戻せる!5つの勉強方法!
この記事を読むのに必要な時間は約 45 分です。 ポイント 不登校の子どもが、全く勉強していない 勉強はしているけれど、学校のカリキュラムに追い付けているか不安 不登校中でも勉強してほしいが、どんな声 ...
続きを見る
また、通信制高校に通う高校生であれば、サポート校もおすすめです。
課題のサポートが受けられるのはもちろん、似た境遇の人が多いため友だちに恵まれる環境が整っています。
4-2. 体調面のサポート
身体と心は繋がっているため、不登校によるストレスが長引けば何かしら影響が出てきます。
子どもが体調不良を訴えるのであれば、一度かかりつけ医に診てもらいましょう。
心療内科・メンタルクリニックではカウンセリングを勧められることがあります。
カウンセリングは、カウンセラーとの会話を通して自分の感情やストレスとの向き合い方、考え方の歪みについて知るきっかけになることも。
また、外へ出かけて第三者と会うため、身なりを整えたり生活リズムを正すことにも繋がります。
4-3. 生活全般のサポート
不登校の解決にあたり、規則正しい生活を送ることは必要不可欠です。
しかし、実践するハードルは高く、家にいる期間が長いほど生活のメリハリが失われ、引きこもりへと悪化します。
とくに、電子機器を子どもの好き勝手に使える状況であると昼夜逆転しやすいため、早めの対策が肝心です。
- スマホ
- パソコン
- ゲーム
※YouTubeサイトへ移動します
あなたのサポートに加え、可能なら家族以外の人と接する機会をつくっておきたいところ。
- 教育支援センター(適応指導教室)
- フリースクール
- 習い事など
- サポート校(通信制高校に通う高校生向け)
人とコミュニケーションをとる予定があれば生活リズムは狂いにくくなり、気にかけてくれる人との繋がりも維持できます。
5. まとめ
あなたが不登校の子どもに対してサポートすることは、次の2つです。
- 親御さんもサポートを受ける
- 子どもを取り巻く環境を整えてあげる
あなたが支援を受けると、感情が安定しやすくなります。
感情が落ち着いていれば、子どもの言動にも慌てず対応できるようになるため、サポーターとして子どもをしっかり支えられます。
合わせて、子どもを取り巻く環境を整えましょう。
不登校によるストレスを和らげつつ、逆境を抜け出せるようにサポートするためには欠かせません。
実際に子どもをサポートをするときは、「これまで」と「これから」の子育てがキーポイントになります。
- これまでの親子関係のあり方を見直す
- 子どもへの効果的な接し方を学ぶ
- 日々の生活の中で育て直しを実践する
子どもが何歳であれ、子どもに無条件の愛を持つことが育て直しのカギです。
「あなたのことを気にかけているよ」という姿勢でコミュニケーションを取りましょう。
時と場合によっては「あなたと本気で向き合っているの!」と、毅然とした態度も必要です。
あなたが子どものサポーターとして、子育てをアップデートさせると変化があらわれます。
あなたの変化と子どもの成長により、子どもは不登校から抜け出す力を身につけられるのです。
6. 追伸:不登校の子どもをサポートできるか相談してみませんか?
不登校の子どものサポートって、「本当に私にもできるの?」
不安・疑問が残るのは、ここまで読んでくれたあなたが子どもの不登校を解決したいと「本気」で思っている証拠です。
本気であるために、確実に不登校から抜け出せる方法を探しているのではないのでしょうか。
「子どもの不登校はどうにかしたい。だけど、サポートすることが本当に正しいのか、正直なところ疑問もある」
あなたが葛藤を抱くのは、当然です。
迷いや不安を小さくしたいなら、一度は私たちが展開している【平均3週間で不登校解決プログラム】の無料オンラインセミナーを覗いてみませんか?
親子関係・子どもへの接し方について、あなた自身が確かめてください。
私たちがあなたを支えます。
一緒にお子さんの不登校を解決するサポーターになりましょう!
参考文献
小野善郎『思春期の謎めいた生態の理解と育ちの支援—心配ごと・困りごとから支援ニーズへの展開-親・大人にできること』福村出版(2020).
杉浦 孝宣『不登校・ひきこもりの9割は治せる—1万人を立ち直らせてきた3つのステップ』光文社(2019).
メグ・ジェイ『逆境に生きる子たち—トラウマと回復の心理学』(北川知子訳)早川書房(2018).
ポール・タフ『私たちは子どもに何ができるのか—非認知能力を育み、格差に挑む』( 高山真由美訳)英治出版(2017).