この記事を読むのに必要な時間は約 37 分です。
「ADHDの子どもが不登校になってしまった」
「うちの子がADHDと診断されてしまって、学校生活が不安」
不登校のお子さんを持つ親御さんから、よくこのような相談を受けます。
ADHDなどの発達障害の二次障害として不登校になってしまうお子さんは少なくありません。
「自分の子どもはADHDだから…」と、不安に思っている親御さんもいるでしょう。
安心してください。ADHDだからといって何かを諦める必要はありません。
お子さんの特性をよく理解してお子さんの自己肯定感を育てていけば、再登校に導くことは可能です!
【平均3週間で不登校解決プログラム】を展開する小川涼太郎監修のもと、お話しする内容は次のとおり。
記事を読むとわかること
- ADHDと不登校の関係性
- ADHDや発達障害の子どもが不登校になる原因
- ADHDや発達障害の子どもが不登校になったときに親ができる支援
- ADHDで不登校になったお子さんの再登校事例
親御さんが抱える不安を解消できれば幸いです。
スダチでは、不登校になったお子さんを平均3週間で再登校に導いています。
病院でADHDと診断されてしまったお子さんを再登校へ導いた実績もありますので、ぜひ、無料相談でお子さんの現状をお聞かせください!
\無料相談を申し込む/
1. ADHDと不登校の関係性
近年、不登校児は増加傾向にあります。
令和3年の文部科学省データによると、小学生から高校生の不登校児の統計人数は29万5925人。前年度と比べて5万6747人の不登校児が増加していています。
参考:令和3年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について
子どもたちが「学校へ行きたくない」と行き渋るのには、以下のような原因があります。
- 人間関係がうまくいっていない
- いじめを受けている
- 勉強についていけない
- 生活リズムの乱れ
- 朝になると具合が悪くなる
ADHDのお子さんは、その特性から人間関係をうまく築くことができなかったり、勉強についていけなかったりする傾向にあります。
そのため、ADHDなどの発達障害を持つお子さんは不登校になりやすいのです。
1-1. 不登校児の発達障害の割合
福島大学では、不登校児の中に発達障害の子どもがどのくらいいるかを調査しています。
- 小学生16.1%
- 中学生7.9%
- 高校生13.3%
調査結果によると、上記の割合でADHDなどの発達障害を持っているお子さんが不登校になっていることがわかりました。
ADHDと診断されていないグレーゾーンの子を合わせると、不登校児の20~30%はADHDなどの発達障害を持っていると考えられます。
発達障害であれば必ず不登校になるというわけではないですが、ADHDなどの特性が学校へ行きにくくなる原因に繋がっている可能性があります。
1-2. ADHDとは
ADHDとは、「注意欠如・多動性障害」と呼ばれる発達障害のひとつです。
生まれつき脳の一部が機能障害を起こしており、それによって「不注意」「多動性」「衝動性」の3つの性質が現れやすくなっています。
不注意で忘れ物が多くなったり、多動性によりじっとしていられなかったり、衝動的に何かをしてしまって失敗するということが多く、自己肯定感が下がりやすく、自分を責めやすい子が多いです。
発達障害には、他にもASD(自閉症スペクトラム障害)とLD(学習障害)などがあります。
特徴は、次の通りです。
| ASD(自閉症スペクトラム障害) | 自閉症やアスペルガー症候群など、他者の気持ちを理解することが難しい障害 |
| LD(学習障害) | どうしても漢字が書けない、計算だけが難しく感じるなどの学習障害 |
これらの発達障害は生まれながらの特性であり、親御さんの育て方によって変わるものではありません。お子さんが発達障害と診断されても自分を責めず、お子さんの特性と向き合うことが大切です。
自閉症についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひチェックしてみてください。
こちらもCHECK
-

-
自閉症は親のせいではない!自閉症や発達障害の子どもが不登校になりやすい理由と親ができる適切な支援
この記事を読むのに必要な時間は約 26 分です。 「うちの子どもが自閉症なのは、親である私のせいなの?」 「自閉症や発達障害の子どもはどうして不登校になりやすいの?」 自閉症のお子さんが ...
続きを見る
1-3. ADHDの特性(不注意・多動性・衝動性)
ADHDには、3つの特性があります。
ADHDのお子さんは、このうちのどれかが優位になっていることが多いです。
例えば、不注意性が優位になっている子は、集中力がないものの落ち着きがなく動き回ってしまう様子はあまり見られません。
お子さんがどの特性が優位になっているかを確認しましょう。
また、お子さんによっては複数の特性が優位になっている混合タイプもいます。
不注意性が優位になっている子は、以下のような特性があります。
- 集中力が持続しない
- すぐ気が散ってしまって周りを気にしている
- 忘れ物が多い
- 自分の好きなことだけ集中して周りが見えない
- 友人と話している最中に別の事を始めてしまう
集中力がないため学校の授業についていけない状況になることが多いです。また、友人トラブルなどを起こしやすい傾向にあります。
多動性・衝動性が優位になっている子は、以下のような特性があります。
- じっとしていると落ち着かず、動き回ってしまう
- 落ち着きがないといわれる
- 授業中に歩き回ったり、指名していないのに発言してしまう
- カッとなって友人に暴力をふるったり、暴言を吐いたりする
多動性が優位になっている子は、学校の先生からたくさん注意を受けていることが多く、自己肯定感が下がりやすい傾向にあります。
また、衝動性で自分を抑えられず、思わぬトラブルを引き起こすこともあります。
1-4. ADHDの二次障害として不登校になりやすい
二次障害とは、発達障害が原因で引き起こされてしまうもののことを指します。
ADHDのお子さんは、二次障害として不登校や引きこもりになりやすいです。
ADHDの特性は、友人トラブル、先生とのトラブルを起こしやすいです。さらに、その特性を注意されたり、指摘されたりすることによって、お子さんは自分を否定されたような感覚になり自己肯定感が下がってしまいます。
自己肯定感が下がることで、お子さんは無気力になったり、学校に行き渋ったりして、不登校になるケースが多いです。
お子さんが不登校になるきっかけは、ADHDだけでなくさまざまな要因が絡み合っている場合が多いです。
以下の記事では、不登校のお子さんの心境と傾向を7つのタイプに分けて解説しています。
お子さんが今どのような気持ちを抱えているのか探る際の参考にしていただけたら幸いです。
-

-
参考不登校になったら親がやるべき3つのこと|不登校の7つのタイプと今の子どもの状態・解決法
この記事を読むのに必要な時間は約 87 分です。 「子どもが不登校になってしまった…子どもにどう接していけば良いのかわからない」 「子どもの今の状態に適した対処方法を知って、不登校を解決したい」 お子 ...
続きを見る
また、ADHDなどの発達障害傾向が引きこもりの原因になることもあります。
発達障害傾向のお子さんが引きこもりにならないために親御さんができることについては、次の記事をご覧ください。
こちらもCHECK
-

-
発達障害でもひきこもりを脱出できる|ご家庭でできること、相談できる窓口を紹介
この記事を読むのに必要な時間は約 35 分です。 「発達障害の子どもが不登校になりそのままひきこもりになってしまった…」 「ひきこもりの子どもが発達障害と診断されて先が不安になってきた」 発達障害の傾 ...
続きを見る
もちろん学校だけでなく幼稚園や保育園も行きたがらないケースがあります。
こちらもCHECK
-

-
発達障害の子どもが幼稚園を登園しぶり・登園拒否する原因とは?親御さんができる対策方法を解説
この記事を読むのに必要な時間は約 31 分です。 「発達障害の子どもが幼稚園に行き渋る。子どもにあった園へ転園した方がいい?」 「何が嫌で毎日登園を拒否するのかわからない。解決のために何をすればいい? ...
続きを見る
2. ADHDや発達障害の子どもが「学校へ行きたくない」と思い不登校になる理由
ここでは、ADHDのお子さんが、学校へ行きたくないと思ってしまう原因について解説します。
2-1. 「周りよりできない」と比較して自己肯定感が下がりやすい
ADHDのお子さんは、学習面で遅れを取ってしまうことが多いです。
- 授業に集中することができない
- じっとして机に座っていることができない
- 宿題を忘れてきてしまう
こういった性質が優位になっていると、勉強面で遅れをとりやすいでしょう。「周りよりできない」と自分で自己肯定感を下げてしまいます。
また、どの特性が優位であっても、「他の子はできているのに、自分はできない」とお子さん自身が思っています。
学校でも「できない子」「トラブルを起こしやすい子」というレッテルを張られてしまうことが多く、学校の先生からもすぐに注意されてしまうことも。
ADHDだからといって、お子さんは努力をしていないわけではありません。努力しても、その特性から上手くいかないことが多いだけなのです。
自分が努力してみんなと同じように頑張ろうとしても、ADHDの特性のせいで周りよりできないと感じてしまうと、お子さんの自己肯定感はどんどん下がっていきます。
お子さんは自己肯定感が下がり切ってしまって無気力になり、学校に行くことを嫌がるようになって不登校になってしまうのです。
2-2.「みんなと同じ」ができないことでからかわれる
学校は集団行動を基本としていて、みんな同じように足並みをそろえて行うことが多いです。勉強ももちろんですが、クラスのルールや決まりごとが多いこともあります。
ADHDのお子さんは、不注意でそのルールや決まりごとを忘れてしまったり、多動性や衝動性によって自分を抑えられずにルールや決まりごとを守れないことがあります。
「みんなと同じ」ができないことで、先生に注意されるのはもちろん、友人にからかわれることもあります。
からかわれることで、お子さんはまた自己肯定感が下がってしまいます。
2-3. ADHDの二次障害によって友人トラブルを起こしやすい
ADHDのお子さんは、友人トラブルも起こしやすい傾向にあります。
ADHDの特性の二次障害によって、以下のような行動をしてしまうからです。
- 順番待ちをしている他の友人を抜いて並んでしまう
- 授業中に動き回ってしまって、友人の迷惑になる
- 思ったことをすぐに口にしてしまい友人とトラブルになる
- 自分の話をしゃべり続けてしまう
このようなことが、ADHDの特性上起きてしまいます。
友人とあまりいい関係を築くことができずに、クラスに居場所がないという子も少なくありません。
2-4. 衝動性によってトラブルを起こしやすい
衝動性は、カッとなったときに思わぬことをしてしまうことが多いです。
- 友人と言い争いになって突き飛ばす
- 学校の先生に注意されて、怒って暴れる
- 自分がやりたいことができずに激昂してしまう
自分の中の衝動が抑えられずに、学校でトラブルを起こしやすく、そのまま学校に行きにくくなってしまうというケースも少なくありません。
2-5. ADHDの子どもは「勉強しない」「勉強できない」ことが多い
ADHDのお子さんは、どうしても学習面で後れを取りやすいです。
多動性によって授業に集中できないことや、不注意性で物音などに気を取られて授業を聞いていないことが多いです。
お子さんも自分の特性によって勉強に集中できないので、勉強自体を嫌がってしまう傾向もあります。
学校で過ごすほとんどの時間は勉強なので、学校に行きたくないと思うようになってしまうのです。
3. ADHDや発達障害の子どもが「学校へ行きたくない」と言いだし不登校になったときに、親御さんができる支援
ADHDや発達障害のお子さんが「学校に行きたくない」と言いだしたとき、親御さんがするべき支援について解説します。
3-1. お子さんがつらいときは気持ちを受け入れる
お子さんが「学校に行きたくない」と言いだしたとき、「学校へ行きなさい!」と無理に学校に行かせるような声かけはおすすめできません。
お子さん自身「本当は学校へ行かなきゃいけないのにどうしても行けない」「普通に過ごしているだけなのに学校で浮いてしまいつらい」と葛藤しています。
そのようなとき、無理にお子さんを学校に行かせてしまうと、お子さんはさらに傷つくだけでなく「この親は私のことをわかってくれない」と信頼関係に亀裂が生じることもあります。
「学校に行きたくない」と親御さんに話すこと自体、実は勇気がいることです。
学校でつらいことがあったお子さんの気持ちをまずは受け入れて認めてあげることが大切です。
そのうえで「一緒に問題を解決していこう」とお子さんと同じ目線に立ち再登校に向けて前進しましょう。
3-2. スダチなどの専門機関に相談する
お子さんが不登校気味になったとき、親御さんが「見守るだけ」では、不登校は解決しません。学校も、不登校の生徒を積極的に学校復帰させようとはしません。そのため、親御さんが行動に移しお子さんをサポートしてあげることが大切です。
その際は、親御さん一人で悩まずに専門機関の力を借りて、二人三脚でお子さんの不登校を解決しましょう。
「ADHDの気質があるしどこに相談をすれば良いのかわからない」
「無理矢理行かせるのではなく、主体的に再登校してほしい」
その場合は、スダチにご相談ください。
スダチの支援では、不登校の根本原因にアプローチして不登校を解決しております。
根本的な問題解決が可能なため、お子さんから主体的に学校復帰し、その後も不登校になることなく、充実した学校生活を送っていただいています。
不登校気味のお子さん、不登校が長期化したお子さん、ADHDの特性から不登校になり悩んでいたお子さん、みなさん平均3週間で再登校しています。
ぜひ一度、お子さんの現状をお聞かせいただけたら幸いです。
無料オンラインセミナー動画をご視聴いただいた方に、無料相談を実施中です。
オンライン相談であり1対1で顔出しも不要です。お気軽にご活用ください。
\無料相談を申し込む/
3-3. 正しい親子関係を築いて、お子さんの自己肯定感を育てる
ADHDのお子さんは、その特性から学校生活を送るだけで自己肯定感が下がってしまうことがあります。
お子さんの自己肯定感を育むには、信頼できる親御さんから褒められることが必要です。
お子さんが行った「結果ではなく、過程」を褒めるようにしましょう。
親御さんから褒められることで、お子さんの自己肯定感は少しずつ育ちます。
重要なのは、お子さんから信頼される親であること。
お子さんが親御さんを信頼していないと、どんなに褒めてもお子さんには届きません。
まずは、正しい親子関係を築いて、信頼できる関係になることが大切です。
- お子さんとは正しい距離感で接する(過保護、過干渉、放置はしない)
- お子さんが正しいことをしたら目一杯褒める
- お子さんがダメなことをしたらダメと毅然とした態度で教える
正しい親子関係を築いて、お子さんの自己肯定感を育てましょう。
自己肯定感が育つとお子さんの心の元気が回復し、「学校に行きたい」と主体的に思えるようになります。
3-4. ADHDの特性を理解した対策を親子で考える
正しい親子関係を築いて、お子さんと落ち着いた話ができるようになったら、ADHDの特性を理解した対策を親子で考えるようにしましょう。
例えば、忘れ物が多い子には「どうすれば忘れ物をしなくなるかな?」と問いかけましょう。
親御さんから一方的に押し付けるのではなく、お子さん自身に考えさせて、答えを導き出しましょう。
お子さんの特性から「こんなときどうしよう?」と親子で話し合って、解決策を練ることで再登校した後に、お子さんのトラブルを減らすことができます。
4. ADHDや発達障害の子どもが不登校になったとき家庭での過ごし方
ADHD気味のお子さんが不登校になったとき、その特性がゆえにスマホやゲームなどの好きなことだけに没頭して過ごしてしまう場合があります。
スムーズに再登校していただくためにも、ご家庭での過ごし方について解説いたします。
4-1. 勉強のサポートをする
不登校になっている期間も、再登校できた後も勉強のサポートは必要です。
自分自身で進める通信教育などは、ADHDの特性上向いていないので、個別指導塾や家庭教師など、お子さんにあった勉強方法を選ぶようにしましょう。
その際のカリキュラムはスモールステップで、まずはひとつずつ物事を理解していくように進めることが大切です。
4-2. 生活リズムを整える
ADHDのお子さんは、自分のやりたいことにだけ熱中してしまったり、スケジュール管理が苦手だったりします。
不登校で学校を休んでいる間、ゲームやSNSに没頭してしまい、デジタル依存になりやすいです。
お子さんのスケジュール管理や、生活リズムはしっかりと整えるようにしましょう。
再登校する際に、昼夜逆転して生活リズムが乱れていると、それがネックになって再登校まで長引くケースがあります。
まずは正しい生活リズムで生活できるように親御さんがサポートするようにしましょう。
お子さんが朝起きられないときの対処法については、次の記事も参考にしてみてください。
こちらもCHECK
-

-
【子どもが朝起きられない】中学生・高校生の子どもが朝起きない原因|起立性調節障害・発達障害との関係【不登校になる前に親ができる対処法】
この記事を読むのに必要な時間は約 52 分です。 「中学生・高校生の子どもを、朝起こしても全然起きない…」 「朝起きない中学生・高校生の子どもが、不登校気味になってきた…」 ...
続きを見る
5. ADHDから不登校になった子どもを再登校に導いたスダチの支援事例
過去にスダチが再登校に導いた支援事例を紹介します。
ADHDの二次障害から不登校になってしまった中学2年生の男子の事例となります。
ADHDが原因で、忘れ物が多く、宿題を提出しないことも多かったそう。
進学校に通っていたので、宿題や課題も多く、こなしきれずに不登校になってしまいました。
そんな時、「楽しい学校生活を送って欲しい」と親御さんからスダチへご相談をいただきました。
お子さんは親御さんに甘えることが多くなり、親御さんから離れることができないような状況が続いていました。
スダチの支援では、お子さんとの距離感を正して、正しい親子関係を築くために、親御さんへお子さんと距離を取っていただくよう、お願いさせていただきました。
あえて家をあける機会を作ったり、毅然とした態度で子どもに接したり、適切な距離感を保つことを意識していただいた結果、お子さんは約1ヶ月で主体的に再登校できるようになりました。
その後不登校にはならず、元気に学校に通っているようです。
こちらの記事で詳しく紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。
こちらもCHECK
-
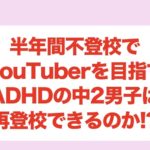
-
【事例紹介】半年間不登校でYouTuberを目指すADHDの中2男子は果たして再登校できるのか?
この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。 すADHDの中2男子は果た半年間不登校でYouTuberを目指すADHDの中2男子は果た して再登校できるのか? 今回は、半 ...
続きを見る
6. ADHDで不登校気味のお子さんを持つ親御さんからのよくある心配事
ここでは、不登校気味のお子さんを持つ親御さんからいただく、よくある心配事について回答します。
何か心配事、不安なことがありましたら、無料相談の際に回答いたします。
6-1. ADHDは何歳で落ち着きますか?
ADHDは脳の一部の機能障害なので、完治するということはありません。
しかし、多動性は13~18歳頃に落ち着く子が多く、不注意性と衝動性は大人になっても残る傾向にあります。
6-2. 発達障害の不登校の特徴は?
発達障害の子どもが不登校になる特徴は、学校に馴染めていないケースが多いです。
- 勉強についていけない
- 友人とうまく関係が築けていない
この2つが原因で不登校になることが多いです。
特に、ADHDのお子さんは、不注意や多動によって授業に集中できないことが多く、学習面の遅れが出やすい傾向にあります。
また、不注意性、衝動性によって友人に言い過ぎてしまったり、注意されたことをまたやってしまったりして、友人トラブルも起きやすいです。
6-3. ADHDの女の子の特徴は?
ADHDの女の子は、女の子特有のコミュニケーションが上手くいかないことが多いです。
衝動性によって思いついたままに話してしまって、友人を傷つけてしまうことや、自分中心の話ばかりしてしまって周りに溶け込めないことがあります。
6-4. 発達障害グレーゾーンの高校生の特徴は?
小学生・中学生と比較して、高校生は自主性が求められます。
スケジュール管理や勉強の管理などを自分で行わなければいけないので、それをつらいと感じているADHDの高校生は少なくありません。
- 人間関係が上手くいかない
- 忘れもの、紛失が多い
- 文化祭や体育祭などの行事が苦手
- 授業に集中できない
- 特定の教科だけ遅れを取ってしまう
- 課題量が多く、スケジュール管理できずにつまずく
このような特徴が出ることがあります。
6-5. 発達障害(ADHD)で不登校になった中学生・高校生の将来は?
ADHDだからといって、就職ができないということはありません。
ADHDが原因で不登校になった中学生・高校生は、その特性と付き合いながら大学進学、就職をする子が多いです。
多動性は13歳から18歳で落ち着く子が多いので、不注意と衝動性を抑えるように立ち回ることで、二次障害を引き起こさずに過ごせることもあります。
不登校の子どもが大学受験をするまでのロードマップを詳しく解説していますので、こちらの記事もぜひチェックしてみてください。
こちらもCHECK
-
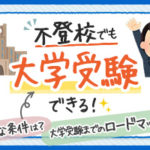
-
不登校でも大学受験できる!大学受験に必要な条件とロードマップ!
この記事を読むのに必要な時間は約 34 分です。 高校生の子どもの不登校が続いている…。大学受験するには転校しかないの? 子どもの不登校を解決する方法が知りたい。 結論から申し上げると、今高校生のお子 ...
続きを見る
また、大学受験を目指す際には高卒資格の取得が必要となります。
通信制高校ならば、登校日数が年に数日である学校もあり、ほとんどを自宅学習で過ごすため発達障害のお子さんも無理なく高卒資格取得を目指せることもあります。
通信制高校については次の記事を参考にしていただけると幸いです。
こちらもCHECK
-
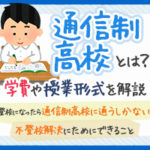
-
通信制高校とは?入学の条件、学費、単位取得の仕組みや卒業後の進路、不登校の解消に役立つのかも紹介
この記事を読むのに必要な時間は約 52 分です。 「子どもが不登校になってしまった…この先の進路として通信制高校を選択肢にいれた方が良い?」 「通信制高校はどんなところ?学費や入学条件、卒業後の進路は ...
続きを見る
6-6. 発達障害(ADHD)で不登校になった子どもの家庭の過ごし方は?
ADHDが原因で不登校になったお子さんに対しては、以下の事を守っていただくと再登校に結び付きやすいです。
- 勉強をする
- 趣味や習い事を始める
- 生活リズムを整える
お子さんが再登校するにあたって、学校の授業がわからないことはストレスです。自宅で勉強を続けて、いつでも学校に行けるようにしておくことが大切です。
また、自宅で過ごしていると外に出ることを嫌がるようになるので、趣味や習い事を続けながら外で人と関わることを続けるようにしましょう。
ADHDのお子さんはスケジュール管理が苦手なので、ゲームだけに没頭してしまうこともあります。お子さんの生活リズムを整えることで、再登校する際にスムーズです。
7. まとめ
お子さんが持つADHDという発達障害は、決して悪いことではありません。
親御さんもお子さん自身も、ADHDの特性と向き合うことができれば、問題なく学校に通えるようになります。
スダチの支援では、不登校の根本的な問題解決が可能です。
お子さん自身がADHDの特性と向き合い、主体的に問題解決することによって、学校復帰した後も不登校にならずに学校に通い続けられます。
ADHDの特性で悩んでいるお子さんも、平均3週間で再登校に導いています。
ぜひ一度、お子さんの現状をお聞かせいただけたら幸いです。
無料オンラインセミナー動画をご視聴いただいた方に、無料相談を実施中です。
オンライン相談であり1対1で顔出しも不要です。お気軽にご活用ください。
\無料相談を申し込む/






