この記事を読むのに必要な時間は約 43 分です。
「子どものひきこもりが長引いてしまっている。脱出する方法を知りたい。」
「ひきこもりから立ち直るきっかけや脱出した人の体験談を知り、子どもへの支援に生かしたい。」
お子さんが自宅にひきこもる状況が続いていると、どうにかして現状を変えるために、親御さんは模索していることと存じます。
お子さんがひきこもりから脱出するために大切なことは、適切な支援を受けること、家庭での関わり方を変化させてみることです。
ひきこもりは、根本解決し完全に脱出することができますのでご参考になさっていただけたら幸いです。
本記事では、ひきこもりから脱出する方法や、お子さんの抱えている心境、脱出した人の体験談を中心に紹介します。
平均3週間で再登校に導くサービスを提供する小川涼太郎監修のもと、お話しする内容は次のとおりです。
記事を読むとわかること
・ひきこもりの人の数と抜け出す人の割合
・ひきこもりから脱出するきっかけ
・ひきこもりを脱出するための思考方法、行動方法
・ひきこもりのお子さんに対して親御さんができること
「子どものひきこもりを解決したいが何からどうしてよいかわからない」そのような時の参考になりましたら幸いです。
スダチでは、小学校〜高校生の不登校・ひきこもりを根本解決し、再登校へ導いています。
スダチの支援では、毎日親御さんからお子さんの様子をヒアリングして、その時のお子さんに必要な声かけ、接し方をフィードバックしております。
1番身近な存在で、毎日最も長い時間を過ごす親御さんに直接支援を実施していただくことが、スムーズにひきこもりから脱出する鍵です。
支援させていただいたお子さん方は、平均3週間で再登校を果たしています。
親御さん方がフィードバックに基づき積極的に行動してくださるおかげで、2023年10月時点で600名以上のお子さんが再登校に成功しました。
まずはスダチの無料オンライン相談をご活用いただき、現状のお子さんのご状況や親御さんが抱える悩みをお伺いできましたら幸いです。
ひきこもり脱出のための一歩を一緒に踏み出しましょう。
\無料相談を申し込む/
1. ひきこもりからの脱出についての現状
1-1. ひきこもりとは|現状の人数
厚生労働省が定めるひきこもりの定義は、次の通りです。
「原則的には6ヶ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態のこと」
このうち、慢性的な疾患を抱えており、自宅で過ごす時間が必須のケースはひきこもりに含まれません。
ただし、6ヶ月に満たなくても不登校が長期化して自宅や自室に1日を通して滞在する状況のときは、ひきこもりになりかけていると言えます。
お子さんの抱えるつらい気持ちを解決していくために、早めに解決に向けて行動することが大切です。
参考:厚生労働省「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」
また、内閣府のデータによると、ひきこもりは日本全国で115万人以上いると推計されています。年齢別の割合は以下の通りです。
◼︎15~39歳:推計数54万1千人
| 15〜19歳 | 10.2% |
|---|---|
| 20〜24歳 | 24.5% |
| 25〜29歳 | 24.5% |
| 30〜34歳 | 20.4% |
| 35〜39歳 | 20.4% |
◼︎40~64歳:推計数61万3千人
| 40〜44歳 | 25.5% |
|---|---|
| 45〜49歳 | 12.8% |
| 50〜54歳 | 14.9% |
| 55〜59歳 | 21.3% |
| 60〜64歳 | 25.5% |
参考:内閣府「若者の⽣活に関する調査報告書」(2016)
内閣府「生活状況に関する調査報告書」(2019)
1-2. ひきこもりを脱出した人の割合
内閣府の資料によると、過去にひきこもり経験がある人のうち、7割程度はひきこもりを脱出し社会復帰されていることがわかります。
- 正社員として働いている…46.3%
- 正社員以外(アルバイトなど)として働いている…27.4%
解決方法がわからず、親子ともに苦しいご状況かと思いますが、ひきこもりは適切な支援を受けることで脱出していけます。
また、ひきこもりを解決し再登校を果たす経験は、お子さんの自信につながります。お子さんがこれから社会で活躍していくうえでの、ひとつの通過点だと捉えていただけたら幸いです。
参考:内閣府「生活状況に関する調査報告書
」(2019)
2. ひきこもりから脱出するのが難しい理由・心理
ひきこもりから脱出できず長期化してしまう原因を紹介します。
また、ひきこもりになる原因については次の記事でもお話ししています。
こちらもCHECK
-

-
ひきこもりの原因は親のせい?ひきこもりの原因6つと脱出に向けて親ができる対策方法を紹介
この記事を読むのに必要な時間は約 35 分です。 「子どものひきこもりの原因は親の私にあるのかな…」 「子どもが引きこもりになった原因や脱出方法を知りたい」 お子さんがひきこもりになって ...
続きを見る
2-1. 自己肯定感が低く挫折経験から立ち直れない
自己肯定感が下がり切っており、立ち直れるような心境ではないことが挙げられます。
受験の失敗や対人関係の失敗などで挫折を経験して、引きこもるケースもあります。
- 「自分は何をやってもダメなんだ」
- 「また失敗してつらくなるくらいなら何もしたくない」
このような自己嫌悪や無力感から、学校へいく気力がなくなって引きこもってしまうのです。
しかし、同じような経験をしても挫折しない人もいますし、挫折を感じてもすぐに立ち直れる人もいます。
挫折で立ち止まる人とそうでない人の違いを辿っていくと、根本に自己肯定感の低さがあることも多いです。
自己肯定感が低いと小さな失敗でも原因が全て自分にあると考えてしまい、落ち込んでしまいます。
そして逃げるようにひきこもりとなった現状の自分をさらに責めてしまい、自己肯定感が下がり切っている状況です。
自己肯定感を育てていくことで、
- 「抱えていた問題は、意外と解決できるものなのかも」
- 「失敗をしても自分なら大丈夫」
という気持ちが芽生えます。
ひきこもりから脱出するために、お子さんの自己肯定感を育てていくことが大切です。
2-2. 精神疾患が長引いている
もしもお子さんが精神疾患を抱えている場合、服薬してもなかなか効果を得られなかったり、再発や悪化を引き起こして治療が長引くケースも少なくありません。
精神疾患が長引いてしまう状況は、さまざまな要因が複雑にからみあっていて、メカニズムが解明されていないと言われています。
ひきこもりの原因となりうる主な精神疾患として、以下が挙げられます。
- 広汎性発達障害
- 強迫性障害
- 身体表現性障害
- 適応障害
- パーソナリティ障害
- うつ病
統合失調症もひきこもりの原因となりますが、国のガイドラインではひきこもりの定義から外されています。
参考:厚生労働省「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」
統合失調症によるひきこもりが疑われる場合の対処法については、次の記事をご覧ください。
こちらもCHECK
-

-
統合失調症とひきこもりの関係性は?不登校は解決できる?親御さんがやるべきサポートを紹介
この記事を読むのに必要な時間は約 24 分です。 「不登校、ひきこもりになった子どもが統合失調症と診断を受けた…」 「できれば学校へ通わせてあげたいが、再登校を目指せるのだろうか」 不登校、ひきこもり ...
続きを見る
うつ病とひきこもりの関係性や、改善するためにできることについては次の記事でお話ししています。
こちらもCHECK
-

-
うつ病とひきこもりの関係性|不登校でうつ気味の子どもへ親はどう接したらいい?ひきこもりを解決する方法
この記事を読むのに必要な時間は約 33 分です。 「ひきこもりの子どもの気持ちが落ち込んでいる様子。これはうつ病なのではないか?」 「不登校の子どもがうつ病と診断され、最近ひきこもり気味…どうすれば解 ...
続きを見る
3. ひきこもりから脱出できる子どもの特徴
ひきこもりを根本解決しているご家庭の特徴について解説させていただきます。
3-1. 家族だけで抱え込まず周囲や専門機関の支援を受けていること
ひきこもりは家族だけで解決するのが難しく、長期化してしまうケースも少なくありません。
家族だけで抱え込まずに専門機関の支援を受けながら、解決に向けて動き出すことが大切です。
これまで数々のひきこもりのお子さんの支援を実施して解決してきた機関には、さまざまなノウハウや知見が蓄積されています。
過去の経験を生かしながら、ひきこもりの解決に導いてくれるでしょう。
また、常に気を配りながら支援しているご家族も疲弊していらっしゃることでしょう。
お子さん本人はもちろんのこと、ご家族も必要なときには専門機関の支援を受けながら、家族で一丸となって前進していくことが大切です。
3-2. 家族が見守ってそのままにしていない
お子さんを見守り続けるのではなく、家族が積極的に行動を起こしてお子さんへアプローチしていくことが大切です。
ひきこもりのお子さんは、自分では解決方法がわからず苦しんでいます。
自己肯定感も下がりきり、行動を起こすことが難しい現状であるからこそ、ご家族が解決に向けて行動していきましょう。
本人が第三者からの支援を嫌がるケースも多いです。その場合には、スダチのような親御さんへ直接お子さんへの関わり方を指導するような、支援機関を検討なさってみてください。
ひきこもりを見守り続けることをおすすめできない理由は、次の動画にてお話ししています。
3-3. ひきこもりを解決したいという気持ちがある
お子さんやご家族が「ひきこもりを解決して再登校したい、してほしい」という気持ちを持っていることも大切です。
親御さんの中には、「社会に出てつらい思いをするくらいなら、子どもに合ったコミュニティの中で生きて欲しい」と考えておられる方もいらっしゃるかもしれません。
お子さんのことを大切にしているからこそ、お子さんへの負担を考えて判断されていることと存じます。
ただ、現状の根本的な問題を解決しないままだと、お子さんはつらい気持ちを抱え続けることになってしまいます。
また新たなコミュニティで何かつらい経験をしたとき、再びひきこもりとなってしまうこともあるでしょう。
そのためひきこもりから脱出するためには、現状の根本的な原因を解決していき、社会復帰を目指していくことが大切です。
4. ひきこもりを脱出するきっかけ
ひきこもりを脱出するきっかけは人それぞれです。
本章では主なきっかけを紹介するので、きっかけをなるべく多く作ってあげるようにお子さんをサポートしていただけると幸いです。
4-1. 年齢を重ねていくことの焦り
ひきこもりになってから時間が経ち、年齢を重ねることでお子さん本人が「このままではいけない」と感じることもあります。
例えば、クラスメイトが受験で難しい学校に進学したり、周囲がアルバイトをし始めたりなどを知ることがきっかけとなる形です。
「立ち止まっている場合じゃない。自分も進まないと!」と感じると、解決に向けて動き出せることもあります。
4-2. 周囲に相談して支援を受ける
心を許している友人知人や支援機関のカウンセラーなどに相談することで気分が変わり、ひきこもりを脱出する意欲が湧くこともあります。
誰とも会わずに一人で過ごしていると、知らず知らずのうちに考え方が固定化してしまい、解決するのを諦めてしまうお子さんも多いです。
そんな時に誰かと話をすることで、自分の考え方の癖に気づきます。
- 「こんな考え方もあるんだ」
- 「抱えていた問題は、大したことじゃなくて、解決策があったんだ」
上記のように多角面から物事を考えられるようになり、前へ進むきっかけとなるでしょう。
また、支援先で適切なアプローチを受けることにより、ひきこもりの脱出につながります。
4-3. 生活リズムを整える
生活リズムを整えて健康的な暮らしをすると、身体が元気になりそれに引っ張られるように気持ちも前向きになってひきこもりの脱出につながるケースもあります。
家に引きこもって社会との接点がなくなると、朝に起きる理由を感じなくなり昼夜逆転したりデジタル依存に陥ったりするリスクが高まります。
不規則な生活習慣は身体や気持ちを疲れさせ、新しいことに挑戦する意欲を奪うので注意が必要です。
睡眠は特に大切で、夜にしっかり眠ることで成長ホルモンが分泌されて、お子さんの心身を整えてくれます。
お子さんは成長期であるため、大人よりも成長ホルモンの影響を受けやすいです。
就寝時間や起床時間などのルールをつくり、お子さんの生活リズムを整えてあげましょう。
4-4. 成功体験を積む
小さなことでも「うまくできた」「練習すればできるようになるんだ」と実感できると、これからのことも前向きな気持ちで考えられるようになります。
ひきこもりになっているお子さんは自己肯定感が下がり切っていることが多いです。
それによって新しい挑戦をすることに対して不安を抱えており、ひきこもりから脱出できない状態になっています。
小さな成功体験を積んで「自分にもできることがある」と思えるようになり、ひきこもりからの脱出についても向き合う気力が湧くようにサポートしてあげましょう。
とくにお子さんが興味を持っていることや、好きなことで成功体験を積めるようにすると、成功するまでの過程も楽しんで過ごせるでしょう。
ただし、ゲームやネットサーフィンなどは脳を疲れさせてしまい、ひきこもりからの脱出の妨げになることが多いので注意してください。
5. ひきこもりを脱出するための行動方法
5-1. 専門機関に相談する
まずは専門機関に相談して、解決に向けた道標を知っていくことが大切です。
さまざまなお子さんのひきこもりを解決してきた専門機関ならば、経験やノウハウが蓄積されています。
今のお子さんの心境を理解したうえで、解決するために必要なアプローチを実施してもらえるでしょう。
また、第三者に相談することで現状を俯瞰して見られるきっかけとなります。
多角面から物事を考えられるようになるので、気持ちの整理ができ、前向きな気持ちで行動していけるようになるものです。
スダチでは、ひきこもりや不登校のお子さんを抱える親御さんに支援を提供しています。
スダチの支援は、毎日お子さんの状況をヒアリングし、それに対してフィードバックをお送りしていることが特徴です。
脳科学と心理学に基づいて、今のお子さんに必要な親御さんからの声かけや接し方を具体的な内容でお伝えし、親御さんに行動していただいております。
最も身近な存在で、長い時間を一緒に過ごす親御さんからの接し方や声かけが変化することで、お子さんの自己肯定感がどんどん育ちひきこもりや不登校の根本解決を果たしてきました。
みなさま平均3週間で再登校を果たしているだけでなく、主体的に楽しんで学校へ通っています。
一度無料オンライン相談にてお子さんの現状をお伺いできましたら幸いです。現状をお伺いしたうえで、お子さんがひきこもりを解決するための道標をお話しさせていただきます。
オンライン相談は1対1で顔出しも不要です。
\無料相談を申し込む/
5-2. 趣味を見つけてみる
お子さんが好きになれること、得意なことを見つけて、趣味として取り入れるのもおすすめです。
好きな物事が上達して小さな成功体験を積んでいくことで、自己肯定感が育ちます。
自己肯定感が育つと、現状の問題を解決する意欲も湧いてくるでしょう。
また、同じ趣味を持っている人と繋がることで社会との接点ができ、それが脱出のきっかけとなるかもしれません。
5-3. 会いやすい人と会ってみる
機会があれば思い切って人と会ってみると、現状を冷静に見られるようになったり、やりたいことが見つかったりすることもあります。
大きなストレスがかかると、人と会うことへの苦手意識が生まれてしまうため、気負わずに話ができる会いやすい人と会ってみましょう。
もし家を出るのが難しい場合には、ビデオ通話や電話で相談できるサービスを利用するのも良いでしょう。
話すだけでも気が楽になり、考え方が柔軟になって解決の糸口が見つかることもあります。
無料で利用できる相談先については、次の記事で紹介しています。
こちらもCHECK
-

-
子どもの悩み相談はどこにすればいい?親子で利用できる公的機関や民間団体の相談窓口【ひとりで悩まず相談が大切】
この記事を読むのに必要な時間は約 25 分です。 「不登校の子どもが、学校の悩みなどを相談できる場所はある?」 「今子どもが抱えている悩みに適した相談先を知りたい。」 お子さんが不登校に ...
続きを見る
5-4. 出かけやすい場所や時間を見つける
お子さんにとって出かけやすい場所を探すことも大切です。
時間帯によって人通りや街の雰囲気が異なるため、同じ場所でも出かけやすい時間を見つけると外出する機会を増やしていけます。
外出すると気分転換になり、前へ進むきっかけとなることがあります。また、周囲に人がいる環境にも慣れることができるでしょう。
5-5. ボランティアなど地域のコミュニティに参加する
ボランティアなど地域のコミュニティに参加して、学校やご家庭の他にお子さんの居場所を作ってあげるのもおすすめです。
地域コミュニティはお金をかけずとも参加できるものも多く、有償ボランティアであれば謝礼を受け取れることもあります。
社会に居場所があることを実感したり、学校だけが全てではないと思えると、お子さん自身、抱えていた問題を俯瞰して見れるきっかけとなります。
お子さんが安心して過ごせる居場所づくりについては、次の記事でもお話ししているためご確認ください。
こちらもCHECK
-

-
不登校の子どもが学校へ行くきっかけとなる居場所づくり|コミュニティ探しなどの親ができること
この記事を読むのに必要な時間は約 30 分です。 「不登校の子どもが学校へ行くきっかけを作るためには何をすればいい?」 「コミュニティに参加したり、学校以外の居場所を作ることは再登校につながる?」 & ...
続きを見る
5-6. アルバイトをしてみる
お子さんが高校生で、アルバイトに興味を持っている場合には経験してみるのも良いでしょう。
1日などの短期で一度働いてみて、お金をもらうことで次のような気持ちがわくこともあります。
- 自分も社会に必要とされているんだ、社会の役に立つことが嬉しい
- 外に出るのは意外と大丈夫なことかもしれない
自己肯定感が育ち、物事の捉え方や考え方が変化するきっかけとなるかもしれません。
こちらもCHECK
-
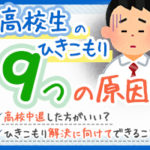
-
「高校生のひきこもり」9つの原因を解説!高校中退にならないために親がやるべき支援とやってはいけないNG行動
この記事を読むのに必要な時間は約 37 分です。 「高校生になってから子どもが自室にこもって出掛けなくなった」 「学校にも行かなくなってひきこもりになった子どもにどう対処するべき?」 そんな不安を抱え ...
続きを見る
6. ひきこもりを脱出するための思考方法
親御さんはずっと自宅にいるお子さんを見て心配になり、「どうにかして脱出させてあげたい」という思いを抱いているかと思います。
お子さんのことを大切に思うからこそ不安になり、思考が堂々巡りになってしまうこともあるかもしれません。
本章ではひきこもりを脱出するための、思考方法や大切な観点をお話しします。
6-1. ひきこもりになった「きっかけ」ではなく「根本原因」を考えてみる
お子さんがひきこもりになるきっかけは多岐に渡ります。
「あのときのあれが子どものひきこもりにつながったのかな…」と、ついつい過去を思い出しては不安にかられてしまうこともあるかもしれません。
ただ、どの出来事がきっかけだったのかは見分けるのが難しく、ほとんどの場合には複数の出来事が重なって絡み合い、ひきこもりとなることが多いです。
そしてそれらのきっかけを辿っていくと、お子さんの自己肯定感が下がっていたことや、親子関係に結びつくこともあります。
自己肯定感が低いと、誰かの何気ない発言に深く傷ついてしまったり、問題に直面したとき解決する自信がなかったりして、外に出ることに恐怖を感じてしまいます。
また、お子さんの自己肯定感は、正しいことはたくさん褒めてくれて、ダメなことはダメだと毅然とした態度で教えてくれる、信頼できて尊敬できる親から褒められることで育つため、親子関係も重要な事柄です。
正しい親子関係を構築すること、そのうえで子どもの自己肯定感を育てることを目指すと、ひきこもった根本原因を解決できるため、お子さんは主体的に前へ進めるようになります。
6-2. 子どもの気持ちやペースを受け入れながら前進する
親御さんはお子さんのためにも、なるべく早く解決してあげたい気持ちがあるかと思いますが、焦らずに前進することを意識しましょう。
根本原因にアプローチしてもいきなり脱出できるわけではなく、お子さんのペースで徐々に進んでいくものです。
なかなか前へ進めないときにも、親御さんに現状の自分や気持ちを受け入れてもらえることで、信頼できる親がいることを実感して気持ちが落ち着き、再び前へ進めます。
お子さんのペースを受け入れて、根本的な解決に向けて行動していきましょう。
7. ひきこもりから子どもが脱出するために親御さんができること
お子さんがひきこもりから脱出するためには、親御さんとの関わりによって自己肯定感を育てるプロセスが欠かせません。
お子さんの自己肯定感を育てるために親御さんができることを紹介します。
7-1. 専門機関の力を借りながら行動する
まずは専門機関の力を借りながら、親御さん自身もお子さんと良い関係性を築くために行動を始めましょう。
専門機関はひきこもりから脱出するためのノウハウを持っていますが、お子さんと一番長い時間を過ごすのは親御さんです。
だからこそ親御さんがお子さんに適切なサポートをすることが、ひきこもり脱出の大きな鍵となります。
お子さんが親御さんの言葉に素直に耳を傾けつつも、お子さん本人が自分で考えて判断して進んでいけるような関係性が理想です。
スダチでは、ひきこもりや不登校のお子さんを抱えている親御さんをサポートしています。
現状をヒアリングした上で、お子さんに必要な声かけを具体的にお伝えし、親子関係の改善を目指します。
熱心に取り組む親御さんが多くいるおかげで、2023年10月時点では600名以上のお子さんが再登校に成功しました。
ただ学校に行くだけでなく「親子の時間が楽しくなった」というお声もいただいています。
お子さんのサポート方法でお悩みの方は、無料オンライン相談でお話しできれば幸いです。
\無料相談を申し込む/
7-2. 頑張っていることを見つけてたくさん褒める
お子さんが頑張っていることを見つけて、たくさん褒めてあげましょう。
お子さんは自分の行動にいつも目を向けてくれている親御さんのことを信頼します。
信頼できる親御さんから、行動した過程を褒めてもらうことで、お子さんの自己肯定感がどんどん育ちます。
お子さんの自己肯定感が育ち、心の元気が回復するとお子さんは主体的にひきこもりを脱出していけるでしょう。
7-3. 正しい親子関係を築く
次のような正しい親子関係を築いていくことも大切です。
- 親子の立場が逆転していない
- 子どもが親の顔色を伺っていない
- 親が先回りして行動していない
- 子どもを放置していたり、無関心だったりする状況ではない
お子さんは、正しいことをたくさん褒めてくれて、間違ったことは感情的にならずに毅然とした態度で教えてくれる親のことを信頼します。
信頼できる親から褒められることで、お子さんの自己肯定感が育ちます。
信頼できる親の存在を感じることで、お子さんは安心して主体的に社会に中へ飛び込めるようになります。
また、親が先回りして行動するのではなく、お子さんが自ら行動して失敗を経験する環境も大切です。失敗から学ぶことで、社会の中で生きていく力がどんどん育ちます。
ひきこもりから脱出し、この先お子さんが社会の中で幸せに生きていけるよう、正しい親子関係を構築しましょう。
7-4. 家庭のルールを定めて生活習慣を整える
生活習慣はお子さんの健康と心の安定性に大きな影響があります。
夜ぐっすり眠ることで成長ホルモンが分泌され、お子さんの心と身体の調子を整えてくれるからです。
「夜22時には寝る」「ゲームは学校に行けた日だけ」などのルールを定めて、規則正しい生活習慣に導いてあげることが大切です。
とくにスマホやゲームなどのデジタル依存は、生活リズムの乱れを起こしやすいのでルールを定めておきましょう。
デジタル依存から抜け出すと家族の時間も増えて、お子さんの様子をより把握しやすくなります。
8. ひきこもりを脱出した体験談
ひきこもりから高認試験に合格して脱出した高校生の体験談です。
学校自体は嫌いではないものの、人間関係につらさを抱えて学校に行けなくなっていました。
このままの状態では高校の卒業が難しい状況で、今後の進路やキャリアを考える中で高認試験の受験を決意します。
自宅で勉強をして無事に高認試験に合格し、国立大学に進学。その後の就活でも大手企業も含めた数社から内定をもらい、今ではのびのびと働いておられます。
働いている今でも高校時代の方がつらかったと感じていて、それを乗り越えた経験が大きな自信になっています。
より詳しく体験談や高認試験について知りたい方は、次の記事もお読みいただけると幸いです。
こちらもCHECK
-

-
不登校から高認試験で引きこもり脱出!実際の経験者のエピソード
この記事を読むのに必要な時間は約 14 分です。 不登校のお子さんでも、高認試験を受験することで高校を卒業しなくても大学に進学することができます。 しかし誰もが受験する試験ではないので、どんなものなの ...
続きを見る
9. ひきこもりの脱出についてよくある質問
9-1. ひきこもりになったら何をするべきですか?脱出できる唯一の方法は?
自己肯定感を高めることがひきこもりから脱出するための方法です。
自己肯定感が十分に高くなっていれば、問題が起きた時、傷つくのではなく主体的に解決に向けて動き出せます。
自己肯定感を育てるためには、次の取り組みをしていきましょう。
- 外部機関に相談してみる
- 生活リズムを正す
- できることから取り組んで成功体験を積む
まずは外部機関に相談して、自分がどういう状況にいるのか、これからどうしていくのかを考えるきっかけにしましょう。
人と話すことで考え方の癖や取り組んだ方が良いことも見えてきます。
また、生活リズムを正すとそれ自体が成功体験になり、健康的で気持ちも前向きになっていきます。
興味が湧いたことがあれば、小さなことでもやってみて成功体験を積んでいくと自己肯定感が自然と育っていきます。
9-2. ひきこもりになる人の特徴は?
ひきこもりになりやすい人の特徴は次の通りです。
- 真面目で結果を出すことにこだわる頑張り屋な人
- 人目が気になって感情表現がうまくできない人
- 自己肯定感が低い人
結果を出すことを目指しすぎると結果が出せなかった時に、挫折を感じてしまいます。
頑張ること自体は素晴らしいのですが、結果が全てだという考えにならないように注意が必要です。
感情表現がうまくできない場合には、ストレスを溜め込むことで人と関わる元気がなくなってしまいます。
また、自己肯定感が低いがゆえに、結果を出そうとこだわったり、自己表現がうまくできなかったりするケースもあります。
9-3. 子どもがひきこもりで会話すらできない。どうしたらいい?
ひきこもりには専門的な支援が必要なため、まずは専門機関に相談しましょう。
その上で、ご家庭では正しい親子関係を築いていくことが大切です。
- お子さんの行動に目を向けて褒めたり、何気ない挨拶や会話を大切にする
- ダメなことについては毅然とした態度で接して声かけをしていく
上記を実施していただくことが大切です。
スダチでは、会話もままならなかったり、家庭内で暴力を振るっていたりしたお子さんの問題も解決してきました。
心理学と脳科学に裏打ちされたアプローチで、お子さんが必要としている親御さんとの関わりを具体的にお伝えします。
お子さんが受け取りやすい形で愛情を伝えることで、正しい親子関係を築き、お子さんが前に進めるように導きます。
2023年10月時点で600名以上の方が再登校に成功しました。
「何から始めたらいいかわからない」という方は、無料オンライン相談で今のお子さんの様子をお伺いできれば幸いです。
\無料相談を申し込む/
10. まとめ
ひきこもりは見守りだけで解決することはほとんどなく、親御さんが解決に向けて積極的に行動を起こす必要があります。
専門機関の力を借りながら親子関係を見直して、お子さんの自己肯定感を育てていきましょう。
自己肯定感が育つと、お子さんが自分からひきこもりを脱出するために前に進み始めます。
スダチでは、お子さんに伝わりやすい形で親御さんの愛情を伝えるサポートを実施しています。
お子さんが親御さんの愛情をしっかり受け取れるようになることで、自己肯定感が育ち親子関係もよくなっていきます。
すぐに実践できる具体的なアドバイスを実施しており、2023年10月時点で600名のお子さんが再登校に成功しました。
「子どもと話をするのも難しい…」
「どうやって関わったらいいかわからない。」
このような場合には、無料オンライン相談で一度お話しできたら幸いです。
\無料相談を申し込む/






