この記事を読むのに必要な時間は約 25 分です。
「子どもが学校を嫌だと言っているけど、転校したほうがいい?」
「転校すれば、不登校が解決するのだろうか?」
お子さんが不登校になっている親御さんの中には、このような疑問を持っている方も多いでしょう。
お子さんの不登校が長期化していると、子ども自身も学校に戻りにくいと感じていることが多いので、転校は解決策のひとつではあります。
しかし、転校すれば不登校は必ず解決するというわけではありません。
今回の記事では転校のメリットと転校先の選び方などを詳しく解説していきます。
【平均3週間で不登校解決プログラム】を展開する小川涼太郎監修のもと、お話しする内容は次のとおり。
記事を読むとわかること
- 転校すれば不登校は解決するのか
- 不登校の子どもが転校するメリット
- 転校先の学校の選び方
- 転校する場合の手続き方法
親御さんの不安や疑問の解決の糸口になれば幸いです。
スダチでは、不登校になったお子さんを平均3週間で再登校に導いています。
休み明けに学校に行きたくないと子どもが言いだした場合は、早めに対処しましょう。子どもが学校を休みたがっていることで悩んでいる親御さんは、ぜひ一度ご相談ください!
\無料相談を申し込む/
1. 転校すれば不登校は解決する?見極めるためのチェックポイント
不登校のお子さんを持つ親御さんは、一度は転校を考える人が多いです。
環境を変えることはお子さんにとってもよいことですが、少なからずリスクがつきものです。
ここでは、転校して不登校が解決するかを見極めるチェックポイントを紹介します。
1-1. 中学を転校するのは子どもの意志なのか考える
一番大切なことは、「転校」という選択肢が、お子さんの意志なのかという点です。
お子さんの不登校が続いていると、中学を転校するという選択肢が出てくることがあります。その際、やはり本人の意思が大切です。
お子さんによっては、
- 環境を新しく変えることに消極的で新しい学校に対して不安がある
- できれば元の学校で頑張ってみたいと思っている
- 仲のいい友達と離れてしまうことが嫌だと感じている
というように、転校自体に消極的なこともあります。
また、転校を促してくる親御さんに、プレッシャーを感じてしまっている子どももいます。
不登校が続いていると親御さんも不安になってしまうでしょう。
しかし、一番不安なのはお子さんであり、転校先で頑張らなければいけないのもお子さん自身です。
本人が「転校したい」という意思を持っているのかは非常に重要です。
お子さん自身が転校に消極的な場合は、転校しても不登校を解決できない場合が多いです。
1-2. 転校が本当に子どものためになるのか考える
転校することがお子さんのためになるのかも考えてみましょう。
たとえば次のように明らかに学校に問題があるときは、転校を選択した方が良い場合もあります。
- いじめを受けている
- 学校の先生とどうしても折り合いが悪い
このように、今の学校だから起きてしまった不登校であれば、中学を転校することで不登校を改善できる可能性があります。
しかし、「人間関係をうまく築けない」「勉強についていけない」といったお子さん側に問題がある場合は、転校することで不登校となったきっかけを解決できるわけではありません。そのためまた不登校になってしまう可能性もあります。
上記の場合お子さんの現状の問題を解決することで、今の学校で再登校できる可能性が高いです。
お子さんが不登校になったきっかけを見極めて、転校することがお子さんのためになるのかを考えましょう。
1-3. 中学を転校しても不登校がすぐに解決するわけではないことを知る
不登校の根本的な原因を解決していない場合、中学を転校しても不登校がすぐに解決するわけではありません。
不登校になってしまったお子さんは、自己肯定感が下がり心身ともに疲れ切っていて、心の元気がなくなっている状態です。
自己肯定感が下がり、心の元気が不足した状態だと、転校先で新しい生活を頑張る力がありません。
新しい環境に入る自信がなく、朝起きられなかったり、学校に行ったり休んだりを繰り返す可能性もあります。
そのため、不登校の根本的な原因がわからない状況のときには、転校したからといって不登校をすぐに解決できるわけではない点も踏まえ、転校を検討してみてください。
編入や転校についての詳しい解説は、こちらの記事で行っています。
こちらもCHECK
-
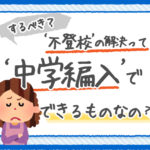
-
中学の不登校は編入もアリ?【学校を変えるだけが解決策ではない!】
この記事を読むのに必要な時間は約 21 分です。 子どもが不登校になると、「編入や転校・転入をして学校を変えるべき?」と思いますよね。 この記事では 中学の不登校は、編入や転校・転入すれば解決する? ...
続きを見る
1-4. 転校以外の選択肢も考える
中学生の不登校の場合、学校を進級するのに出席日数は関係ありません。高校進学においても、私立の全日制の学校であれば出席日数は加味されないことが多いです。
そのため、不登校の状況でも勉強し続けていればお子さんの学習レベルに合った高校と大学に進むことが可能です。
環境を変えることで改善することもありますが、環境が変わるとお子さんの負担が増えることも事実です。
そのため、転校せずに今の学校に残り、そして再登校を目指す選択肢も考えてみましょう。
「不登校が長期化しているため、再登校などできるはずがない」そのようなお悩みがある場合は、スダチにご相談ください。
スダチは、不登校が長期化したお子さんたちの不登校の根本原因を解決し、再登校に導いてきた実績があります。みなさん平均3週間で再登校しているため、お子さんも大丈夫です。
お子さんの人生の大切な岐路だからこそ、まずは相談して不安を解決しましょう!
無料オンラインセミナー動画をご視聴いただいた方に、無料相談を実施中です。オンライン相談であり1対1で顔出しも不要です。ぜひ一度現状のお子さんの様子をお聞かせください。
\無料相談を申し込む/
2. 中学生の不登校は転校で解決することもある!転校するメリット
チェックポイントでは、中学校を転校する際のデメリットについても触れさせていただきました。ここでは、中学を転校することのメリットについて詳しく解説していきます。
2-1. 不登校の原因から離れることができる
転校する場合の大きなメリットは、不登校になったきっかけから離れられることです。
- 人間関係のいざこざが原因で不登校になってしまった
- いじめを受けて不登校になってしまった
- 学校の先生と上手くいかずに不登校になってしまった
学校を変えることで、お子さんが不登校となったきっかけから離れることができます。
お子さんがストレスを感じることがない新しい学校は、お子さんにとって再登校しやすいかもしれません。
ただし、新しい学校でも同じようにストレスを感じることが発生する場合もある点は考慮しておきましょう。
2-2. 新たな環境で再スタートできる
不登校が続いているお子さんは、元の学校に戻りにくいと感じていることがあります。
- 長期間休んでしまったから戻りにくい
- 学校に行くと先生や友達に何か言われるのではないか
- 学年の途中で戻るのは少し不安
学校に行きたいのに戻りにくいと感じている場合は、転校することで新たな環境で再スタートできます。
特に不登校の根本原因を解決し、お子さんの自己肯定感が育った状況でお子さん自身が「新しい学校で再スタートしたい」と望む場合には、転校を視野に入れることがおすすめです。
2-3. 転校した中学で新しい刺激を得られる
転校先の新しい中学で何か刺激を得られる可能性もあります。
不登校になったお子さんは、自己肯定感が低い状況にあり「私なんて何をしてもダメなんだ」という気持ちがあります。
そのため、何か自分の興味のあることに熱中して取り組み、達成感や自信を得る機会がない状況です。
新しい中学で、お子さんが興味のある部活と出会ったり、新しい友だちの影響で何か興味のあることが見つかったりする可能性もあります。
興味のあることと出会い一生懸命に取り組むことで、達成感を感じ、自己肯定感が育つきっかけとなるかもしれません。
3. 中学を転校する場合の転校先の選び方は3つ
中学を転校する場合、転校先の学校をきちんと選ぶことも非常に重要です。
お子さんの再スタートのための転校なので、転校した後にしっかり通えるように、お子さんにあった転校先を選びましょう。
ここでは、転校先の選び方を3つご紹介します。
3-1. 転校先は公立中学か私立中学かで選ぶ
転校先を公立中学、私立中学にするかを選ぶことが大切です。
ここでは、公立中学と私立中学の違いについて詳しく紹介します。
▼公立中学と私立中学の違い
| 公立中学 | 私立中学 | |
| 学習面 | 公立中は一定のカリキュラムが決まっているので、学習の遅れなどが出にくいです。 | 私立中学は中高一貫校が多いため、大学受験に向けてカリキュラムを組んでいる場合もあります。
例えば、中学の3年間と高校の3年間で学ぶ内容を5年で終えるようにして、残りの1年は大学受験に向けた授業を行う場合もあります。 そのためカリキュラムにギャップが生じるかもしれません。 |
| 不登校のサポート | 公立中学の場合、学校の先生は積極的に不登校の対応をしてくれないことが多いです。
転校先に不登校生徒の数や取り組みを確認しましょう。 |
不登校サポートが充実している学校が多いです。学校に来られない子に対しても丁寧にサポートしてくれます。 |
| 進学先 | 公立中学の場合、高校受験をすることが必要になります。 | 私立中学は中高一貫で高校まで通うことができます。
簡単な内部進学試験に合格すれば、高校入学も可能です。本人が望めば別の高校を目指すこともできます。 |
| 転入試験 | なし | 転入試験を合格する必要があります。 |
公立中学は、転校のハードルが低いことがメリットですが、不登校生徒への対応はあまり積極的ではないというデメリットがあります。
私立中学は、不登校の生徒への対応がしっかりしている学校が多いですが、転入試験があり、それに合格しないと転校できないというデメリットがあります。
3-2. 通学距離や送迎などができるかで選ぶ
お子さんが卒業まで無理なく通える環境であるかも重要です。
中学への通学距離が長いと、お子さんにとって負担になってしまいます。
送迎するのか、お子さんが一人で通うのか、家族でしっかり話し合って学校を決めるようにしましょう。
3-3. 転校先の候補へ足を運び選ぶ
公立中学でも、私立中学でも、転校先をある程度絞り込んだら実際に学校に足を運んでみてください。
子どもが新しく通う学校であるからこそ、学校の雰囲気、先生の雰囲気や対応などを実際に見てみることが大切です。
実際に足を運ぶことで、お子さん自身学校の雰囲気が合うかどうかを確かめることができます。
また、先生と事前に話すこともできるため、現状のお子さんの様子を伝えておくこともできます。
4. 中学を転校する場合の手続きの流れと必要な条件【中学転校の仕方】
ここでは、中学校を転校するときの手続きについて詳しく紹介します。
4-1.【転校の手続き】私立中学から公立中学への転校の流れ
私立中学から公立中学へ転校する場合の手続きは、以下の通りです。
- 現在通っている中学校から「在学証明書」を貰う
- 市町村にある教育委員会に連絡し、「転入学通知書」を受け取る
- 転校先の中学に「転入学通知書」「在学証明書」を提出する
ちなみに、公立中学から公立中学への転校も、上記と手続きは同じです。
教育委員会に相談すれば、引っ越しをしなくても学区外の中学校に転校することができます。
4-2.【転校の手続き】公立中学から私立中学への転校の流れ
公立中学から私立中学へ転校するときの手続きについて詳しく紹介します。
- 転校先の学校に連絡し、転校可能か確認する
- 転校先の学校に転校したい旨を伝える
- 試験を受けて、合格する
- 合格後に現在通っている中学校へ連絡
- 「在学証明書」を貰う
- 転校先の学校に書類を提出する
私立中学への転校の場合は、試験に合格する必要があります。
学校のレベルによっては難しいテストを受けることになる場合もあるので、しっかりと準備しましょう。
5. 中学の転校を考えている親御さんのよくある心配事
ここでは、中学の転校を考えている親御さんから、よくある質問について回答していきます。
5-1. 不登校の中学生が転校しないで学び続ける方法は?
転校だけが選択肢ではありません。転校せずにお子さんが学び続けることは可能です。
転校しないまま学び続ける方法としては、以下の通りです。
- 自宅学習
- 通信制中学
- 高校進学支援サポート
- 海外留学
- ホームスクーリング
- フリースクール
通信制中学や高校進学支援サポートは、自宅に居ながら学習のサポートをしてくれます。お子さんが外に出るのを嫌がる場合は、家庭教師などを利用して自宅学習を進めることも可能です。
ホームスクーリング、フリースクールという選択肢もありますが、スダチではおすすめしておりません。
理由は、ホームスクーリングやフリースクールは学習のカリキュラムが決まっておらず、「したいことをする」という趣旨だからです。
通常の学校と大きく仕様が異なることから、フリースクールに慣れてしまうと通常クラスへの再登校が難しくなってしまいます。
高校進学を考えている場合は、自宅学習・通信制中学・高校進学支援サポートなどを利用するようにしましょう。
また学校へ行くのと同様の生活リズムで勉強に取り組むことがおすすめです。
5-2. 中学校の転校に適したタイミングは?中3でも転校してもいいの?
中学の転校に適しているタイミングは、長期休み明けです。
夏休みや春休みといった長期休み明けのタイミングは、不登校が解決しやすいタイミングでもあります。
長期休み明けの子どもたちも新鮮な気持ちで学校に戻ってくるので、その際に転校すると、受け入れられやすいです。
ただし、長期休み中は学校の先生も出勤が少ない場合があるので、長期休み前から転校の手続きなどの対応はしておくべきです。
中学3年生での転校については、転校自体に問題はありません。
しかし、受験を控える時期のため、転校先での学習のズレによってお子さんに負担があったり、成績表の評価に影響したりするため慎重に動くようにしましょう。
5-3. 中学校の転校で馴染めない時は?
中学を転校することで、環境を変えることができますが、逆に転校先の学校に馴染めないというお子さんも少なからずいます。
新しい学校に馴染めず再度不登校になってしまう状況をつくらないためにも、転校前に不登校となった根本原因を解決しておくことが大切です。
お子さんが不登校となるときお子さんの自己肯定感が下がり切っていることがあるため、次のことを意識してお子さんの自己肯定感を育てましょう。
- 子さんが取り組んだことを褒める
- 結果ではなく、過程に目を向けて褒める
- 正しいことは褒めて、ダメなことはダメと毅然とした態度で教える
ダメなことはダメだと伝え、正しいときにはたくさん褒めて正しい親子関係を築いていると、お子さんは親御さんから褒められたときに自己肯定感がどんどん育ちます。
また心の元気が回復した状態で転校したときにも、環境に慣れるまで時間がかかる場合もあります。
日々のお子さんの様子をよく見てあげて、お子さんの話には耳を傾け意見を受け入れてあげましょう。
お子さんが安心して前へ進めるようサポートしてあげてください。
5-4. 中学校は学区外への転校も可能?
公立中学への転校は、学区外からでも可能です。
事情がある場合は学校へ相談すれば、引っ越しせずに学区外から転校できます。
しかし、学区外の中学に通うとなると、どうしても距離の問題が出てしまうので、送迎などの方法を考えるようにしましょう。
5-5. 中学転校でいじめは解決する?
もし、いじめが原因で不登校になってしまった場合、転校することで不登校の原因と離れることができるため、いじめ自体は解決します。
しかし、いじめを受けていたお子さんは、心に深い傷を負っており、自己肯定感も下がり切ってしまっています。
その状態で転校して新しい場所で再スタートしても、人間関係が上手く築けなかったり、自己肯定感が低いことでまたいじめのターゲットにされてしまうケースもあります。
いじめられているから、即転校という考え方は危険です。
まずはお子さんが根本的な原因と向き合って、解決することが大切。
親御さんとの会話を通して自己肯定感を育てることで、お子さんはどんなときでも毅然とした態度で立ち回れるようになります。
いじめが原因で不登校になってしまったお子さんに対しての、対応方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
こちらもCHECK
-
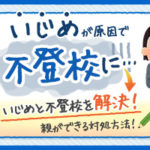
-
いじめが原因で不登校に!不登校を解決するために親ができる対処方法
この記事を読むのに必要な時間は約 34 分です。 子どもがいじめられて不登校になってしまった…どう接したらいいの? いじめと不登校を解決する方法を知りたい。 お子さんがいじめから不登校に ...
続きを見る
6. まとめ
今回は、不登校の子どもが中学校を転校する場合のメリットやチェックポイント、さらには手続きについて解説しました。
転校はお子さんにとっても、家族にとっても負担があるものです。
転校することで不登校を解決できる場合もありますが、転校だけでは不登校が解決できないこともあります。
お子さんが本当に転校したいのかを一番に考え、親子でしっかりと話し合ってください。
スダチは、日々多くの不登校のお子さんを支援しています。
みなさん平均3週間で現在通っている中学校へ再登校しています。不登校のお子さんのことでお悩みの場合は一度ご相談ください!
脳科学に基づいた方法で不登校の根本原因を解決いたします。
現在、無料オンラインセミナー動画をご視聴いただいた方に、無料相談を実施中です。オンライン相談で、1対1で顔出しも不要です。ぜひ一度現状のお子さんの様子をお聞かせください!
\無料相談を申し込む/






