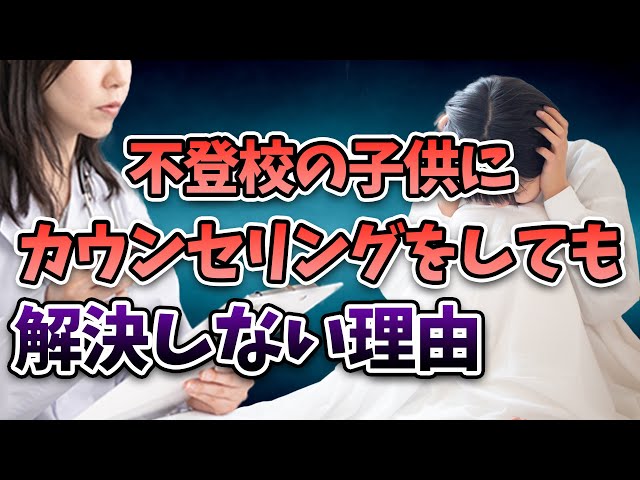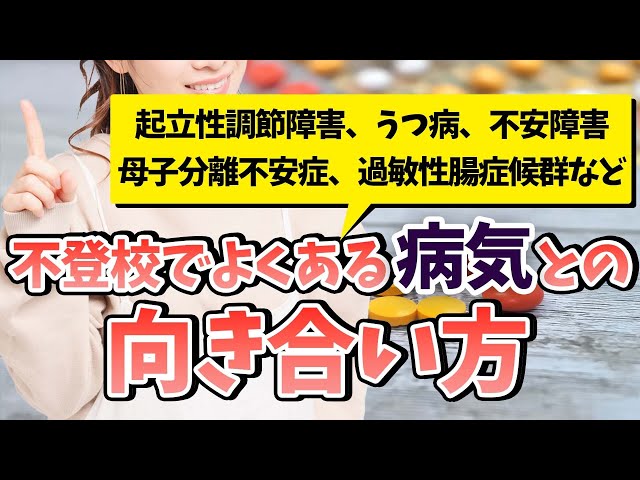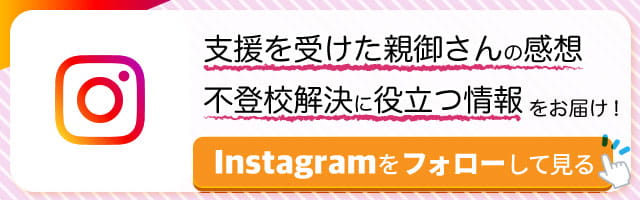この記事を読むのに必要な時間は約 32 分です。
お悩みポイント
- 子どもが不登校になり、今後どうしたらいいのか…
- “わからない”から、誰かに相談したい
- 相談したいけれど、どこに相談すればいいのかわからない
子どもが不登校になったとき、相談先に悩む親御さんは少なくありません。
この記事を書いている私は、小〜中学生の間、学校に通えませんでした。
そのため、自分の親が「不登校をどこに相談するのか」で悩んでいた姿を見ています。
この記事が不登校の相談先に頭を抱えている、あなたのお役に立てば幸いです。
記事を読むとわかること
- 不登校の相談先「公的機関」と「民間」
- 不登校の相談先をきめるための3つのポイント
記事を読むと、不登校の解決にあたり子どもが他者と関わるのがいいのか、第三者介入不要がいいのかの比較検討ができます。
さらに、どのような相談先が子どもに適しているのかを考えやすくなりますよ。
1.不登校の相談はどこにすればいいの?
不登校の相談先は、主に次の2つに分けられます。
- 公的機関(学校や教育相談所(教育相談室)や教育支援センター(適応指導教室)など)
- 民間(フリースクール・カウンセリング施設・医療機関(心療内科や精神科)など)
公的機関の特徴は、学校との連携が強く、相談からサポートまで無料で受けられる点です。
民間は、本格的なサポートを受けるためには料金がかかりますが、公的とは異なる視点・手法での支援が受けられます。
また、子どもと相談先を会わせる必要のない、第三者介入不要の不登校解決法があるのも民間の特徴です。
1-1.不登校の相談先:公的機関
公的機関は、次のように細分化できます。
- 学校(担任・養護教論やスクールカウンセラー)
- 教育相談所(教育相談室)や教育支援センター(適応指導教室)
公的機関は、教育現場との距離感が近いのが特徴です。
学校は相談先に担任以外の第三者を含めることで別の視点が加わるほか、学校復帰の足がかりをつくる際のサポートを受けやすくなります。
教育相談所などでは、単純に不登校の相談に限らず、子育て全般の相談を受け付けています。
1-1-1.不登校の相談先:学校(担任・養護教論やスクールカウンセラー)
不登校の相談先に学校、担任の先生は外せません。
あなたと担任の先生で次のステップを踏むことで、再登校へつながります。
- これまでの学校生活と家での様子をふり返る
- 現状を再確認する
- 再登校へのステップ(保健室登校・相談室登校)を決める
不登校の初期から学校との連携がスムーズなら、保健室登校・相談室登校の要望も通りやすいでしょう。
結果、学校へ通わない期間も短くできます。
すでに不登校となって日が経っていても、改めて学校へ相談してみてください。
教育相談所(教育相談室)や教育支援センター(適応指導教室)などへの紹介、取り継ぎを受けるきっかけが生まれます。
もし、担任の先生に技量不足などを感じるのであれば、次のような第三者を介入させてください。
- 学年主任
- 養護教論
- スクールカンセラー
とくに、養護教論やスクールカウンセラーへの相談、情報共有はおすすめです。
保健室登校・相談室登校の持ちかけがしやすくなります。
1-1-2.不登校の相談先:教育相談所(教育相談室)や教育支援センター(適応指導教室)
以下の2つの機関は、主に教育委委員会が設置している相談先です。
不登校に限らず、教育全般の相談を数多く受けています。
- 教育相談所(教育相談室)
- 教育支援センター(適応指導教室)
教育相談所(教育相談室)は、相談のみの対応です。
教育支援センター(適応指導教室)は次のことを行っています。
- 教育相談
- 不登校の子どもの学校復帰・社会的自立の手助け
ちなみに、通所決定後に手続きをすることで、教育支援センター(適応指導教室)の出席=在籍校への出席にしてもらえます。さらに、教育支援センター(適応指導教室)から学校側へ、通級や支援状況の定期連絡も行われます。
教育相談所(教育相談室)・支援センター(適応指導教室)の設置状況は、各自治体によって様々です。
手はじめに、住んでいる自治体のホームページを見てみましょう。
「子育て・教育」のページから、不登校をはじめとする教育にまつわる相談先をチェックできます。
以下からも教育支援センターを探せます。
文部科学省:都道府県・政令指定都市・中核市教育センター等
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kenkyu/1225078.htm
1-2.不登校の相談先:民間
民間は、以下のように分かれます。
- フリースクールなど
- カウンセリング施設
- 医療機関(心療内科や精神科)
サポート内容や方法は団体によって様々です。
子どもが特定の場所に通うものもあれば、「平均3週間で不登校解決プログラム」のようにお子さんと第三者を会わせずに不登校支援を行うところもあります。
公的機関とは異なりサポートがはじまると料金はかかりますが、子どもや親御さん1人ひとりに合う濃いサポートを受けられるのが民間のメリット。
相談は無料で受けられるため、1度は気軽に相談してみることをおすすめします。
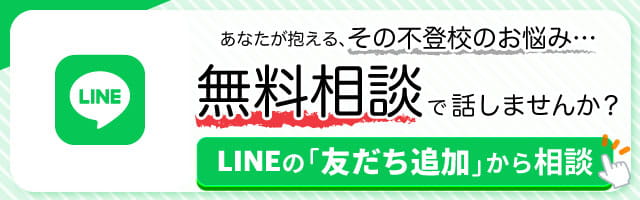
1-2-1.不登校の相談先:フリースクールなど
学校に行けない、学校には行かないと決めた子どもが集う場所がフリースクールです。
子どもへの支援としては、教育支援センター(適応指導教室)と同じように、学習支援や体験活動を行っています。
もちろん、親御さんからの相談も受け付けており、文部科学省が平成27年に行ったアンケート調査では、相談やカウンセリングを実施している割合は90.9%。
家庭への訪問は50.9%にものぼります。
多くのフリースクールで不登校の相談を受けているため、1度は連絡をしてみるとよいでしょう。
子どもが通うフリースクールと第三者介入不要の支援先を比べておくと、サポート内容を比較できるため、あなたとお子さんへの負担が少ない支援先を選びやすくなります。
1-2-2.不登校の相談先:カウンセリング施設
カウンセリング施設では、心の専門家が聴き手となり、あなたが抱える悩みや不安を聴いてくれます。
ただし、あくまでもカウンセリングは、話し手自身が感情や思考を外に出す場所です。
心のもやもやを話しつつ不登校解決のアドバイスがほしいなら、不登校に強いカウンセリング施設を探しましょう。
不登校を専門にしているカウンセリング施設では、初回のみ親御さんがカウンセリングを受け、次回以降は子どもがカウンセリングを受けるのが基本。
もし、子どもがカウンセリングを受けられない場合は、親御さんが施設へ赴き、カウンセラーから生活上のアドバイスを受けるかたちになります。
※YouTubeサイトへ移動します
こちらもCHECK
-
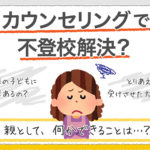
-
高校生の不登校はカウンセリングで解決できるか知りたい親御さんへ
この記事を読むのに必要な時間は約 29 分です。 疑問&お悩み ・不登校や引きこもりにカウンセリングって効きそうだけど… ・カウンセリングって話を聴いてくれるだけ? ・カウンセラーとのやりとりには、な ...
続きを見る
カウンセリングのメリットや流れなどについて知りたい方は、次の記事が参考になります。
こちらもCHECK
-
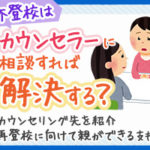
-
不登校を支援するカウンセラーに相談すれば再登校できる?カウンセリングのメリットや流れ、子どもが嫌がる時の対処法を紹介
この記事を読むのに必要な時間は約 27 分です。 「不登校専門のカウンセラーによるカウンセリングはどこで受けられるの?」 「カウンセリングを受けることで、不登校解決につながる?」 お子さんが不登校にな ...
続きを見る
1-2-3.不登校の相談先:医療機関(心療内科や精神科)
不登校は、子どもの心だけでなく体調にも何かしらの影響を及ぼします。
また、体調不良からメンタルに影を落としている場合もあるため、様子が気になるのであれば医療機関を受診するのもいいでしょう。
事実、不登校児童が病院や診療所に通院しているケースはよくあることです。
文部科学省の調査では、学校内外で不登校の相談・指導を受けた人の12.1%が医療機関にかかっています。
数値上は小さく見えますが、教育支援センター(適応指導教室)への相談割合(12.0%)とほぼ同等です。
医療機関に相談する際は、受診の度に医師からの診察とカウンセラーによるカウンセリングの両方を受けられるとベスト。
場合によってはお薬によって体調の改善や悪化を予防しつつ、話を聴いてもらうことで感情との向き合い方を学べます。
こちらもCHECK
-

-
中学生の不登校 上手に病院と付き合うために…
この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です。 1. 中学生の不登校は病気? 病院に行くべきか? お子さんが不登校なのは病気のせいだと思っていませんか? 病院に行くべきかお悩みの親御さ ...
続きを見る
また、不登校に限らずお子さんの悩みについて幅広く相談できる窓口もあります。
次の記事では子育ての悩みやお子さんの学校での悩みを相談できるところを紹介しているので、こちらも参考にしていただけると幸いです。
こちらもCHECK
-

-
子どもの悩み相談はどこにすればいい?親子で利用できる公的機関や民間団体の相談窓口【ひとりで悩まず相談が大切】
この記事を読むのに必要な時間は約 25 分です。 「不登校の子どもが、学校の悩みなどを相談できる場所はある?」 「今子どもが抱えている悩みに適した相談先を知りたい。」 お子さんが不登校に ...
続きを見る
2.不登校の相談先を決めるための3つのポイント
不登校の相談先がいくつかあることは、知っていただけたかと思います。
ポイント
- 公的機関(学校や教育相談所(教育相談室)や教育支援センター(適応指導教室)など)
- 民間(フリースクール・カウンセリング施設・医療機関(心療内科や精神科)など)
そして、1つの疑問も浮かんできたことでしょう。
「じゃあ、どうやって相談先を決めたらいいの?」という疑問です。
この章では、不登校の相談先を決めるための3つのポイントについて、1つずつ答えていきます。
- 子どもの復学意思と生活状況
- 不登校の“なに”を改善してあげたい?
- 相談先と子どもをつなぐ橋渡し役になれるか
ムリをして、はじめから相談先を1つに絞ろうとしないでくださいね。
1つに決めようとすると、視野が狭くなってしまいます。
まずは、お子さんの状況確認をしつつ、1つずつ検討していきましょう。
2-1.子どもの復学意思と生活状況
あなたが実際に不登校の相談をする前に、あらかじめ次の2つを把握しておきましょう。
・子どもに学校に戻りたい気持ちがあるのか
・今の生活状況は従来通りか昼夜逆転しているか
大まかにでも子どもの意思傾向がわかっていると、子どもと相談先のミスマッチなどを事前に防げます。
現状把握のポイントは、子どもから「学校には絶対に戻らない!戻りたくない!」と言われてショックだとしても、観察する視点を持つことです。
「あぁ、今のこの子は、こう思っているんだな」と“知る”心構えでいると、少しラクに聞き入れられます。
また、不登校は身体の不調から生じることもあるため、生活状況も確認しておきましょう。
とくに、朝の起床が困難になる起立性調節障害は、不登校が起きやすい思春期の時期に発生しやすいです。
朝に起きられない、だるい、頭痛がするという症状が頻繁に起きることで日常生活が苦しくなり、不登校や引きこもりに発展するケースも。
こちらもCHECK
-
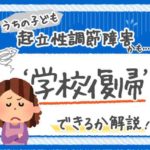
-
不登校の起立性調節障害は心配不要⁉︎改善のポイントは心身のケア
この記事を読むのに必要な時間は約 28 分です。 不登校について調べていると、多くの子どもが「朝に起きられないこと」が挙げられます。 さらに、朝起きられないことを深堀した結果、「起立性調節障害」に辿り ...
続きを見る
※YouTubeサイトへ移動します
2-2.不登校の“なに”を改善してあげたい?
あなたが、「子どもの不登校を解決してあげたい」と思っていることは重々承知です。
しかし、ただ単純に「不登校を解決したい」だと漠然で、どういったアプローチが必要なのかが少々わかりにくい状態です。
少し難しいところではありますが、今の段階で子どもの“なに”を改善してあげたいのかが見えてくると、あなたが今後、実際に相談する際にも状況や展望などを伝えやすくなります。
例えば
- 子どもの具合が悪そう…→まずは医療機関にかかる
- 無気力や「自分はダメだ」と思いが強そう→…カウンセリングや認知行動療法を受けられる施設
- 1人で過ごしているから居場所が必要かも…→教育支援センター(適応指導教室)やフリースクールを検討する
もちろん、相談内容は同じでも、相談先によって返答もサポート方法も違うことがあります。
場合によっては「手助けするべき点がズレていた!」ということもあるでしょう。
相談を重ねることで、どこから手をつけるのが子どもにとっていいのか、どんな方法がベターなのかが見えてきます。
こちらもCHECK
-
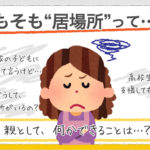
-
【高校生も求めている】不登校の子どもに必要な居場所とは?
この記事を読むのに必要な時間は約 30 分です。 疑問&お悩み ・「不登校の子どもには居場所が必要」と聞くけど、居場所ってなに?どういうこと? ・居場所の必要性が、いまいちピンとこない…。   ...
続きを見る
2-3.相談先と子どもをつなぐ橋渡し役になれるか
橋渡し役をできるかどうかは、不登校の相談先を決めるにあたって極めて重要なポイントです。
実際にあなたが不登校の相談をして「ここなら、大丈夫かもしれない」と思っても、1つハードルが待ち構えています。
ハードルとは、相談先と子どもをつなぐ橋渡し役になれるか。
つまり、相談先をお子さんに紹介してお子さんが第三者と対面する場面まで結びつけられるかです。
基本的に「不登校を解決したい」と思い、何かしらのアクションをとるのは、子ども本人ではなく、あなたのような親御さんです。
このため、必然的に相談先とお子さんをつなぐ必要が生まれ、あなたは相談先と子どもの橋渡しをしなければなりません。
また、多くの不登校支援では、次の2つが前提として挙げられます。
- 子どもが外に出られる
- 子どもが、家族以外の第三者の前に顔を出せる
例えば、公的機関の教育支援センター(適応指導教室)や民間のフリースクールやカウンセラーも、子どもが他者の前に出られる状態でないと、充分なサポートを受けるのは困難でしょう。
しっかりとした不登校支援を受けるためには、子どもと相談先の橋渡し役は避けられません。
橋渡しの際は、子どもの状態や相談先の方針、支援方法などを念頭においたうえで慎重に行う必要があります。
お子さんと親御さんの両方が相談できる窓口を利用する場合には、橋渡し役をする必要がなくなります。
高校生の不登校について、お子さんと親御さんの両方が相談できる窓口については、次の記事で確認できます。
こちらもCHECK
-

-
高校生の不登校に関する悩みを相談できる窓口一覧を紹介|不登校を根本解決する方法
この記事を読むのに必要な時間は約 31 分です。 「高校生の子どもが不登校になってしまった…どのような機関に相談をすればよい?」 お子さんが不登校になってしまったとき、お子さんが気持ちを ...
続きを見る
2-2-3.橋渡しがキビしいなら「第三者介入不要」の支援先も検討する
もしも、すでにお子さんが引きこもりであったり、家族以外との会話を拒む状態であれば、橋渡し役を担うのは、とても難しいことに感じるでしょう。実際に、お子さんと相談先をつなげるのは至難の技です。
無気力状態であったり、わずかな復学意思を持っている場合でも、子ども本人が行動に移せないジレンマも抱えているのは明らか。この状態で無理に相談先へ連れて行こうとすれば、親子関係がギクシャクする可能性が跳ね上がります。
子どもを思っての行動が裏目に出てしまうなど、親御さんにが望むことではないはず。
子どもが部屋に閉じこもっている、家族以外と接するのが難しいなら、第三者介入不要の「3週間で不登校解決プログラム」などを相談先に検討するといいでしょう。
既存の支援先と比較ができ、お子さんに合う不登校解決策が見つかりやすくなります。
スダチ(旧逸高等学院)など、第三者を介入しない不登校支援は、子どもに相談先を紹介する必要もなければ外へ連れ出す必要もありません。
あなたが橋渡し役をしなくていいため、子どもにも余計なストレスを与えずに済みます。
試しに無料セミナーを受けて相談することで悩みや不安といったモヤモヤがスッキリし、ゆとりを持ってお子さんの不登校解決に取り組めますよ。
こちらもCHECK
-

-
【不登校の中学生】相談先選びで押さえておくべき3つのポイント
この記事を読むのに必要な時間は約 31 分です。 中学生のお子さんが不登校になると、子どもが思春期あるため、親の考えのみで相談に行って良いのか悩みますよね。 この記事は、次のような悩みを持つ、中学生で ...
続きを見る
3.まとめ:不登校の相談先は【公的機関と民間】さらに分かれている
不登校の主な相談先は次のとおりです。
公的機関
- 学校(担任・養護教論やスクールカウンセラー)
- 教育相談所(教育相談室)や教育支援センター(適応指導教室)
公的機関は、比較的学校との距離感が近いのが特徴。相談から支援まで無料で受けられます。
民間
- フリースクール
- カウンセリング施設
- 医療機関(心療内科や精神科)
民間の場合、料金がかかりますが、公的機関にはない視点からサポートを受けられます。
不登校の相談先を決めるための3つのポイントは以下のとおり。
- 子どもの復学意思と生活状況の確認
現段階の状況を確認しておくことで、相談先との相性や方向性のすり合わせがしやすくなる。
- 不登校の“なに”を改善してあげたいのかを考える
子どもに対して、どういった面から不登校解決のアプローチをしていくのかが見えやすくなる。
- 相談先と子どもをつなぐ橋渡し役になれるかを充分に考える
従来の不登校支援では、親であるあなたが相談先に赴いたあと、子どもと相談先を結びつける必要がある。
橋渡しをしている間、多少なりとも子どもが自発的に行動できそうか様子をみること。
不登校の相談先は、はじめから1ヶ所に決めず、数ヶ所から検討することをおすすめします。
その際は、教育支援センター(適応指導教室)やフリースクールのような第三者が介入する支援先、「平均3週間で不登校解決プログラム」のように第三者が介入しない支援先の両方を検討しましょう。
方針やサポート内容を比べることで、より子どもの状況に合った不登校解決法を見つけられます。
4.追伸:早い不登校解決を目指すなら無料相談からはじめましょう
不登校の相談は、早いに越したことはありません。
というのも、不登校は時間が経つほどに、解決に時間がかかるからです。
お子さんの不登校を相談をするのは、あなたにとって勇気のいることかもしれませんね。
私たちは、これまでにあなたと同じように悩んでいる方々から相談を受け、不登校の解決にあたってきました。
2021年の年間再登校人数は109人にのぼり、なかには引きこもりだった方もいます。
お子さんの不登校への一歩は、まずはあなたが行動することです。
お悩みや不安がある方は、以下からLineにてご相談ください。
お子さんの不登校を解決につなげるため、折り返しご連絡いたします。
また、不登校を平均3週間で解決に導くための『無料オンラインセミナー』も随時開催しています。
お子さんの不登校に悩んでいるあなたのサポートができればと思っていますので、ぜひお申し込みください。