この記事を読むのに必要な時間は約 33 分です。
「高校生の子どもが不登校になってしまった…どのような機関に相談をすればよい?」
お子さんが不登校になってしまったとき、お子さんが気持ちを相談できる場所だけでなく、親御さんご自身もこの先どうすればよいのかを相談できる場所を探していらっしゃるのではないでしょうか?
本記事では、高校生の不登校について相談できる窓口を5つ紹介します。
親御さん、お子さん共に相談できる機関をご紹介しておりますので、参考にしていただけましたら幸いです。
平均3週間で再登校に導くサービスを提供する小川涼太郎監修のもと、お話しする内容は次のとおりです。
記事を読むとわかること
- 高校生の不登校について相談する前に確認すべきこと
- 高校生の不登校の相談ができる窓口5つ
- 高校生のお子さんの不登校を解決するために親御さんができること
不登校の相談先に悩まれている方のお役に立てば幸いです。
スダチでは、不登校のお子さんを抱えている親御さんの相談に乗り、2023年6月時点で500名以上のお子さんを再登校に導いてきました。
脳科学に基づいたアプローチによって、お子さんが不登校となった根本的な原因を解決しております。
1対1で顔出し不要のオンライン無料相談を実施しておりますので、お子さんの現状をお伺いできれば幸いです。
\無料相談を申し込む/
1. 不登校の高校生に関する悩みを相談する際に確認すべきこと|相談窓口・カウンセリング先の探し方・選定方法
1-1. 子どもだけでなく親も積極的に相談窓口に頼る
親御さんの中には、お子さんを対象としたカウンセリング窓口を探している方もいらっしゃるかもしれません。
不登校となったお子さん本人が悩みを解決しない限り、前へ進めないと考えていらっしゃるからこそだと存じます。
不登校の相談は次の3パターンが考えられます。
- 親御さんが相談するケース
- お子さんが相談するケース
- 親子で相談するケース
お子さんをつらい気持ちから救ってあげたいという場合には、お子さんだけカウンセリングを受けるのではなく、親御さんも積極的に相談することが大切です。
お子さんが自分で現状を変えられない状態にあるからこそ、不登校になっており、解決には親御さんの協力が欠かせません。
お子さんと接することができる時間は親御さんが1番多く、お子さんへの接し方を変えると、お子さんをつらい気持ちから救い、不登校を解決していけるようになります。
外部に相談してアドバイスを受け、お子さんへの正しい接し方、声かけを知り、お子さんにアプローチをかけていきましょう。
1-2. 【相談窓口の探し方】悩みを聞いてほしいのか解決策を知りたいのか
相談窓口を探すときには、相談に何を求めているのかを考えてみましょう。
不登校の相談には次の2種類があります。
- 否定せず、共感しながら悩みを聞いてもらう相談
- 具体的な解決策を提示してもらう相談
どちらの相談を望むのかで相談先が異なりますので、相談先を探す前にどちらなのか考えておくことをおすすめします。
- 悩みを打ち明ける場所を作り、子どもの気持ちを軽くしてあげたい
- 再登校は考えていない、子どもが不登校になってしまったつらい気持ちを聞いて欲しい
このような場合には、共感しながら悩みを聞いて、カウンセリングしてくれる相談先が適しているかもしれません。
ただ、共感をベースにした相談では、気持ちの整理はできるものの、現実的に不登校を解決するための方法は知ることができないのが現状です。
不登校の根本的な解決を望む場合には、お子さんとの接し方などを具体的にアドバイスをしてくれる団体へ相談するようにしましょう。
不登校支援で行われるカウンセリングの注意点については、こちらの動画も参考にしていただけると幸いです。
上記動画でお話ししているカウンセリングの注意点を踏まえた上で、利用を検討される場合には、無料カウンセリングサービスで一度体験してみると良いでしょう。
高校生とその親御さんが利用できる無料カウンセリングサービスについて、以下の記事でお話ししています。
こちらもCHECK
-

-
高校生の悩みを相談できる無料カウンセリング一覧|オンライン・電話・LINEチャットから利用可能!利用する際の注意点も紹介
この記事を読むのに必要な時間は約 28 分です。 「高校生の子どもが学校の悩みなどを無料で相談できるカウンセリングはある?」 「子どもが悩みを抱えている様子だ…このままにしていていいのだろうか?」 高 ...
続きを見る
2. 不登校の高校生が抱える悩みを相談できる窓口5選【子ども・親どちらも相談可能】
不登校について相談できる窓口を5つ紹介します。
共感と解決策のどちらを得られるのかに注目して、相談先を検討していきましょう。
2-1. スダチ|親御さんからの相談に対応
スダチでは親御さんからの相談に対応しており、不登校解決に向けて具体的なアドバイスを実施しております。
もちろん親御さんの抱えるつらい気持ちをお伺いしたうえで、その気持ちを軽減する方法、お子さんと一緒に前へ進む方法をお話しさせていただいております。
スダチでは、親子の信頼関係の構築やお子さんの自己肯定感を育てることに焦点を当てて、不登校解決に向けた支援を実施しております。
親御さんから、日々お子さんの様子や親御さんのお悩みをお伺いさせていただき、そのときのお子さんに合わせた最適な接し方、声かけをフィードバックする支援が特徴です。
親御さんがフィードバックに基づき行動してくださっているおかげで、親子の信頼関係が強いものになり、お子さんの自己肯定感もどんどん育ち再登校へとつなげています。
実際にスダチが支援させていただいた、お子さんはみなさん平均3週間で主体的に再登校しています。
脳科学に基づくアプローチによって、2023年6月時点で500名以上のお子さんを再登校に導いてきました。
顔出し不要で参加できる1対1の無料オンライン相談にて、一度お子さんの現状をお聞かせいただければ幸いです。
\無料相談を申し込む/
2-2. 学校の教職員|子ども・親どちらの相談にも対応
お子さんが通っている学校の教職員にも、不登校の相談ができます。
- 担任の先生
- 保健室の先生
- スクールカウンセラー
- スクールソーシャルワーカー など
このような職員に不登校の相談ができます。
スクールカウンセラーなどは、学校によっては配置されていない場合もあります。
基本的には共感ベースの相談で、気持ちの整理をしたいときに向いているでしょう。
学校で面談したり、家庭訪問してもらったりなど、お子さんの状態や学校の方針によって対応が変わります。
ただ、明確な因果関係は証明されていませんが、スクールカウンセラーの設置を増やした結果、不登校者数が増えたというデータがあることも念頭に置いていただけると幸いです。
共感してもらうことでお子さんと親御さんに、
- このままの自分でもいいんだ
- 不登校でもありのままの子どもでいてくれればいいんだ
という感情が生まれる場合があります。
そのため、不登校解決に向けたアプローチを実施する機会を失ってしまうこともあります。
共感してもらうことは、一時的な気持ちの整理になるため、大切なことです。
しかし不登校の解決にはつながらない場合もあるため、再登校して欲しい場合には、他の相談機関も同時に利用しましょう。
2-3. 教育相談センター|子ども・親どちらの相談にも対応
教育相談センターは、教育委員会が設置している公的な不登校の相談窓口です。
お住まいの地域のセンターを利用できますが、地域によっては「不登校相談センター」などと名称が異なることもあるので注意しましょう。
主に不登校で抱えているつらい気持ちに共感し、お子さんに居場所を提供することを目的としています。
ただし国が定めている方針では、不登校を解決し生徒の再登校を促すよりも、生徒が将来自立できるように支援するという方針があります。
実際、令和元年に国から各都道府県の教育委員会に対して通知された、「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」では、再登校しない選択肢もある旨が記載されています。
そのため、公的な相談窓口では不登校を解決し、再登校に向けて積極的に指導はしていない点は知っておきましょう。
詳しくは次の記事も参考にしてみてください。
こちらもCHECK
-

-
不登校の原因を文部科学省の実態調査から徹底解説【2023年4月最新情報】
この記事を読むのに必要な時間は約 36 分です。 「子どもが不登校になってしまった」 「文部科学省の調査からわかる子どもが不登校になる原因を知りたい」 「不登校に対する国の方針などを知り ...
続きを見る
2-4. 子どもの人権110番|子ども・親どちらの相談にも対応
子どもの人権110番は、不登校やいじめなど、子どもの人権に関わる問題を相談できる電話ダイヤルです。
親御さんとお子さんの両方から相談を受け付けていますし、顔を出す必要もなく、匿名もOKなので気軽に相談できます。
- 身元を明かさずに相談したい
- すぐに悩みを誰かに話したい
- 共感してもらって気持ちの整理をしたい
基本的に共感ベースの相談なので、以上のような方に向いています。
2-5. 精神科、心療内科|子ども・親どちらの相談にも対応
精神科や心療内科では、不登校の悩みに共感してもらいながら、身体に生じている症状の解決方法を相談できます。
- 起立性調節障害
- 昼夜逆転など生活リズムの乱れ
- 学習障害やADHDなどの発達障害
- スマホやゲームに熱中してしまうデジタル依存
お子さんがこれらの症状を抱えている場合には、医学的なサポートを受ける方法もあります。
ただし、医療機関で受けられるのはあくまで症状の治療であり、不登校の解決まで支援してもらえるわけではありません。
また不登校の相談で心療内科を受診した場合、医師によって診断の結果が異なる場合があります。ADHDと診断される場合もあれば、ADHDとは診断されず他のメンタルの不調を診断されるケースも多いです。
本来ならば解決できた不登校も、医師に発達障害と断定されたり、何かしらの病名を診断されることにより、再登校を諦めてしまう場合もあるでしょう。
そのため、お子さんの不登校はあきらかに病気が原因で投薬した方が良い状況なのかは見極めてあげることも必要です。
また、不登校の原因がよくわからずに心療内科へ相談する場合には、発達障害と断定されたり、何かしらの病名を診断されたとしても、それが原因で再登校を目指せないわけではないと知っておきましょう。
身体の症状が不登校にどう関連するのかについて、こちらの記事で紹介しています。お子さんの状態への理解を深めるきっかけとなれば幸いです。
こちらもCHECK
-

-
【子どもが朝起きられない】中学生・高校生の子どもが朝起きない原因|起立性調節障害・発達障害との関係【不登校になる前に親ができる対処法】
この記事を読むのに必要な時間は約 52 分です。 「中学生・高校生の子どもを、朝起こしても全然起きない…」 「朝起きない中学生・高校生の子どもが、不登校気味になってきた…」 ...
続きを見る
3. 高校生の不登校と抱える悩みを解決するための方法
3-1. 正しい親子関係を築き子どもの自己肯定感を育てる
正しい親子関係を築くことで、お子さんの自己肯定感が育ち、主体的に行動できるようになります。
正しい親子関係は次のような状態です。
- お子さんが親に遠慮することなく気持ちを適切に伝えてくれる
- 親子の立場が逆転していない(親が子どもの言いなりになっていない)
正しい親子関係を築くために大切なことは次のとおりです。
- お子さんが行動した過程に目を向けてたくさんほめる
- お子さんの気持ちや考えを受け入れて認める
- ダメなことはダメだと毅然とした態度で教える
気持ちをいつも受け入れて認めてくれて、そのうえで正しいことダメなことをきちんと教えてくれる親御さんのことをお子さんは尊敬して信頼するようになります。
信頼できる親御さんから、自分の行動や努力の過程をほめられることにより、お子さんの自己肯定感がどんどん育ちます。
自己肯定感が育つことで、「学校の問題も自分なら解決できる」と前進しはじめるでしょう。
3-2. 子どもに適した相談窓口、カウンセリング先を探しておく
高校生は思春期でもあり、親御さんに本当の気持ちを伝えるのが恥ずかしいお子さんも多いです。
お子さんが相談できる窓口を探しておき、気持ちが苦しくなってしまった時にいつでも相談できるようにしてあげましょう。
いつも身近にいる親御さんには言いづらいことでも、他の人に対してなら気持ちを打ち明けられることもあります。
お子さんにプレッシャーを与えないためにも、相談することは強制せず「こういう相談ができるところがあるよ」と選択肢を教えてあげるようにしましょう。
3-3. 規則正しい生活習慣に導く|デジタル依存を克服
スマホやゲームなどのデジタルに依存せず、規則正しい生活習慣を保てるようにしておきましょう。
昼夜逆転や長時間デジタル機器に没頭するなどの不規則な生活スタイルだと再登校を目指すことができません。
まずは、学校へ行く時と同じ生活リズムに整えましょう。
- デジタル機器の利用ルールを決める
- 寝る時間と起きる時間を固定しておく
- 親御さんも一緒に取り組む
これらを取り入れることが大切です。
そうすると次のような小さな成功体験が積み重なり、お子さんにとって「自己コントロールができる」という自信につながります。
- 朝きちんと起きられた
- きちんと寝る時間に布団に入れた
また、生活習慣が改善されて健康的になることで、お子さんのやる気も自然と生まれやすくなります。
生活習慣の改善が再登校のきっかけになることもあるのです。
詳しくは次の記事で解説しています。
こちらもCHECK
-

-
高校生の不登校の理由や原因とは?克服する意外なキッカケは早起き!?
この記事を読むのに必要な時間は約 31 分です。 高校生の子どもが不登校になってしまった。理由や原因はなに? 不登校を解決する方法を知りたい! お子さんがある日不登校になってしまったら、どうしたらまた ...
続きを見る
また、不登校になったお子さんの心境やタイプ別の対処法については、次の記事で紹介しています。
こちらもCHECK
-

-
不登校になったら親がやるべき3つのこと|不登校の7つのタイプと今の子どもの状態・解決法
この記事を読むのに必要な時間は約 87 分です。 「子どもが不登校になってしまった…子どもにどう接していけば良いのかわからない」 「子どもの今の状態に適した対処方法を知って、不登校を解決したい」 お子 ...
続きを見る
4. 不登校の高校生が抱えやすいよくある悩み
お子さんの不登校を解決するにあたって、次のような疑問を抱えている方もいるかもしれません。
- どうして子どもが不登校になってしまったのだろう?
- 今どんな気持ちを抱えているのだろう?
お子さんの気持ちや悩みを理解することは、不登校改善の大切な一歩となります。
4-1. 人間関係についての悩み
高校生は思春期でもあるため、繊細になったり感情的になったり気持ちをうまくコントロールすることが難しい時期でもあります。
自分の心身の変化に戸惑い、迷うことが増えるのは仕方ないことだと言えるでしょう。
また、学区ではなく学力で人が集まる高校では、生活環境が全く異なるクラスメイトも多くなります。
小学生のうちは、知らない人に対して臆せず話しかけるお子さんが多いですが、成長していくにつれて初対面の人と話すのが苦痛になるお子さんもいます。
また、スマホの所持が認められている学校では、SNSなどの振る舞いについても人間関係に影響があるでしょう。
ネットとの付き合い方は人それぞれですが、温度感の違いから友達がうまく作れないケースも見受けられます。
4-2. 成績を受けて将来についての漠然とした悩み
高校では専門的な授業内容が増えるため、思うように成績が上がらず将来について不安を抱えることもあります。
とくに自分の学力よりも高い学校に入ったお子さんは、勉強の悩みを抱えることが多いです。
中学では成績上位を取れていたにも関わらず、高校で同じように頑張っても成績が振るわないことがあるからです。
目に見える成果が出にくくなることで挫折感を味わい自己肯定感が下がってしまうお子さんもいます。
- 高みを目指して勉強に取り組んだのは素晴らしいこと
- 成績がどうであっても大事な存在であること
などを伝えてあげて、お子さんの気持ちが落ち込み過ぎないようにフォローしていきましょう。
4-3. 無気力になる|なぜ不登校になったのかわからない悩み
お子さんが無気力になってしまうこともあります。
お子さん自身も無気力になった理由がわからず、不登校の原因が明らかにできないので対処に困りやすいケースです。
無気力は自己肯定感の低下によって起こります。
長い時間をかけてストレスが少しずつ積み上がっていると、小さなきっかけで自信を失ってしまうことがあります。
「なんとなく元気がない」といった状態のこともあれば、「今まで好きだったことにも関心を示さない」というケースもあります。
無気力については前兆を見逃さないように注意することが大切です。
もし、前兆を見逃してしまった時でも、お子さんの心理状態に合わせた対応をするように心がけましょう。
無気力なお子さんへの対応方法については、こちらの記事も参考にしてみてください。
こちらもCHECK
-
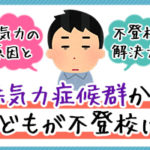
-
無気力症候群から子どもが不登校に?無気力の原因と解決法【高校生・中学生・小学生】
この記事を読むのに必要な時間は約 26 分です。 子どもが無気力症候群気味で不登校になってしまった。解決方法を知りたい。 子どもが無気力になった原因を探りたい。 お子さんが無気力な様子で不登校となった ...
続きを見る
5. 不登校の高校生がいる親御さんが抱えやすい悩み【相談窓口を頼って大丈夫】
5-1. 子どもとどう接したらいいかわからない
お子さんの不登校を解決したい気持ちはあるものの、お子さんにどう接したらいいのか戸惑うかもしれません。
不登校の解決で大切なのは、見守って待つのではなく、専門機関の相談窓口を利用しながら、親御さんがお子さんに働きかけることです。
お子さんへの接し方に不安がある場合には、不登校支援を専門に扱うスダチなどに相談しましょう。
専門機関は不登校のお子さんを数多く見ており、お子さんの心理状態や親御さんが取るべき行動を熟知しているからです。
専門機関に相談しながら、お子さんに対して次のことを意識して接してみましょう。
- 努力を褒めて自己肯定感を育てる
- 毅然とした態度で間違いを教えてあげる
この2つを徹底して実践していくと、お子さんから信頼されるようになります。
お子さんから悩みを打ち明けてくれるようになったり、言うことを聞いてもらいやすくなったりします。
不登校のお子さんを見守る危険性については、こちらの動画も参考になさってください。
お子さんを見守っているだけでは不登校が改善しないばかりか、学校をやめたいと言い出す危険性もあります。
お子さんが学校をやめたがっているときの対処法については、次の記事で解説しています。
こちらもCHECK
-

-
「高校やめたい、学校やめたい」親はどう対応すべき?後悔しないためのその後の選択肢を解説
この記事を読むのに必要な時間は約 47 分です。 「高校が合わないからやめたいと子どもが言い出した」 「将来のために卒業まで通ってほしいけど、どうやって説得したらいいかわからない」 お子さんから突然「 ...
続きを見る
5-2. 育て方が悪いなどと責められるかもと不安
不登校の相談をしに行ったときに「自分の子育ての仕方についてお叱りを受けるかもしれない」と不安に思う親御さんもいらっしゃるのではないでしょうか?
親御さんは、お子さんのことを大切に思い育児されているからこそ、相談窓口の利用を検討されていることと存じます。
そのような親御さんに向けて「子育てが悪い」などと言う場合には、利用を控え、相談窓口からの助言については聞き流し、気に病まないようにしていただきたいです。
不登校は1つの原因で起こるわけではなく、さまざまな要因が複雑に絡み合って起こります。
根本をたどっていくと、お子さんが親御さんからの愛情を上手に受け取れていない場合も多いです。
しかし、現状の日本はお子さんの将来のために共働きをして、お子さんと過ごす時間が限られている世帯も多く、海外と比べてスキンシップをとる機会も少ないです。
また、お子さんが受け取りやすい愛情の伝え方を教えてくれる機関もありません。
決して親御さんが悪いわけではなく、現状の日本では不登校は誰にでも起こりうることだと言えるでしょう。
そのため、これから不登校の解決方法や、お子さんに愛情が伝わりやすい接し方を知っていけば大丈夫です。
スダチでは、そのときのお子さんの様子を日々お伺いさせていただき、お子さんに合った声かけ方法や接し方をアドバイスしております。
不登校が解決しただけでなく「前よりも親子関係がよくなった」「家族で過ごす時間が楽しくなった」という声もいただいております。
無料のオンライン相談を実施しており、1対1で顔出しも不要です。現状の悩みを一度スダチへご相談いただけたら幸いです。
\無料相談を申し込む/
6. まとめ
高校は、お子さんの今後のキャリアにも大きく関わってくる大事な時期なので、親御さんは不登校の現状を強く心配されていることでしょう。
お子さんだけでなく、親御さんご自身もご不安な気持ちを相談して、不登校解決に向けた行動方法を知っていただけたら幸いです。
スダチでは不登校のお悩みに共感するだけでなく、脳科学に基づいたアプローチ方法で不登校解決に向けて行動すべきことを具体的にご提案させていただきます。
不登校が長期化し、留年の危機が迫っていた高校生のお子さんも再登校に導いてきました。
お子さんへの接し方を実践しやすい具体的な形でお伝えしますので、どうしたらいいのかわからない方は、一度お子さんの現状をお聞かせいただければ幸いです。
1対1の無料オンライン相談を実施しており、顔出しも不要です。
\無料相談を申し込む/






