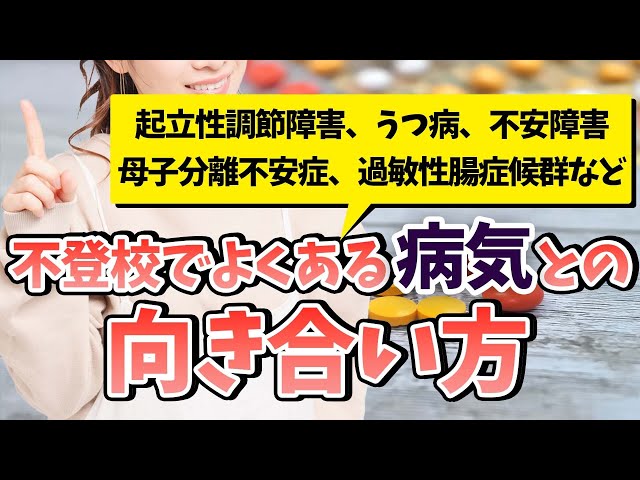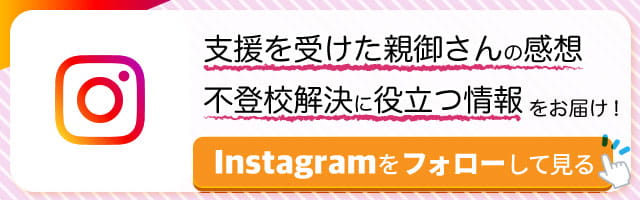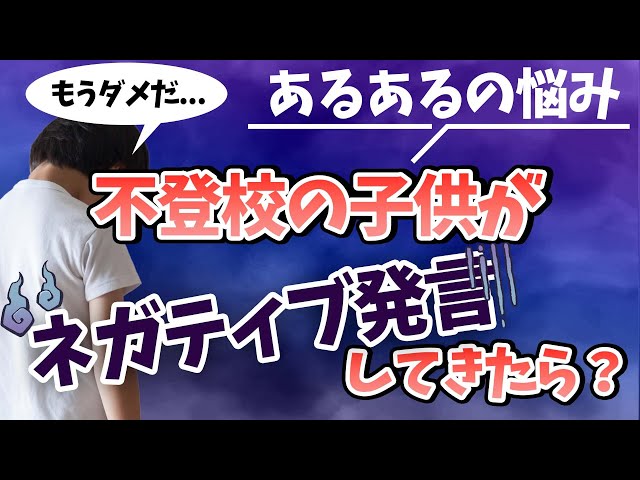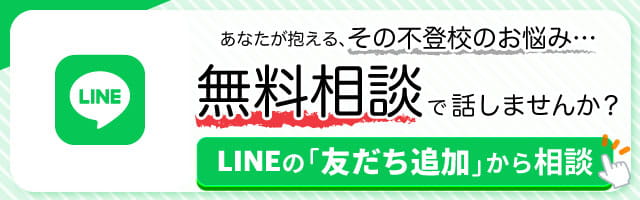この記事を読むのに必要な時間は約 56 分です。
大人の「敏感さん・繊細さん」を表す言葉として、有名になったHSP(Highly Sensitive Person)。
HSPの子どもバージョンは、「人一倍敏感な子ども」として、HSC(Highly Sensitive Child)と呼ばれています。
私たちをはじめとする不登校支援サービスのもとに、最近増えているのが「うちの子どもが不登校になったのは『HSCだからですか?』」というもの。
この記事を読んでいるあなたも、子どもの不登校とHSCの関係が気になっているはずです。
今回は、HSCの気質がある子どもの特徴と再登校に向けた接し方について解説します。
【平均3週間で不登校解決プログラム】を展開する小川涼太郎監修のもと、HSCで不登校経験者の筆者がお伝えする内容は次のとおり。
記事を読むとわかること
- HSCと不登校の関係
- HSCの特性・特徴と学校生活
- HSCの不登校を解決する3つのポイント
「敏感・繊細」である HSCは、不登校になる可能性が高めです。
しかしながら、「『HSC』だから不登校に…」と考える必要はありません。
HSCは子どもが生まれ持った気質であるため、HSCを原因にするのは「子どもに問題がある」と言っているのと同じです。
HSCの特性・特徴を理解して子どもとの向き合い方を知ることで、不登校を解決に導くことはできます。
1. HSC(エイチエスシー)とは?HSCの定義や特徴
人一倍敏感であるHSC(エイチエスシー)の定義や特徴をまずは詳しく解説します。
1-1. HSCの概念
HSCとは「Highly Sensitive Child(ハイリーセンシティブチャイルド)」を略した表記であり、「非常に敏感で繊細な子ども」を意味します。
アメリカの心理学者であるエレイン・N・アーロン博士によって、まとめあげられた概念です。
同じアーロン博士が提唱したHSPもありますが、HSPは「非常に敏感で繊細な大人」を指します。
アーロン博士によると、人口の15%〜20%を占めるそうです。
HSCの子どもは「非常に敏感で繊細」なため、外部からの刺激に対して他の人よりも大きな反応が出やすい特徴があります。
たとえば、周囲の雑音が気になって集中できなかったり、機嫌の悪い人がいるといち早く気づき、自分が悪いように捉えてしまったりなどです。
そのため、刺激の強い環境に長時間いると神経が消耗し、疲れやすくなる傾向があります。
1-2. HSCの原因は?HSCは生まれ持った性質
HSCは生まれ持った性質です。
病気や障害ではなく、医学的な診断はされません。人は、それぞれさまざまな性格や性質がありますが、その一つとなります。
生まれつきの性質なので、親の育て方が原因でHSCになるわけでもありません。
「自分のせいでHSCになってしまったかもしれない」と自分を責めないようにしてください。
また、HSC気質があるのは、決して悪いことではありません。
他人の痛みや苦しみにいち早く気づくことができたり、さまざまな事柄を自分の責任として捉えることができ責任感が強かったり、社会で生きていくうえで非常に大切な性質でもあります。
1-3. HSCが持つ4大特性|DOESとは?
すでにネット記事や書籍を読み知っているかもしれませんが、改めてHSCが持つ特性をチェックしておきましょう。
敏感・繊細な子どもであるHSCは、4つの特性“DOES(ダズ)”を必ず持っています。
- D:深く処理する
- O:過剰に刺激を受けやすい
- E:全体的に感情の反応が強く、共感力が高い
- S:ささいな刺激を察知する
まとめると、HSCは「1を聞いて10を知る・感じる」を無意識に行っています。
私たちが息をするのと同じように、自動的に行っているため、ONとOFFを切り替えるのは簡単ではありません。
さらに、DOESの特性は生まれ持ったものであり、変えることはできません。
DOESの特性とは、一生つきあっていくものです。
子どもによって、それぞれの特性には強弱があります。
親御さんだけでなく子どもも、HSCの特性がどのようなもので、どのようなことに影響するのかを学ぶといいでしょう。
1-4. HSCと発達障害の関係
HSC気質のある子どもは、感性や五感が鋭いことから、病気・発達障害だと思われがちです。
HSCは病気でも、発達障害でもありません。
しかしHSCは病気でも、発達障害でもありません。
HSCと発達障害の違いを詳しくみると、次のとおり。
- 発達障害(神経発達症):情報処理の仕方や速さ、物事の感じ方や理解の仕方が一般と異なる脳の機能による障害
- HSC:生まれつきの性質・気質で、受性豊かな子ども
あくまでHSCが持つ敏感さ・繊細さは、生まれ持った気質。
病気・障害ではないため、病院で診断が下ることも、治療することもありません。
発達障害は、先天的な脳機能の障害とされています。
読む・書く・計算ができない・とても苦手であったり、人とのコミュニケーションがうまくとれません。
発達障害は医師による診断を受けられるものの、完治は難しいとされています。
ただし、発達障害の特徴の中には、光や音に敏感に反応したり、HSCの気質と似たような特徴もあります。
もしも、HSCの特性なのか発達障害なのか判断がつかない場合は、以下の医療機関に相談してみましょう。
- 小児科
- 児童精神科
- 小児神経科
- 発達外来
- 大学病院または総合病院
発達障害かも?と思うならコチラ
-
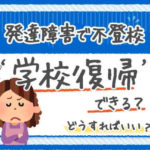
-
【発達障害と不登校】「ふつう」ができない【理解とサポートがカギ】
この記事を読むのに必要な時間は約 52 分です。 子どもの不登校について調べていると「発達障害かも」と書かれていることもあり、気がかりですよね。 この記事は、次のお悩み・疑問を持っている ...
続きを見る
1-5. 子どもがHSCなのか診断するためのセルフチェックリスト
ここでは、お子さんがHSCかどうかを簡易的に診断するための、23のチェックリストをご紹介します。
簡易的なものとなるため、お子さんにHSCの気質の傾向がみられるか知りたいときの手助けとして活用してみてください。
次の質問に、感じたままに答えてください。子どもについて、どちらかといえば当てはまる場合、あるいは、過去に多く当てはまっていた場合には「はい」、全く当てはまらないか、ほぼ当てはまらない場合には、「いいえ」と答えてください。
- すぐにびっくりする
- 服の布地がチクチクしたり、靴下の縫い目や服のラベルが肌に当たったりするのを嫌がる
- 驚かされるのが苦手である
- しつけは、強い罰よりも、優しい注意の方が効果がある
- 親の心を読む
- 年齢の割りに難しい言葉をつかう
- いつもと違う臭いに気づく
- ユーモアのセンスがある
- 直感力に優れている
- 興奮したあとはなかなか寝つけない
- 大きな変化にうまく適応できない
- たくさんのことを質問する
- 服がぬれたり、砂がついたりすると、着替えたがる
- 完璧主義である
- 誰かがつらい思いをしていることに気づく
- 静かに遊ぶのを好む
- 考えさせられる深い質問をする
- 痛みに敏感である
- うるさい場所を嫌がる
- 細かいこと(物の移動、人の外見の変化など)に気づく
- 石橋を叩いて渡る
- 人前で発表するときは、知っている人だけのほうがうまくいく
- 物事を深く考える
得点評価:13個以上に「はい」なら、お子さんはおそらくHSCでしょう。
引用元:『ひといちばい敏感な子』(1万年堂出版、エレイン・N・アーロン著、明橋大二訳)
しかし、心理テストよりも、子どもを観察する親の感覚のほうが正確です。
たとえ「はい」が1つか2つでも、その度合いが極端に強ければ、お子さんはHSCの気質を持っていると捉えることもできます。
2. HSC(エイチエスシー)が原因で不登校になるわけではない!子どもの敏感さを原因にするのは“感性の否定”
「子どもの不登校の原因は、学校にある」と考えていませんか?
けれど、子どもに聞いても学校に行きたくない理由がわからず、行き詰まりを感じていると思います。
- “いじめ”はない
- 友だちはいる
- 先生との仲も悪くはない
- 勉強もできている
不登校の原因が学校にないとなれば、子どもに原因を求めたくなりますよね。
子どもの性格が内向的であれば、不登校が子どもの性格に起因すると考えるのも当然です。
敏感さん・繊細さんであるHSPが有名になり、今ではHSCのネット記事や書籍も数多くあります。
子どもを「HSCかも」と判断することで、納得できた点もあったでしょう。
しかし、「HSCだから不登校になった」と考えるのは、良い傾向とは言えません。
HSCは病気などではなく、子どもが生まれ持った特性です。
HSCを不登校の原因として扱うことは、「子どもの物事の感じ方・捉え方が悪い」と言っているのと同じなのです。
HSCが原因なのではなく、お子さんの自己肯定感が低い状態にあるとき、不登校になりやすいことがあります。
また、親御さんはお子さんに愛情をたくさん注ぎ育児なさっていることと存じますが、時にお子さんが愛情をうまく受け取れていないとき、自己肯定感が下がってしまう場合があります。
親御さんが悪いわけでは決してありません。
これからお子さんに最適な愛情の伝え方を知っていくことが大切です。
スダチの支援では、お子さんに合わせた愛情の伝え方や接し方をサポートしております。
お子さんに愛情が行き届き、お子さんが自己肯定感で満たされるとお子さんは前進します。
\ HSCも抱えがちな「うつ病・不安障害」などの向き合い方がわかります! /
※YouTubeサイトへ移動します
親の自分に原因が?と考えていませんか?
-
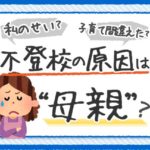
-
「不登校の原因は母親」だと感じていませんか?【母親のせいではない】
この記事を読むのに必要な時間は約 51 分です。 子どもが不登校になると、自分のせいかもしれないと責任を感じる親御さんは多いです。 子どもの不登校は、母親の私が原因? 子育てを間違えてし ...
続きを見る
3. HSC(エイチエスシー)で敏感な子どもが持つ6つの特徴と学校生活にストレスを感じる理由
HSCの特性DOESは抽象的で、ピンとこないかもしれません。
DOESの特性を具体的にすると、次のようになります。
-
細かいことに気づく
-
刺激を受けやすい
-
強い感情に揺さぶられる
-
他人の気持ちにとても敏感
-
石橋を叩き過ぎる
-
よくも悪くも注目されやすい
「そんな小さなことなの?」と思ったかもしれません。
「そんな小さなこと」に気づいて反応してしまうのが、「ひといちばい敏感・繊細」なHSCの特徴です。
ここで気になるのが、HSCの特性と学校の関係ですよね?
敏感・繊細なHSCにとって、学校は刺激(情報)が多すぎる場所。
例えるなら、毎日テーマパークに通っているようなものなのです。
ここからは、HSCの特性と学校の関係を1つずつ解説します。
学校生活にストレスを感じやすい理由を知っていただくことができます。
3-1. 細かいことに気づく・気づきやすい
ほかの人が見過ごすような、小さなことに気づくのが、HSCです。
何に対して気づく・気づきやすいかは、子どもによって様々。
におい・音に反応しやすい子もいれば、人間関係の変化に気づきやすい子もいます。
例えば、においに敏感なHSCの場合、人が密集する教室・給食のにおいがストレスになることも。
はたから見ればささいなことが、HSCには大きな悩みの種であることも珍しくないのです。
3-2. 刺激を受けやすい
学校は刺激(情報)に溢れており、HSCには肉体的・精神的にも疲れやすい場所です。
加えてHSCは、慣れていないこと・突発的なことが苦手。
このため、学校行事に忌避感を抱くことも少なくありません。
- 運動会
- 発表会
- 授業参観
学校行事の場面では、周囲の「気」に圧倒されつつ、注目を浴びるなかで実力を試されます。
人に見られる場面では、ふだんの実力を出せない傾向が高めです。
3-3. 強い感情に揺さぶられる
HSCは感情に対する感度も敏感です。
HSCの感情への感度は、自分の気持ちにだけ敏感なわけではなく、他人の感情にも敏感です。
学校生活であれば、次のような場面に強く反応します。
- 先生がクラスメイトを叱っている
- クラスメイトが言い争っている
直接的に自分は関係なくても、その場の空気・その場を取り巻く感情に圧倒されてしまうのです。
ちなみに、感情に対する感度は、ネガティブなもの・ポジティブなもの、どちらにも発揮します。
3-4. 他人の気持ちにとても敏感
共感力の高さも、HSCの特徴の1つです。
同じ空間にいる人であれば、目に見えるもの・見えないものから、その人の機嫌を読み解きます。
- 表情
- まとっている雰囲気
- 声のトーン
- ジェスチャー など
相手の調子に合わせて先回りできるため、HSCの気質を持つ子どもは「気が利く・優しい」の評価を受けやすいです。
良いことではあるものの、無意識的に他人を優先しているだけであって、自分自身の気持ちにフタをしていることも。
親や先生が望む子どもであろうとして、常に優秀であろうと無理をすることもあります。
3-5. 石橋を叩き過ぎる
見慣れた光景でも何かしらの変化があれば、HSCはすぐに気づきます。
それだけ、注意深く用心深く、物ごとを見ているのです。
学校生活では、クラス全員が足並みをそろえつつ、テキパキ動くことが良しとされます。
慎重さを活かせる場面は少ないため、長所を生かし辛い傾向にあります。
3-6. よくも悪くも注目されやすい
HSCが持つ特性や特徴は、とても偏見を受けやすいもの。
敏感・繊細の言葉も、人によっては次のように捉え方が異なります。
敏感・繊細をネガティブに言うと
- 臆病で、小さなことにとらわれやすい
敏感・繊細をポジティブに言うと
- 注意深く、小さなことに気づける
HSCは5人に1人の、少数派(マイノリティ)。
基準値からほんのわずかに飛び出しているため、「少し変わった子」として見られがちです。
HSPと不登校の関係性については、以下の記事でも紹介しています!
こちらもCHECK
-

-
不登校に多いHSPとは?正しい付き合い方と不登校を解決する対応方法
この記事を読むのに必要な時間は約 22 分です。 「HSPの気質があると不登校になってしまうのか知りたい」 「HSP気質のある子どもの不登校を解決する方法が知りたい」 不登校のお子さんの中には、非常に ...
続きを見る
こちらもCHECK
-

-
【HSCの子育ては疲れる】HSCの子どもは学校へ行くだけで疲れる!不登校気味のときや家庭で癇癪を起こすときの対処方法
この記事を読むのに必要な時間は約 26 分です。 「HSCの子どもが不登校気味で子育てに疲れてしまった。不登校の解決方法を知りたい。」 「HSCの子育てに疲れてしまった。どのような子育て ...
続きを見る
4. HSC(エイチエスシー)の気質があり不登校の子どもが再登校するための4つのポイント
ここまで、 HSCの特徴を解説しました。
ここからは、HSCかつ不登校の子どもが再登校を叶えるためのポイントを解説します。
人一倍敏感で繊細なHSCが不登校になったとき、することは次の4つです。
- スダチなどの不登校支援団体へ相談する
-
ネガティブな気持ちを吐き出させる
-
自己否定感を小さくする
-
自己肯定感を育てる
まずは、子どもが抱えているネガティブな気持ちを吐き出させましょう。
先に感情を出すことで、自分が持つ敏感さや繊細さなどの特性・特徴を受け入れやすくなります。
また、HSCは自分で自己肯定感を抱きにくいです。
親御さんがサポーターとして、フォローする必要があります。
4-1. スダチなどの不登校支援団体へ相談する
HSCの傾向が見られお子さんが不登校のとき、親御さん1人で悩まずにスダチなどの専門機関へご相談いただけたら幸いです。
HSCのお子さんは周囲の細かいことに気づくことができるからこそ、周囲の子どもと自分を比較してしまうことがあります。
また、感受性が強く、人の気持ちに敏感に気づけるからこそ、何か周りでうまくいかないことがあるとき自分の責任として捉えることも。
それらが関係し、お子さんは自分のことを責め、自己肯定感が下がり切っている状況です。
自己肯定感が下がりきった状況では、学校でうまくいかないときになんでも自分のせいだと捉えてしまいます。
学校生活を送ることに大きなストレスを抱えてしまうのです。
お子さんの自己肯定感を育てることができるのは親御さんだけです。
親御さんの接し方や声かけを変えるだけで、HSCのお子さんの自己肯定感が育ち、自発的に再登校するようになります。
スダチでは、これまでさまざまな不登校のお子さんを持つ親御さんを支援させていただき、HSCの気質が見られる不登校のお子さんを再登校に導いてきた経験があります。
日々のお子さんの様子をヒアリングさせていただき、そのときのお子さんに合った、自己肯定感の育つ声かけや接し方をサポートいたします。
親御さんがサポートに沿って行動してくださっているおかげでみなさん平均3週間で再登校しています。
無料セミナー動画からスダチの支援内容を知っていただけたら幸いです。
動画をご視聴いただいた方には、無料相談を実施しております。ぜひお子さんの現状をお聞かせください。
4-2. ネガティブな気持ちを吐き出させる
物ごとや他人の気持ちに敏感なHSCは、無意識に他人に合わせる生き方をしています。
他人に合わせる=「我慢」をしているのです。
まずは、これまで我慢してきたことを全部、吐き出させてあげましょう。
このときのポイントは、子どもに向ける態度です。
- 何でも言っていいよ
- あなたの気持ちを受け止める準備はできているよ
子どもが話せるように、安心できる空間を整えることが大切です。
加えて、HSC気質を持つ子どもの感情を受け止めるとき、親は「ゆとり」が必要です。
親も一緒に感情を爆発させると、子どもは次のどちらかを強制されるため、自分の気持ちを出すどころではなくなります。
- 親の感情に圧倒され、自分の気持ちが引っ込む
- 自分ではなく、親を気遣わなければならない
安心できる場所で気持ちを吐き出すことで、子どもは我慢から解放されます。
\ ネガティブな言葉が出てきたら… /
※YouTubeサイトへ移動します
4-3. 自己否定感を小さくする
HSCは自己否定感が強いことが珍しくありません。
自己否定感とは「自分はダメなんだ」と思う気持ち、考え方です。
HSCは、敏感さ・繊細さから、ほかの子どもと「少し違う」と見られやすいです。
「少し違う」を、個性や長所ではなく、欠点に感じてしまうため、自己否定感を抱きやすくなります。
自己否定感を小さくするため、効果的なのは「質問をする」こと。
- どうして、そう思うのか
- 何がネガティブな感情にさせるのか
子どもに質問を投げかけることで、自己否定感を引き起こしている原因・考え方のクセが見えてきます。
\ ○○力があれば自己否定感が低い理由もわかるかも /
※YouTubeサイトへ移動します
さらに、自己否定感を小さくしておくことで、自己肯定感も育ちやすくなります。
4-4. 自己肯定感を育てる
自己肯定感は、自分と他人を比べずに、今の自分を認めること。
自己肯定感は、心の土台です。
土台である自己肯定感が低いと考え方が歪み、生きづらさを覚えることになります。
例えば、極端な例をあげると次のようになります。
- ほかの子どもと違う自分は、変・おかしい
- 変・おかしいから、不登校になったんだ
- どうせ、大人になっても、このままなんだ
自己肯定感が育つと、たとえば何か壁にぶつかったときも「自分がダメだからこうなったんだ」とは捉えず、「こんなことが起きる時もある、乗り越えよう」と前向きに解決できるようになります。
ちなみに、自己否定感が強く、自己肯定感が弱くなりがちなHSCが、大人になってから自己肯定感を育むのは至難の技です。
心の土台を強固なものにするタイミングは、今しかありません。
子どものうちに自分の敏感さ・繊細さを知るのは、自己理解が深まる良い機会です。
そして、不登校を乗り越えることは、苦難を乗り越えた経験として、お子さんの今後の人生に必ず役立ちます。
自己肯定感を育てるには“甘え”が必要⁉︎
-

-
学校に行きたくない!子どもの不登校は「甘え」ではなく「甘え」である。でも「甘やかしすぎ」はNG
この記事を読むのに必要な時間は約 32 分です。 ポイント 不登校は甘えが理由なの? 親のしつけが悪かったのだろうか? 甘やかしはいけないから無理矢理学校へ行かせた方がいいの? &nbs ...
続きを見る
お子さんが母親と離れることを敏感に嫌がる場合は、次の記事をご参考になさってください。
こちらもCHECK
-

-
母子分離不安気味な小学生の子どもが不登校に!根本原因と解決方法
この記事を読むのに必要な時間は約 24 分です。 子どもが一時も離れてくれない状況で不登校気味になってしまった…原因はなに? 不登校を解決して再登校する方法を知りたい。 母子分離に不安を感じお子さんが ...
続きを見る
5. HSC(エイチエスシー)で不登校の子どもに不調が見られるときの対処法
ここでは、HSCで不登校の子どもに不調がみられて困っているとき、親御さんがすぐできる対処法を紹介していきます。
5-1. HSC(エイチエスシー)で不調が見られるときの対処法①環境になじめず落ち込む様子が見られるとき
HSCの特性上、集団生活を送ると疲れやすくなってしまいます。
不安や緊張の神経回路が活発で、長時間集団の中で過ごさなければならない環境は、つらさを覚えてしまいます。
そんなお子さんにとって、ご家庭で過ごす時間は大切なものです。
ご家庭でリラックスできる時間は、すり減ってしまった神経や疲れを回復してくれます。
お子さんがぐったりと疲れているときは、1日がんばったことをねぎらい、ゆっくり休ませてあげましょう。
5-2. HSC(エイチエスシー)で不調が見られるときの対処法②学校に行きたがらないとき
ストレスを感じながらも学校へ行き続けたとき、疲れ果ててしまい、登校を渋ったり、拒否したりする場合もあります。
本人も、学校に行けない自分を責めてしまっているかもしれません。
親御さんに心配をかけていることに負い目や罪悪感を感じている場合もあります。
まずは、お子さんの毎日つらかった気持ちを受け入れて認め、安心させてあげてください。
どんな状況のときでもお子さんのことが大切な存在だと伝えましょう。
「困っていることを一緒に解決していこう」とお子さんの気持ちが前進するように声かけすることが大切です。
5-3. HSC(エイチエスシー)で不調が見られるときの対処法③体に不調が見られるとき
HSCのお子さんは、頭痛や不眠を引き起こしやすくなります。
過剰に緊張することから興奮状態が続き、抑うつ状態などが生じることも。
無理を重ねお子さんが頑張ってきた証拠でもあります。
まずは、どんな状況のときでも頑張ってきたお子さんのことを認めてほめてあげてください。
明らかな不調がわかるときに無理に「学校へいこう」と促すと、お子さんも親御さんのことをうまく信頼することができません。
まずは、不調が回復するよう体を休ませることも大切です。
そのうえで、親子の信頼関係とお子さんの自己肯定感を育てる次の接し方を日常で意識してみましょう。
- 正しいことはたくさんほめる
- 結果を見ずにお子さんが頑張ったことの過程をほめる
- いけないことをしたときにはダメなことはダメだと毅然とした態度で伝えていく
信頼できる親からたくさんほめられることでお子さんの自己肯定感が育ちます。
気づくと心の元気を取り戻し、心身に感じていた不調がなくなってしまいます。
ただし、明らかにお子さんの心身に普段とは異なる不調が見られる時には、受診することも大切です。
体に不調が見られ不登校のときの解決法は以下の記事でも解説しています。
こちらもCHECK
-

-
学校へ行く前腹痛や吐き気を感じる高校生・中学生の原因とは|不登校の解決方法
この記事を読むのに必要な時間は約 34 分です。 学校へ行く前体調不良を訴えることが増えた 何か病気なのかしら? どうやって解決すればいいの? 結論を申し上げると、学校へ行く前の体調不良 ...
続きを見る
6. HSC(エイチエスシー)で敏感な子どもを正しく理解するために役立つ書籍やコミュニティ
ここまで、HSCの概念や特徴などを紹介してきました。
HSCのお子さんの性質、特徴をさらに詳しく知っていくことで、お子さんがストレスを感じる原因やお子さんの心境を探ることができます。
もしも今HSC気質のあるお子さんが不登校気味の時、親子で前進するためには、お子さんの今の心境をさらに理解することも大切です。
HSCのお子さんとより深く関わっていくためには、たくさんの情報が必要なのです。
ここでは、役立てられる情報をまとめましたので参考にしてください。
6-1. HSC(エイチエスシー)を正しく理解できる書籍
書籍は正しい知識を身につけることができます。
HSCの子どもの特徴を理解することができる4つの書籍をご紹介します。
『ひといちばい敏感な子』
1万年堂出版刊、エレイン・N・アーロン著、明橋大二翻訳
HSCの名付け親、アーロン博士が著書の書籍です。
長年の研究による豊富な知識、お子さんの時期別のアドバイスが掲載されています。
『子どもの敏感さに困ったら読む本』
誠文堂新光社刊、長沼睦雄著
多くのHSPを診察してきた第一人者による情報です。
5章にわけ、HSCの子育てにまつわるアドバイスが載っています。
『HSCの子育てハッピーアドバイス』
1万年堂出版刊、明橋大二著、太田知子イラスト
漫画やイラストが多いため、文字を読むのが苦手な方に最適です。
困ったときの対処法をわかりやすく学べる一冊です。
『鈍感な世界に生きる敏感なひとたち』
ディスカヴァー・トゥエンティワン刊、イルセ・サン著、枇谷玲子訳
HSCというよりはHSP向けの内容ですが、巻末のアイデアリストにはさまざまな休息法が載っています。
さまざまな刺激を受けて、お子さんが疲れを感じているとき参考になります。
6-2. HSC(エイチエスシー)を正しく理解できるコミュニティ
HSCの子どもと親が集まるコミュニティも存在しています。
親同士でお子さんの悩みを共有しあったり、一緒に前進できるような場です。
さまざまな親御さんの悩みや前進に向けた接し方を聞くことで、HSCの特性を身を持って理解していくことができます。
また、同じ悩みを持つ親御さんに知り合えることで、現在ひとりで抱え込んでいる悩みの軽減につながるかもしれません。
気持ちが軽くなり「HSCについて必要以上に悩みすぎていたのかも」と捉えることができ、お子さんと一緒に前進するきっかけになるかもしれません。
7. HSC(エイチエスシー)気質の子どもが不登校のときによくある質問
ここではHSC気質のお子さんが不登校のときによくある質問をまとめました。
参考にしてください。
7-1. HSC(エイチエスシー)とHSP(エイチエスピー)の違いは?
子どもか大人かの違いになります。
HSCは「Highly Sensitive Child」の略で、HSPは「Highly Sensitive Person」の略です。
HSPについては以下の記事でも解説していますので合わせてご参考になさってください。
こちらもCHECK
-

-
不登校に多いHSPとは?正しい付き合い方と不登校を解決する対応方法
この記事を読むのに必要な時間は約 22 分です。 「HSPの気質があると不登校になってしまうのか知りたい」 「HSP気質のある子どもの不登校を解決する方法が知りたい」 不登校のお子さんの中には、非常に ...
続きを見る
7-2. HSC(エイチエスシー)の具体例は?
具体的な特徴として次の6つがあげられます。
- 細かいことに気づく・気づきやすい
- 刺激を受けやすい
- 強い感情に揺さぶられる
- 他人の気持ちにとても敏感
- 石橋を叩き過ぎる
- よくも悪くも注目されやすい
エピソードの具体例としては次のような様子が見られます。
例えば、お子さんと一緒にスーパーを訪れた際、店頭で流れるBGMのことを気にかけたりします。
誰もが聞き逃してしまうようなBGMも「この音楽はなんて悲しそうなんだろう」などと感覚的にとらえたりもします。そのくらい、さまざまな刺激に敏感に反応し、大きく受け止めるのです。
そのため、親御さんが小さなため息をついただけでも、「怒ってるの?」と敏感に感じとることもあります。
7-3. HSC(エイチエスシー)は親のせい?
HSCは生まれ持った特性のため、親御さんが原因ではありません、
ちなみに、遺伝で決まるかどうかは、正直まだはっきりとわかっていません。
「HSCは遺伝するのか」という研究はまだ続いています。
7-4. 子どもが学校に行きたくない、怖いという。病気なの?
学校へ行きたくないと思う気持ちは病気ではない場合がほとんどです。
お子さんの自己肯定感が下がりきったことを機に、「学校へ行きたくない」気持ちが現れる場合が多いです。
学校でなにか問題に直面したとき、お子さんの自己肯定感が下がり切った状態だと「私が悪いんだ」「私に乗り越えられるはずがない」と学校へ行きたくないという感情が生まれます。
そのため、お子さんに愛情を伝えながらお子さんの自己肯定感を育てることが大切です。
親御さんが積極的に行動することでお子さんの気持ちは、再登校しようという気持ちへシフトします。
不登校になるきっかけや原因については、こちらの記事で細かく説明しています。合わせてお読みください。
こちらもCHECK
-

-
不登校になったら親がやるべき3つのこと|不登校の7つのタイプと今の子どもの状態・解決法
この記事を読むのに必要な時間は約 87 分です。 「子どもが不登校になってしまった…子どもにどう接していけば良いのかわからない」 「子どもの今の状態に適した対処方法を知って、不登校を解決したい」 お子 ...
続きを見る
7-5. HSC(エイチエスシー)の子どもが大人になるとどうなるの?
HSCは性質のため、大人になっても基本的には変化はしません。
ただし子どものうちから自己肯定感を育てていると、物事の捉え方や考え方は大きく変化しています。
たとえば何か人生の壁に遭遇した時にも、自己否定して捉えず、「自分なら乗り越えられるから大丈夫」と捉えられるようになります。
一方、自己肯定感が小さいままだったり、不登校を放置したままにすると、引きこもりになる可能性もあるので注意しましょう。
7-6. HSC(エイチエスシー)で思春期の子どもの特徴と接し方は?
思春期のHSCは、大人の顔と子どもの顔を持ち合わせています。
悩んでいる様子があり、話を聞きだそうとしても、反抗的でそっけない態度をとられることも。
反抗的でそっけなくても、そんなお子さんを受け入れて「どんなときでも大切な存在だから、困ったことがあったらいつでも支えるからね」と伝えてあげましょう。
また反抗期でも、正しいことは正しいとたくさんほめて、ダメなことは毅然とした態度でダメだと教えることが大切です。
以下のポイントも意識してみましょう。
- 親以外にも子どもの相談相手を見つけておく
- アドバイスは押し付けがましくしない
- いつも愛情を伝える
- 日頃から子どもに意見を聞き、思考力を伸ばす
- 子どもを信頼する
- 適度な距離を取る
- 父親と母親で一緒に子どもを支える
7-7. HSC(エイチエスシー)の高校生の特徴は?日々を過ごしやすくする方法は?
高校生は、HSCでなくても人からどう見られているかを気にすることが多い年齢です。
そのためHSCのお子さんは、考えすぎてしまったり、人からの情報を敏感に感じとってしまったりします。
人を避けて、お昼休みの時間には1人で過ごすことも。
さまざまな情報を敏感に感じとるからこそ、1人で過ごしリフレッシュする時間も大切です。
お子さんの心に余裕がない様子が見られる時には、息抜き方法を一緒に見つけていきましょう。
7-8. 子どもの頃から何もしたくない様子が見られる。これはHSC(エイチエスシー)?
無気力な様子だけではHSCと判断できません。
ただしお子さんが無気力になっている原因は次のことが考えられます。
- 楽しいことや目標が見つからない
- 感情的に怒られてきた
- 自分で主体的に物事を選択してきた経験がない
- 結果だけをほめられてきた
上記のことから、自分に自信を持つことができず何をするにも無気力になっている可能性があります。
解決するための方法は以下の記事で解説していますので、参考にしてください。
こちらもCHECK
-
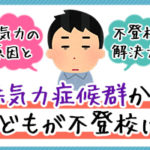
-
無気力症候群から子どもが不登校に?無気力の原因と解決法【高校生・中学生・小学生】
この記事を読むのに必要な時間は約 26 分です。 子どもが無気力症候群気味で不登校になってしまった。解決方法を知りたい。 子どもが無気力になった原因を探りたい。 お子さんが無気力な様子で不登校となった ...
続きを見る
7-9. 中学生の子どもが学校に何かストレスを感じている様子。どのような対応をしたらいい?
お子さんがストレスを口にして、相談してくれる場合は、「話すこと」「共感してもらうこと」でお子さんの気持ちが晴れることも。
「まずは話してみてね」といった雰囲気作りをしてみましょう。
ストレスがあっても、口に出せない場合は、「なにかつらいことがあったんだね」「どんな状況のときでもあなたが大切だからね」とお子さんの気持ちを受け入れて愛情を伝えることが大切です。
「親に悩みをうちあけて大丈夫なんだ」と思ってもらえるよう、話ができる信頼関係を構築していきましょう。
8. まとめ
HSCを不登校の原因にすることは、子どもの感性の否定です。
HSCが持つ敏感さ・繊細さは、生まれ持ったものであり、変えられるものではありません。
HSCは4大特性DOES(ダズ)が生まれつき備わっています。
D:深く処理する
O:過剰に刺激を受けやすい
E:全体的に感情の反応が強く、共感力が高い
S:ささいな刺激を察知する
DOESの特性により、HSCは“1を聞いて10を知る”を本能的に行えます。
ただ、感覚が敏感で物ごとや感情を深く処理できる分、HSCにとって学校は情報が多すぎる場所。
HSCの特性・特徴をポジティブに見てもらえない環境の場合、不登校になってしまいます。
もしも、HSCで不登校になった場合は、次の4つのポイントが再登校へのヒントです。
- スダチなどの専門機関へ相談してみる
- ネガティブな気持ちを吐き出させる
- 自己否定感を小さくする
- 自己肯定感を育てる
まずは、今まで溜め込んでいたネガティブな気持ち、自分を責める気持ちを小さくします。
その後、心の土台である自己肯定感を育むことで、HSCである自分を受け入れながら不登校を乗り越えられるのです。
9. 追伸:HSCで不登校の子どもを持つ親御さんと知り合えるチャンス
私たちはお子さんの不登校に悩む親御さんをサポートしており、定期的に【無料】不登校解決オンラインセミナーを開いています。
オンラインセミナーの参加者は、あなたと同じ、不登校の子どもを持つ親御さんです。
もしかすると、HSCの親御さんもいるかもしれません。
HSCが存在する割合は、5人に1人。
つまり、5人に1人はHSCの親です。
子どもの敏感さに悩んでいるのは、あなただけではないのです。
1回だけでいいので、【無料】不登校解決オンライン相談で不登校を解決する方法を知り、同じ悩みを持つ親御さんと気持ちを共有してみませんか?
<参考文献一覧>
エレイン・N・アーロン『ひといちばい敏感な子』(明橋大二訳)1万年堂出版(2015).
イルセ・サン『鈍感な世界に生きる 敏感な人たち』(枇谷玲子訳)ディスカヴァー・トゥエンティワン(2016).
長沼睦雄『子どもの敏感さに困ったら読む本:児童精神科医が教えるHSCとの関わり方』誠文堂新光社(2017).
長沼睦雄『敏感すぎて生きづらい人の明日からラクになれる本』永岡書店(2017).