この記事を読むのに必要な時間は約 38 分です。
「子どもが不登校になってしまった」
「文部科学省の調査からわかる子どもが不登校になる原因を知りたい」
「不登校に対する国の方針などを知りたい」
このような不安を抱えている親御さんは少なくありません。
お子さんが不登校気味のとき、不登校の原因やお子さんの心境を探るために正確なデータを知りたいと考える親御さんは多いです。
本記事では、不登校の原因などを文部科学省が発行している資料や統計などから細かく解説していきます。
不登校の定義や、小学校・中学校・高校ごとの学校に行きたくない理由などをまとめています。
文部科学省のデータからはわからない不登校になった根本原因についても解説いたします。
【平均3週間で不登校解決プログラム】を展開する小川涼太郎監修のもと、お話しする内容は次のとおり。
記事を読むとわかること
- 文部科学省の資料から読み解く:不登校の現状
- 文部科学省の資料から読み解く:不登校の原因
- 子どもの心境と根本的な原因
- 不登校を解決するために親御さんができる取り組み
- 文部科学省が定める不登校でも出席扱いになる場合のある機関
親御さんが抱える不安を解消できれば幸いです。
スダチでは、不登校になったお子さんを平均3週間で再登校に導いています。
学校嫌いで長期間不登校だったお子さんも学校復帰している実績がありますので、悩んでいる親御さんは、ぜひ一度ご相談ください!
\無料相談を申し込む/
1. 文部科学省の調査から読み解く:不登校の現状について
不登校の現状や実態など、さまざまな調査結果がありますが、今回は文部科学省が発行している資料や統計などから「不登校の現状について」詳しく読み解いていきます。
1-1. 文部科学省による不登校の定義は「年間30日以上の欠席」
文部科学省は、不登校のことを次のように定義しています。
「不登校児童生徒」とは「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」
引用:文部科学省「不登校の現状に関する認識」
お子さんが年間30日以上学校を欠席しているとき、不登校だと定義することができます。
しかし、上記に当てはまらず不登校気味のとき、何も対策を打たないでいると、そのまま欠席が増え不登校が長期化してしまいます。
そのため、以下の状況になった場合は、早めの対処が必要でしょう。
- 子どもが「学校へ行きたくない」と言い出した
- 遅刻や欠席することが増えた
- 朝体調不良を訴えることが増えた
1-2. 不登校の児童生徒数(人数)
令和4年10月に文部科学省が発表した不登校の人数は以下の通りです。
| 学校 | 児童生徒数 | 不登校児童生徒数 | 不登校児童生徒数の割合 | 不登校児童生徒数の前年度比 |
| 小学校 | 6,262,256人 | 81,498人 | 1.30% | 128.65% |
| 中学校 | 3,266,896人 | 163,442人 | 5.00% | 123.10% |
| 高校 | 3,014,194人 | 50,985人 | 1.69% | 118.43% |
参照:文部科学省「令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」
こちらの表を見てみると、不登校児童生徒の割合は中学校の5.00%が一番多くなっています。
しかし、どの学校も前年度から比べると、小学校、中学校、高校と全ての学校で不登校の子どもが増加していることがわかります。
1-3. 学年別で見る不登校の児童生徒数(人数)
| 学校 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
| 小学校 | 4,534 | 7,269 | 10,289 | 14,712 | 19,690 | 25,004 | 81,498 |
| 中学校 | 45,778 | 58,740 | 58,924 | 163,442 | |||
| 高校 | 12,474 | 11,887 | 8,764 | 440 | 17,420 | 50,985 |
参照:文部科学省「令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」
こちらの表を見てみると、学年が進むにつれて不登校の児童生徒数が増加していることもわかります。
高校では、学年が進むにつれて減少傾向にあります。
しかしここで注意していただきたいのは、高校では不登校となり退学する生徒も多いということ。
そのため、全体的に学年が進むにつれ不登校は増えると判断してよいでしょう。
1-4. 「隠れ不登校」「不登校傾向」の児童生徒はどれくらいいるのか?
前項で解説した人数は、年間30日以上欠席がある生徒となります。
しかし、30日以上欠席していなくても、欠席が多かったり、学校へいきたくないと訴える不登校気味の生徒はいます。
不登校傾向にある子どもの実態調査によると、年間欠席数が30日未満である不登校傾向の中学生は、約33万人もいることがわかりました。
これは、全中学生325万人の10.2%にあたります。
約10人に1人が「隠れ不登校」「不登校傾向」であることがわかります。
参照:文部科学省「不登校傾向にある子どもの実態調査」
こちらの記事では、不登校の実態について詳しく説明していますので、参考にしてください。
こちらもCHECK
-

-
不登校は何人に一人?人数や割合、増えすぎている実態は?小学生・中学生・高校生ごとに不登校になった子どもたちの今を知る!
この記事を読むのに必要な時間は約 25 分です。 「子どもが不登校になってしまった…実際のところ不登校の子どもは何人に一人いるのかを知りたい」 「不登校の子どもは増えている?割合や現状を知りたい」 不 ...
続きを見る
1-5. 文部科学省の調査からわかる不登校児への国の取り組み
令和元年に、「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」というものが各都道府県の教育委員長宛に通知されました。
そこに示されていた不登校児への取り組みの方針として
- 不登校支援では、必ずしも「学校に登校する」という結果のみを目標としない
- 児童生徒が自ら主体性をもって進路に向き合い、自立することを目指す
- 児童生徒によっては、不登校という期間が重要な休息期間でとなる場合があるが、不登校によって生じる勉強の遅れ、進路選択の不自由などのリスクを念頭に置く必要がある
と記されています。
つまり、学校は積極的に登校を促さない場合もあることがわかります。
子どもの自立を目指すとされていますが、お子さんがこの先社会で自立していくためには、いま目の前の不登校という課題を解決し、通常クラスへの再登校を果たすことが大切です。
そのため、親御さんが積極的に行動し、現状の課題を解決する必要があるでしょう。
2. 文部科学省の実態調査による子どもが不登校になった原因(きっかけ)【学年別の数値】
文部科学省が発表する小学校・中学校・高校ごとの子どもが不登校になったきっかけは次の通りです。
| 区分 | 小学校 | 中学校 | 高校 | ||||
| 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
| 学校に係る状況 | いじめ | 245 | 0.30% | 271 | 0.20% | 104 | 0.20% |
| いじめを除く友人関係をめぐる問題 | 5,004 | 6.10% | 18,737 | 11.50% | 4,623 | 9.10% | |
| 教師との関係をめぐる問題 | 1,508 | 1.90% | 1,467 | 0.90% | 249 | 0.50% | |
| 学業不振 | 2,637 | 3.20% | 10,122 | 6.20% | 3,176 | 6.20% | |
| 進路に係る不安 | 160 | 0.20% | 1,414 | 0.90% | 2,194 | 4.30% | |
| クラブ活動、部活動への不適応 | 10 | 0.00% | 843 | 0.50% | 400 | 0.80% | |
| 学校のきまり等をめぐる問題 | 537 | 0.70% | 1,184 | 0.70% | 422 | 0.80% | |
| 入学、転編入学、進級時の不適応 | 1,424 | 1.70% | 6,629 | 4.10% | 4,777 | 9.40% | |
| 家庭に係る状況 | 家庭の生活環境の急激な変化 | 2,718 | 3.30% | 3,739 | 2.30% | 859 | 1.70% |
| 親子の関わり方 | 10,790 | 13.20% | 8,922 | 5.50% | 1,731 | 3.40% | |
| 家庭内の不和 | 1,245 | 1.50% | 2,829 | 1.70% | 973 | 1.90% | |
| 本人に係る状況 | 生活リズムの乱れ、あそび、非行 | 10,708 | 13.10% | 18,041 | 11.00% | 7,610 | 14.90% |
| 無気力,不安 | 40,518 | 49.70% | 81,278 | 49.70% | 19,977 | 39.20% | |
| 左記に該当なし | 3,994 | 4.90% | 7,966 | 4.90% | 3,890 | 7.60% | |
引用元:文部科学省「令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」
小学生・中学生・高校生すべてで「無気力・不安」をきっかけに不登校となったことがわかります。
おこさんが無気力になったり、不安を感じるとき、お子さんの自己肯定感が低い場合がよくあります。
無気力がきっかけの不登校について、以下の記事で詳細を解説しているため、あわせてご確認いただけたら幸いです。
こちらもCHECK
-
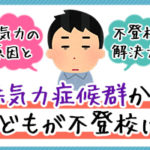
-
無気力症候群から子どもが不登校に?無気力の原因と解決法【高校生・中学生・小学生】
この記事を読むのに必要な時間は約 26 分です。 子どもが無気力症候群気味で不登校になってしまった。解決方法を知りたい。 子どもが無気力になった原因を探りたい。 お子さんが無気力な様子で不登校となった ...
続きを見る
以降の章では、無気力・不安に次いで多いきっかけを解説いたします。
学校ごとに異なる違いがあるため、お子さんが不登校になったきっかけを探ることができます。
2-1. 文部科学省による小学生が不登校になる原因(きっかけ)
小学生のお子さんが不登校になるきっかけとして多かったのは、次の問題です。
| 親子関係 | 13.2% |
| 生活リズムの乱れ・あそび・非行 | 13.1% |
| いじめ以外の友人関係の問題 | 6.1% |
特に小学生のお子さんは、育児においてまだまだ手のかかる時期です。お子さん自身も親御さんからのサポートをたくさん必要としています。
そのような時期であるからこそ、過保護になりすぎたり、もしくは放っておいたりすることにより親子関係が悪化しやすいです。
また、友人関係の問題は、学年が上がるごとに増える傾向にあるようです。
2-2. 文部科学省による中学生が不登校になる原因(きっかけ)
中学生のお子さんが不登校になるきっかけとして目立つのは、次の問題です。
| いじめ以外の友人関係の問題 | 11.5% |
| 生活リズムの乱れ・あそび・非行 | 11% |
| 学業の不振と親子関係 | 6% |
中学生になると、他人と比較した「自分」という存在に気づく時期です。
しかし、比較するだけで「自分の性格・長所」の分析までは行う子どもは少ないでしょう。
そのため中学生の人間関係では「周囲に同調する」ということが求められる空気感があります。
同調することにストレスを感じたり、もしくは他の子よりも目立つことから人間関係がうまくいかないという子どももいます。
また思春期であるからこそ、遊びや非行に走るお子さんも増える時期です。
2-3. 文部科学省による高校生が不登校になる原因(きっかけ)
高校生のお子さんが不登校になるきっかけとして多かったのは、次の問題です。
| 生活リズムの乱れ・あそび・非行 | 14.9% |
| 入学・転編入学・進級時の不適応 | 9.4% |
| いじめ以外の友人関係の問題 | 9.1% |
高校生になると、自分の将来について現実的に考え始める時期です。
自然と「自立」に向けて行動をはじめます。
そのため、親からの干渉を嫌ったり、もしくは親御さんも今まで以上に干渉しなくなる時期でしょう。
上記の時期であるからこそ、目の前の楽しさに没頭してしまい、あそびや非行に走る子どもも多いです。
非行に走ってしまう原因ややめてもらうためにどうすればいいかについては、次の記事でお話ししています。
こちらもCHECK
-

-
非行の根本原因は?非行の種類や統計データから見る現状、更生するためにできることを紹介
この記事を読むのに必要な時間は約 44 分です。 「子どもが言うことを聞かなくなり、非行に走っている。学校にも行っていないようだ。」 「注意をしても無視されたり、暴言を吐かれたりする。この状況をどうや ...
続きを見る
また、中学生のとき、自分の意思で学校を決めず親の期待に応えるために進学先を決めたとき、学校への不適応から入学してストレスを感じる子どももいます。
3. 文部科学省による不登校の原因を踏まえ子どもの心境を考察 |不登校になる根本的な原因とは
文部科学省の調査では、不登校になる原因を「学校」「家庭」「本人」と分類わけしています。
さらにそのきっかけは、細分化されています。一つの問題だけがきっかけだったり、子どもによっては複数の問題が絡みあったりして不登校となる場合もあります。
しかし、きっかけとなった問題は複雑であっても、根本原因を探ると、次のことにたどりつくケースが多いです。
「お子さんが親御さんからの愛情をうまく受け取れていないことによる自己肯定感の低下」
親御さんはお子さんに十分に愛情を注ぎ育児されていることと思います。
しかし時にお子さんがその愛情をうまく受け取れていない場合もあるのです。
例えば、親御さんが十分に愛情を注いでいらっしゃってもお子さんにうまく伝わっていないとき、お子さんは次の心境に陥り不登校になってしまうことがあります。
| 状況の例 | 子どもの現状と心境 |
| 子どもが大切だからこそ子どもを過度に管理 | ・親が先回りして行動してくれるため失敗したり考えて行動した経験がない
・親のいない学校で自分の言行に自信を持てず周囲と比較してしまう ・自分の考えに自信がないため問題が発生したとき困ってしまう |
| 子どもに自立してほしいからこそ放任主義 | ・自分は大切にされない人間だと捉え自己肯定感が低い |
| 子どもに将来成功してほしいからこそ期待している | ・親の期待していた結果を残せなかった時に激しく自己否定し無気力になる |
上記のように親御さんが十分に愛情を注いでいてもお子さんは異なる捉え方をしてしまうこともあります。
自己肯定感が低下した状態にあると、学校でなにかストレスや問題を抱えたときに、自分の力で乗り越えられずそのままストレスを避けるために不登校となってしまうのです。
お子さんが不登校になりやすいご家庭について次の記事にて解説しております。親御さんが注いでいる愛情がお子さんに伝わっているのか確認したいときには合わせて参考にしてください。
こちらもCHECK
-

-
不登校になりやすい子どもの親や家庭の特徴とは?小学生の事例をご紹介
この記事を読むのに必要な時間は約 35 分です。 お問い合わせ 不登校になりやすい子どもの特徴は? 子どもが不登校になりやすい親や家庭の特徴は? 本記事では、不登校になりや ...
続きを見る
お子さんが愛情をうまく受け取れていないとき、それは親御さんが悪いわけでは決してありません。
これからお子さんに伝わりやすい愛情の伝え方を知っていけば大丈夫です。
次の章では、お子さんの心の元気を回復し、再登校へ導くために親御さんがお子さんへできることを解説します。
また、「不登校になった今の子どもの心境を知りたい」「うちの子どもに合わせた愛情の伝え方を知りたい」そのような場合にはスダチにぜひご相談ください。
スダチでは、無料相談を実施しております。無料相談はオンラインで顔出し不要です。
もちろん1対1ですので、現状のお子さんの様子をお聞かせください。一緒に不登校解決に向けて取り組んでいきましょう。
\無料相談を申し込む/
4. 文部科学省の調査から見える不登校の原因を解決する方法【親御さんが子どもへできること】
ここでは、不登校を解決するために親御さんが子どもへできることを紹介していきます。
4-1. 不登校の子どもを支援する専門機関へ相談する
ここまで紹介してきた文部科学省の資料からわかるように、国は不登校解決に向けて積極的に取り組んでいるわけではありません。
しかし、これからお子さんが社会で幸せに生活していくためには、現状の不登校を根本的に解決することが最も大切です。
そのためには、親御さんが積極的に行動に移していく必要があります。
その際は、親御さん一人で解決しようとせず、専門機関の力を借りて二人三脚で前進していきましょう。
スダチでは、お子さんが不登校になったきっかけがわからないときにも、子どもの心境を紐解き、不登校の根本原因から解決しております。
スダチの支援を受けた子どもの中には、不登校が長期化してしまった子どももいましたが、みなさん平均3週間で再登校しています。
スダチの支援では、そのときの子どもの状況に合わせた最適な声かけ方法や接し方を親御さんへ指導させていただいております。
親御さんが日々フィードバックに基づき行動してくださることで、お子さんの心の元気が回復しみなさん主体的に再登校しています。
無料オンラインセミナー動画をご視聴いただいた方に、無料相談を実施中です。
オンライン相談であり、1対1で顔出しも不要です。ぜひ一度現状のお子さんの様子をお聞かせください。
\無料相談を申し込む/
4-2. 子どもと正しい親子関係を築き子どもの自己肯定感を育てる
子どもと正しい親子関係を築くことも大切です。
子どもが親の言いなりになっている状況、また子どもの言うことをなんでも聞き入れるような親子の立場が逆転している状況は好ましくありません。
正しい親子関係を築くポイントは次の通りです。
- お子さんの意見や考え方を否定せず受け入れて認める
→そのうえで正しい考え方を教える - ダメなことはダメだと毅然とした態度で教える
- 子どもが行動した良いことに目をむけてたくさん褒める
お子さんが親御さんを信頼するということは、自分が愛されていると実感することでもあり、愛着を形成することでもあります。
そして信頼できる親からたくさん褒められると、お子さんの自己肯定感がどんどん育ちます。
自己肯定感が育ったお子さんは、「学校の問題も自分なら乗り越えられる」と前進し始めます。
こちらの記事でも、学校復帰に向けて親ができる支援を紹介しています。参考にしてください。
こちらもCHECK
-

-
不登校児は29万人!登校拒否する児童が増加した原因と学校復帰に向けて親ができる支援
この記事を読むのに必要な時間は約 31 分です。 「うちの子どもが不登校になってしまった…」 「不登校児は全体でどのくらいいるのだろう?」 子どもが不登校になってしまうと、 ...
続きを見る
こちらもCHECK
-

-
先生が原因で不登校に…主な要因と対策方法【親にできることは?】
この記事を読むのに必要な時間は約 20 分です。 不登校の原因は実に様々で、その中に学校の先生が理由で不登校になるケースもあります。 子どもの不登校が改善せず、次のようなことに悩んでいませんか? 子ど ...
続きを見る
5. 文部科学省が定める「不登校でも出席扱い」になる選択肢
不登校でも次の機関を利用することで出席扱いになる場合もあります。
ただし出席扱いになるかの判断は、自治体により異なる点にはご注意ください。
また、この先お子さんが社会復帰してほしい場合は、目の前の問題である不登校を解決し通常クラスへの復帰を目指すことが1番でもあります。
しかし、次の機関は、通常クラスの仕様と大きく異なる場合がほとんどです。
そのため、お子さんが各機関での生活仕様に慣れてしまうと通常クラスへの復帰が難しくなる場合もあります。
「出席日数の獲得を優先すべきか」「それとも通常クラスへの復帰を第一に目指すべきか」お子さんの将来を考えたうえでご判断いただけたら幸いです。
5-1. フリースクール
フリースクールは、比較的少人数で過ごします。
それぞれが自由に過ごしたり、子ども中心の活動や学習のサポートなどを受けることができます。
文科省は、「一般に、不登校の子供に対し、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間の施設」と定義しています。
5-2. 適応指導教室(教育支援センター)
適応指導教室は、個別で学習支援を受けられる機関です。
スポーツや芸術、調理体験や自然体験など集団での活動もあります。
市町村の教育委員会が設置する場合がほとんどで、学校生活への復帰を目指し、学校内の空き教室や学校以外の場所に教室が設置されます。
5-3. 不登校特例校
不登校特例校は、これから徐々に増えていくと言われている学校です。
学校と同じように出席扱いになる教育機関で、個に合わせた学び方が徹底されています。
オンライン学習なども取り入れ、学校内の好きな場所や自宅などさまざまな場所で学習できるようなシステムがある学校もあります。
6. よくある質問
ここでは、不登校の原因についてよくある質問をまとめました。参考にしてください。
6-1. 文部科学省による不登校の原因1位は?
文部科学省の調査によると、小学校・中学校・高校全てで「本人の無気力・不安」がほとんどを占めます。
参照:文部科学省「令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」
ただし根本の原因をたどっていくと、お子さんが親御さんからの愛情をうまく受け取れていないことが不登校につながっている場合もあります。
6-2. 文部科学省の調査による不登校の推移は?
文部科学省の調査による不登校の推移を学校ごとにまとめました。
【小学校】
| 小学校 | 不登校数(人) | 不登校の割合(%) | 前年度比(%) |
| 平成24年度 | 21,243 | 0.31 | - |
| 平成25年度 | 24,175 | 0.36 | 138 |
| 平成26年度 | 25,864 | 0.39 | 107 |
| 平成27年度 | 27,583 | 0.42 | 106.6 |
| 平成28年度 | 30,448 | 0.47 | 110.4 |
| 平成29年度 | 35,032 | 0.54 | 115.1 |
| 平成30年度 | 44,841 | 0.7 | 128 |
| 令和元年度 | 53,350 | 0.83 | 119 |
| 令和2年度 | 63,350 | 1 | 118.7 |
| 令和3年度 | 81,498 | 1.3 | 128.6 |
【中学校】
| 中学校 | 不登校数(人) | 不登校の割合(%) | 前年度比(%) |
| 平成24年度 | 91,446 | 2.56 | - |
| 平成25年度 | 95,442 | 2.69 | 104 |
| 平成26年度 | 97,033 | 2.76 | 101.7 |
| 平成27年度 | 98,408 | 2.83 | 101.4 |
| 平成28年度 | 103,235 | 3.01 | 104.9 |
| 平成29年度 | 108,999 | 3.25 | 105.6 |
| 平成30年度 | 119,687 | 3.65 | 109.8 |
| 令和元年度 | 127,922 | 3.94 | 106.9 |
| 令和2年度 | 132,777 | 4.09 | 103.8 |
| 令和3年度 | 163,442 | 5 | 123.1 |
【高校】
| 高校 | 不登校数(人) | 不登校の割合(%) | 前年度比(%) |
| 平成24年度 | 57,664 | 1.72 | - |
| 平成25年度 | 55,655 | 1.67 | 97 |
| 平成26年度 | 53,156 | 1.59 | 95.5 |
| 平成27年度 | 49,563 | 1.49 | 93.2 |
| 平成28年度 | 48,565 | 1.46 | 98 |
| 平成29年度 | 49,643 | 1.51 | 102.2 |
| 平成30年度 | 52,723 | 1.63 | 106.2 |
| 令和元年度 | 50,100 | 1.58 | 95 |
| 令和2年度 | 43,051 | 1.39 | 85.9 |
| 令和3年度 | 50,985 | 1.69 | 118.4 |
引用元:文部科学省「令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」
6-3. 不登校が増えているのはなぜ?
主に3つの原因が考えられます。
- 家庭の状況の変化
- 親子のパワーバランスの逆転
- 家の中の居心地がよくなり過ぎている
不登校の子どもが増えている原因については、こちらの記事で詳しく説明しているので参考にしてください。
こちらもCHECK
-

-
【驚愕】なぜ不登校は増え続ける?どこでも語られていない真の事実とは?
この記事を読むのに必要な時間は約 18 分です。 今回は「なぜ不登校の人数は増え続けているのか?」というテーマでお話しいたしました。 まず、みなさんは不登校の人数が増え続けていることをご存知ですか? ...
続きを見る
7. まとめ
今回は、不登校の原因を文部科学省の実態調査を元に解説しました。
文部科学省の調査による不登校の主な原因は「本人の無気力・不安」がほとんどを占めます。
しかし、根本原因をひもといていくと、お子さんが親御さんからの愛情をうまく受け取れておらず、自己肯定感が低い状況にあることが原因の場合も多いです。
親御さんはお子さんに愛情をたくさん注いでいらっしゃることと思います。
そのため、この原因は、それは決して親御さんが悪いわけではありません。
お子さんに最適な愛情の伝え方、接し方をこれから知っていけば大丈夫です。
お子さんが不登校で苦しんでいるとき、そしてお子さんに伝わりやすい方法で愛情を伝え、お子さんに元気を取り戻してもらいたいご状況のとき、お子さんのために解決に向けて行動しましょう。
その際は、ぜひスダチの支援をご活用ください。
お子さんの状況を確認し、親御さんがお子さんへかけるべき言葉、そして行動方法をしっかりアドバイスいたします。
無料オンラインセミナー動画をご視聴いただいた方に、無料相談を実施中です。
オンライン相談で、1対1で顔出しも不要です。ぜひ一度現状のお子さんの様子をお聞かせください。
\無料相談を申し込む/






