この記事を読むのに必要な時間は約 34 分です。
「うちの子どもが不登校になってしまった…」
「不登校児は全体でどのくらいいるのだろう?」
子どもが不登校になってしまうと、親御さんは不安になって当然です。
文部科学省のデータによると、不登校児の統計人数は29万人。少子化が進み、子どもが減っているにも関わらず不登校児は年々増えている状態です。
【平均3週間で不登校解決プログラム】を展開する小川涼太郎監修のもと、お話しする内容は次のとおり。
記事を読むとわかること
- 不登校児が増加し続けている原因
- 不登校児が登校拒否する理由
- 不登校児が再登校を目指すために親御さんができること
- 学校復帰までの流れ
なぜ不登校児が増えているのか、再登校に導くまでのプロセスを解説します。
スダチでは、不登校になったお子さんを平均3週間で再登校に導いています。
不登校を長期化させず、早めに解決したいと考えている親御さんはぜひ一度ご相談ください!
無料オンライン相談は、1対1で顔出しも不要です。ぜひ一度現状のお子さんの様子をお聞かせください。
\無料相談の申し込みをする/
1. 不登校児が増加し続ける原因【文部科学省による不登校児の統計人数は29万人】
病気や経済的な理由以外で、年間欠席30日の生徒を文部科学省は「不登校児童生徒」と定義しています。学校に行けなくなった子どものことを「不登校」「不登校児」と呼んでいます。
令和3年の文部科学省データによると、小学生から高校生の不登校児の統計人数は29万5925人。
前年度と比べて5万6747人の不登校児が増加していています。
参考:令和3年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について
参考:東京学芸大学学内こどもの学び困難支援センター「令和3年度の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」結果が公開されました。」
1年間で5万人以上の不登校児が増加している原因について解説します。
1-1. 不登校の児童にとって学校が息苦しい場所になっている
1つ目の原因としてあげられるのが、年々学校が息苦しい場所になっていることです。
SNSなどでよく見かける炎上は、本当に悪いことをしているものもあれば賛否両論のものもあります。社会全体が「正しいこと」を求める風潮にあるため、それが学校にも影響しているように感じます。
学校の先生たちは生徒を管理するときに「●●さんは非常によく頑張っていました!」などと模範意識を強めるようなことを言う場合もあります。
とある学校では「チャイム着席運動」という、チャイムが鳴り終わる前に生徒は椅子に着席しているというルールを作っている場合もあります。これを行うと自分自身をコントロールできるため成績が伸びると生徒に話していたりします。
これから大人になり社会に出ると、自分自身をコントロールすることや、目標となる人物を超えられるよう努力し続けることはたしかに大切なことです。
しかし、このような模範意識を押し付けてくること、全員でやらなければならないという同調圧力や、競走しなきゃいけない環境に息苦しさを感じている子どももいます。
その息苦しさに耐え切れずに登校拒否をする場合もあります。
1-2. 児童同士のトラブルを管理しきれなくなっている
学校側が児童同士のトラブルを管理しきれなくなっていることも原因の1つです。
今までは、児童同士のトラブルは学校で起きていたので、先生や学校全体で注意や管理し、時には親御さんを含めて解決し、不登校を未然に防げたケースもありました。
しかし、最近ではSNSを使った児童同士のトラブルが多く存在しています。
SNSなどのトラブルは水面下で行われていることもあり、学校や親がトラブルを把握するのに時間がかかってしまう状況です。
SNSを使ったトラブルが増えて、学校が管理しきれてないことも不登校児が増えている原因の1つです。
1-3. 学校に行かせる方が悪化すると親の認識が変わった
文部科学省が不登校児の統計を始めた1966年の頃から、登校拒否をする児童はいました。
しかし当時は、「学校に来たくないなんて甘えだ」という認識が強かった時代でもあるので、無理に学校に連れて行く親御さんが多かったようです。
最近では、「子どもの事を考えて一度休ませる」という認識に変わってきています。これも、不登校児が増加した理由の1つです。
しかし、これは悪いことではありません。
親御さんがお子さんの気持ちを受け入れ、認めている傾向にあることがわかります。
子どもの気持ちを尊重し受け入れてあげたら、次は不登校解決に向けて親御さんが行動していくことが大切です。
1-4. 学校だけでは不登校の児童を支援しきれない
実は、学校では不登校児を支援しきれない状況です。
子どもが不登校になって、担任の先生や校長先生などに相談したとき「まずはお子さんの様子を見ましょう。落ち着いたら来てくださいね。」と言われ何もしてもらえないケースもあります。
その理由は、文部科学省から「不登校児を無理に学校に戻すのではなく、将来的に社会復帰できるように」と指導されているためです。
先生たちは必死になって不登校児を学校に戻すことができません。
このことから、学校だけでは不登校児の支援をしきれない状況です。
こちらの記事では、不登校の原因を文部科学省の実態調査から徹底解説しています。ご参考にしてください。
こちらもCHECK
-

-
不登校の原因を文部科学省の実態調査から徹底解説【2023年4月最新情報】
この記事を読むのに必要な時間は約 36 分です。 「子どもが不登校になってしまった」 「文部科学省の調査からわかる子どもが不登校になる原因を知りたい」 「不登校に対する国の方針などを知り ...
続きを見る
2. 不登校児の心理状況【登校拒否をする理由】
ここでは、不登校児が登校拒否する理由について詳しく解説していきます。
お子さんが不登校になるきっかけは、さまざまな要因が複雑に絡み合っている場合が多いです。
以下の記事では、不登校のお子さんの心境と傾向を7つのタイプに分けて解説しています。
お子さんが今どのような気持ちを抱えているのか探る際の参考にしていただけたら幸いです。
-

-
参考不登校になったら親がやるべき3つのこと|不登校の7つのタイプと今の子どもの状態・解決法
この記事を読むのに必要な時間は約 87 分です。 「子どもが不登校になってしまった…子どもにどう接していけば良いのかわからない」 「子どもの今の状態に適した対処方法を知って、不登校を解決したい」 お子 ...
続きを見る
2-1. 不登校児が登校拒否をする理由①人間関係がうまくいっていない
学校での人間関係が上手く築けていないと、登校拒否につながります。
子どもたちは1日のほとんどを学校で過ごしているため、さまざまな人と関わることになります。時には波長が合わず人間関係がうまくいかない人と出会うこともあります。
また、実は仲の良い人が誰もおらず1人で過ごしているのかもしれません。
中学生の場合は教科によって担当の先生が異なるため、担任の先生との関係も希薄になりがちです。
学校での人間関係のトラブルで何か困ったことがあったときに気軽に相談できる大人もいないため、長い間人間関係のトラブルを抱え続けることになってしまいます。
長期間ストレスを感じたことを機に登校を拒否していることも考えられます。
2-2. 不登校児が登校拒否をする理由②いじめを受けている
いじめを受けているから学校に行きたくないという子は少なくありません。
暴力的なものだけでなくても、陰口や嫌がらせなど、大人から見えにくいいじめを受けているケースも多く、SNSトラブルも考えられます。
いじめを受けた子どもは酷く傷ついており、自己肯定感も下がり切っている状態です。
まずは、お子さんがつらい気持ちを今まで我慢してきたことを認めて褒めて、自己肯定感を育てることに注力しましょう。
いじめが原因で不登校になった場合の支援方法は、こちらの記事で詳しく解説しています。
こちらもCHECK
-
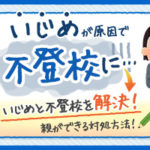
-
いじめが原因で不登校に!不登校を解決するために親ができる対処方法
この記事を読むのに必要な時間は約 34 分です。 子どもがいじめられて不登校になってしまった…どう接したらいいの? いじめと不登校を解決する方法を知りたい。 お子さんがいじめから不登校に ...
続きを見る
2-3. 不登校児が登校拒否をする理由③勉強についていけない
進級・進学すると学習内容ががらりと変わります。
それによって勉強でつまずいてしまう子は少なくありません。一度つまずいてしまうと他のところもわからなくなってしまい、勉強へのモチベーションが下がってしまいます。
また、成績が悪い状態が続いていると「自分は何をやってもダメなんだ」と感じ、学校生活がつらいものとなってしまいます。
結果として勉強についていけないことが登校拒否につながる場合もあります。
2-4. 不登校児が登校拒否をする理由④生活リズムの乱れ
生活リズムの乱れも登校拒否の理由の1つです。
例えば、夜更かしをしてしまった日の朝は学校に行きたくないと思ってしまうのは当然のこと。
夏休みなどの長期休み明けは不登校が増加する傾向にあるため、生活リズムを整えることは非常に大切です。
2-5. 不登校児が登校拒否をする理由⑤朝になると具合が悪くなる
十分に睡眠をとっているのに、朝になると頭痛、めまい、吐き気、動悸などの症状が出る子どもは、学校に行くことに大きなストレスを感じている可能性があります。
体調不良を訴える場合、休ませることしかできないので欠席が増えて不登校になることも。
病気が隠れている場合も中にはありますが、学校へ行きたくないという気持ちから不調を感じている場合もあります。
朝になると不調を感じ不登校気味のお子さんが再登校するための行動方法は次の記事で解説しています。
こちらもCHECK
-

-
学校へ行く前腹痛や吐き気を感じる高校生・中学生の原因とは|不登校の解決方法
この記事を読むのに必要な時間は約 34 分です。 学校へ行く前体調不良を訴えることが増えた 何か病気なのかしら? どうやって解決すればいいの? 結論を申し上げると、学校へ行く前の体調不良 ...
続きを見る
また、学校にストレスを感じていることが大きな原因になっている可能性もあります。学校で感じるストレスについてはこちらの記事で詳しく紹介しています。
こちらもCHECK
-
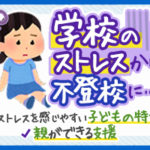
-
【学校のストレスで不登校に】ストレスを感じやすい子どもの特徴と親ができる支援
この記事を読むのに必要な時間は約 28 分です。 「学校のストレスから不登校になってしまった…もう学校復帰は難しい?」 「子どもが学校で何かストレスを感じているようだ。このまま不登校にな ...
続きを見る
3. 不登校児が再登校を目指すために親のできる支援
お子さんが不登校児になっても、前述した通り学校は必死になってサポートはしてくれません。
親御さん自身がお子さんの不登校解決に向けて行動することが大切です。
親御さんの行動や声かけを変えるだけで、お子さんの不登校は解決できるので大丈夫です。前進するためにやるべきことをご紹介します。
3-1. スダチなどの専門機関に相談する
再登校に導くためには親御さん1人で悩まずに、スダチのような専門機関に相談することが1番の近道です。
スダチでは、今までに数えきれないほどの不登校のお子さんを再登校に導いてきました。
不登校になったきっかけはお子さんによりさまざまですが、親御さんとお子さんが正しい親子関係を築き、お子さんの自己肯定感が満たされることで、みなさん平均3週間で再登校が叶っています。
お子さんの自己肯定感を育て、お子さんが主体的に再登校できるようサポートさせていただきます。
無料オンラインセミナー動画をご視聴いただいた方には、無料オンライン相談を実施しております。1対1で顔出しも不要です。ぜひ一度現状のお子さんの様子をご相談ください!
\無料相談を申し込む/
3-2. 児童や自分自身を責めない
不登校児は、「学校に行かない」のではなく「行けない」状態です。
「どうして学校に行かないの!みんなは学校に行ってるのに!」
「サボってばかりいないで学校に行きなさい!」
そういった言葉をかけるとお子さんを追い詰めてしまうだけでなく「この親は自分の気持ちをわかってくれず信用できない。」と信頼関係まで失ってしまいます。
まずは不登校のお子さんが感じているつらい気持ちを受け止めて「どんな状況でも大切な存在」ということを、子どもに伝えてあげましょう。
また、親御さんも自分自身を責めすぎないでくださいね。
「私の育て方が悪かったから…」
「私がもっとちゃんとしていれば…」
親御さんがそんな風に不安に思っていることは、子どもは敏感に感じ取ってしまいます。
一緒に乗り越えていこう、というポジティブな感情でお子さんと接してあげてください。
3-3. 正しい親子関係を築く
正しい親子関係が築けていないと、子どもは不登校になった理由を親には話してくれません。逆に、不登校児が反抗したり、反発的な態度をとってきたりする可能性もあります。
そんな状態では、どんなに良い言葉をお子さんにかけてもお子さんの元に届きません。
まずは、正しい親子関係を築くことに力をいれましょう。
正しい親子関係とは、お子さんが親御さんを信頼し、尊敬できる状態であること。
- 不登校児であるお子さんを受け止める
- 結果ではなく、過程を褒める
- 正しいことをしたらたくさん褒める
- ダメなことはダメだと毅然な態度をとる
このようなことを意識して、信頼関係を構築していきましょう。
3-4. 学校以外の居場所を作ってあげる
学校に行けない不登校児は、あまり外に出ようとしません。人と関わることを避けたり、家族以外の人との交流を嫌がったり、外に出ることさえ拒む場合もあります。
そんな状態が続いてしまうとひきこもりになる可能性もあるので、学校以外の居場所を作ってあげることが大切です。
子どもが仲の良い友人や、親戚などに協力をしてもらって他者との関わりを作ることも非常に大切です。
家以外の場所で成功体験が増えることで自己肯定感が育つことにもつながります。
「学校に行っても意外と大丈夫かも」と気持ちがシフトするきっかけとなります。
4. 登校拒否をする不登校児が学校復帰するまでの流れ
ここからは、不登校児が学校復帰するまでのプロセスを解説します。
不登校には4つの期間があり、お子さんの心境は移り変わります。
自分の子どもがどの期間なのかを見極めつつ、適切なアプローチをしましょう。
4-1. 「不安定期」は子どもが安心できるように
不登校になりたての「不安定期」は、子ども自身が心身共に疲れ切っていて、心の元気を完全に失っている状態です。
お子さんは不登校になった罪悪感を抱いていて、家族にすら恥ずかしい・申し訳ないという気持ちでいっぱいになっている、ネガティブな状態です。
この状態の子どもには、親御さんの言葉は届きにくいです。不登校のきっかけとなった出来事も聞き出すことが難しいでしょう。
「学校で何かつらいことがあったんだね。どんなときも味方でいるから大丈夫。」
と、お子さんを安心させられるような声掛けをしましょう。
お子さんが安心すると、何か話してくれるようになります。
そうなったら、お子さんの言葉をしっかりと聞いてあげましょう。
4-2. 「安定期」は子ども主体に動く
子どもが心の元気を少しずつ取り戻し、「何かしたい」と思えるようになるのが「安定期」です。
ほとんどのお子さんは「勉強したい」ということが多いです。
学校には行けないけれど、それでも勉強は遅れてはいけないと分かっているからでしょう。
勉強しやすい環境を作ったり、家庭教師などを雇ったり、子どもの気持ちが前進していくよう環境を整えてあげましょう。
また、家事の手伝いなどもしてくれるようになったら、買い物などで外に連れ出すのもおすすめです。
この時注意したいのが「押し付けないこと」です。
あくまでお子さん主体で、お子さんがしたいことをさせてあげてください。勉強したいからといってどっさりドリルを購入してきたり、高校のパンフレットを持ってきたりなどは、お子さんへのプレッシャーになってしまうので注意しましょう。
4-3. 「停滞期」がある場合は外部に相談
安定期から、そのまま再登校につながるケースが多いです。
しかし、そうではない場合もあります。
気持ちが安定し、何かする力も出てきたのに学校に行くことができない状態は「停滞期」にあたります。
「どのような声かけをしたら学校へ行けるようになるのだろう」「子どもが一歩前進できるようなサポートをしたい」その場合は、スダチにご相談ください。
現状のお子さんの気持ちに合わせた適切な声かけや、親御さんが行うべき行動方法をお伝えします。
スダチでは、無料オンライン相談を実施しております。1対1で顔出しも不要です。ぜひ一度現状のお子さんの様子をご相談ください!一緒にお子さんの今の心境を紐解いていきましょう。
\無料相談を申し込む/
4-4. 「回復期」には学校復帰ができるようになる
回復期になると、お子さんは「学校に行こうかな」と言い出します。
そうなったら、学校復帰に向けてスモールステップでできることを増やしましょう。
- 学校に行く時間に起きてみる
- 制服に着替えてみる
- 学校と同じスケジュールで勉強してみる
再登校がうまくいかなければ、お子さんの心にまた大きなダメージを与えてしまいます。
そうならないようにスモールステップで練習します。また、親御さんは学校に連絡しておきましょう。学校との連携も非常に重要になります。
5. 登校拒否をする不登校児についてのよくある心配事
ここでは、不登校児のお子さんを持つ親御さんから、よく質問されることについて回答していきます。
5-1. 文部科学省が定義する不登校児とは?
文部科学省では、以下のように定義しています。
「不登児校童生徒」とは「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義しています。
病気や経済的な理由以外で、年間欠席30日の生徒を「不登校児」と定義しています。
5-2. 中学生が不登校になったらどうなる?
中学生が不登校になると、欠席が多い状態が続く場合高校受験に影響が出てしまいます。
ただし全日制高校をあきらめなくてはならないわけではありません。中学生で不登校でも進学できる高校の選択肢は複数あるため大丈夫です。
公立高校の場合は欠席の日数が決まっていますが、私立高校であれば欠席日数が多い場合でも受験・合格することができます。
その他にも、通信制、定時制の高校に通うという選択肢もあります。
不登校児の進学については、こちらの記事で詳しく解説しています。
こちらもCHECK
-
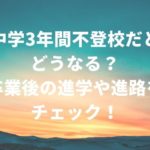
-
中学生の3年間不登校だとどうなる?卒業後の進学や進路をチェック!
この記事を読むのに必要な時間は約 56 分です。 中学3年間不登校だとどうなってしまうの? 3年間不登校のとき、高校やこの先の進路はどうなるの? 結論から申し上げると、中学の3年間不登校 ...
続きを見る
5-3. 不登校の人、不登校になる子の特徴は?
不登校になってしまった人の特徴としては、自己肯定感が下がり切っていて自分に自信がない状態です。
不登校になる子どもの特徴には、
- 主張が強すぎる(対人関係)
- 人にどう思われているかが気になる(対人関係)
- 親へのわがままが多い(家庭環境)
- 朝、寝起きが悪い・夜寝るのが遅い(家庭環境)
- 何をするにしても気力が出ない(本人の気持ち)
などがあります。
不登校になりやすい子どもについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
こちらもCHECK
-

-
不登校になりやすい子どもの親や家庭の特徴とは?小学生の事例をご紹介
この記事を読むのに必要な時間は約 35 分です。 お問い合わせ 不登校になりやすい子どもの特徴は? 子どもが不登校になりやすい親や家庭の特徴は? 本記事では、不登校になりや ...
続きを見る
5-4. 不登校になりやすい家庭はありますか?不登校にならない対策は?
不登校になりやすい家庭の特徴としては、以下のようなものがあります。
- 子どもを感情的に怒りすぎる(非難タイプ)
- 子どもを叱らず甘やかしすぎる(甘やかしすぎるタイプ)
- 子どもへの干渉が強すぎる(過干渉タイプ)
- 子どもへの興味が無さすぎる(放任タイプ)
- 子どもにルールを課しすぎる(条件付けタイプ)
上記に当てはまると、お子さんの自己肯定感が下がりやすく不登校になりやすいため親御さんはすぐにやめましょう。
不登校にならないようにする対策として、正しいときにはお子さんをたくさん褒めて、ダメなことは毅然とした態度でダメと教え、正しい親子関係を構築することが大切です。
5-5. 不登校は「甘え」「ずるい」と言われたのですが…
不登校は甘えでもずるいと言われるものではありません。
子ども自身、「学校へ行かなきゃいけないのにいけない」と悩み苦しんでいます。
また、不登校は恥ずかしいものや怠けていると捉えられるものではありません。お子さんがこれから成功していくための一つの人生の通過点に過ぎません。
ここで不登校を乗り越えると、お子さんはこれからどんどん成長します。成長のための大切な通過点だと捉え、親子で前進していきましょう。
5-6. 子どもが不登校なのですが、フリースクールに通わせた方がいいですか?
お子さんが不登校になっている親御さんから、このような相談をよく受けますが、スダチではフリースクールをおすすめしていません。
なぜなら、フリースクールは「自分のやりたいことをやろう」という趣旨の場所で、登校時間も決められていませんし、勉強時間などありません。
全日制の高校受験や大学受験などの選択肢がなくなってしまいます。
お子さんにやりたいことがあって、それを突き詰めたい!などの目的があれば別ですが、そうでない場合は、再登校を目指すことがおすすめです。
スダチにご相談いただければ、再登校までしっかりとサポートいたします!
6. まとめ
今回は、不登校児が増加している原因と親御さんができる支援について紹介しました。
不登校児が増加している原因は、以下の通りです。
- 学校が息苦しい場所に変わってきている
- 児童同士のトラブルが管理しきれなくなっている
- 学校に行かせることが逆に不登校を悪化させるという考えに変わった
- 学校だけでは不登校支援がしきれない
今後も不登校児は増加するでしょうが、親御さんがしっかりサポートすれば再登校につなげられます。
スダチのような専門機関を頼ることも、再登校の近道になります!
スダチでは、不登校になったお子さんを平均3週間で再登校に導いています。
不登校を長期化させず、早めに解決したいと考えている親御さんはぜひ一度ご相談ください!
\無料相談を申し込む/






