この記事を読むのに必要な時間は約 29 分です。
「子どもが不登校になってしまった場合、復学のためにどのようにサポートすればよいのか知りたい。」
「子どもが不登校になる前に、不登校から学校復帰するまでのプロセスや、それに必要な支援について知りたい。」
このような不安を抱えている親御さんは少なくありません。
子どもが不登校を乗り越え、学校復学を成功させるためには、親御さんのサポートが欠かせません。
今回は、不登校から学校に復学するための段階や、親御さんができるサポート方法についてお伝えします。
【平均3週間で不登校解決プログラム】を展開する小川涼太郎監修のもと、お話しする内容は次のとおり。
記事を読むとわかること
- 不登校の解決法
- 不登校からの復学には段階ごとの対応を
- 現在の不登校支援の目的
- 不登校からの復学や自立を目指せる相談機関
- 復学や自立に向けた相談・指導の効果
- 不登校の復学に向かうきっかけ例
スダチでは、不登校になったお子さんを平均3週間で再登校に導いています。
お子さんへの声かけや接し方を少し変えていただくだけで、お子さんは主体的に再登校を果たしています。
さらにみなさん、学校でも問題を主体的に乗り越えられるように成長なさっています。
子育てに悩んでいる親御さんは、ぜひ一度ご相談ください!
\無料相談を申し込む/
1. 不登校を解決し復学するための方法【知っておくべき前提知識】
不登校になってしまった子どもの問題を解決して、復学するための方法を紹介していきます。
知識のない状態でお子さんを見守り続けてしまうと、不登校が長期化して取り返しのつかないことになってしまう場合もありますので、事前にきちんと確認しておきましょう。
1-1. 「根本原因」と「きっかけ」を理解する
お子さんが学校を行き渋るには必ず「原因」と「きっかけ」があります。
不登校の問題を解決していくためにはまず親が不登校の「原因」と「きっかけ」を明確にして、お子さんが学校へ行けなくなったメカニズムを知ることが大切です。
根本的な原因は、親御さんからの愛情がお子さんへうまく行き届いていないことにあることも多いです。
親御さんの愛情をうまく受け取れていない子どもは、
- 自分なんてどうでもいい存在なんだ
- 私は何をやっても怒られてばかり
- 親が全て対応してくれるから親がいないときの自分に自信を持てない
と自己肯定感の低い状態となり、学校で何か問題が発生したときにうまく解決することができません。
そしてそのまま不登校になってしまう場合があります。
しかし、これは親御さんが悪いわけではありません。
親御さんはお子さんのことを大切に思い、愛情をたくさん注いで育児をなさっていることと存じます。
その愛情をお子さんがうまく受け取れていないということはよくあることなのです。
現状の日本ではお子さんに伝わりやすい方法の愛情の伝え方を教えてくれるような機関がありません。
また、共働きしている世帯も多く、どうしてもお子さんとの時間を作れないご家庭も多いためです。
ちなみに、お子さんの自己肯定感が低い状況のとき、次のことがきっかけとなり、不登校につながることが多いです。
| 環境的要因 | 子どもを取り巻く環境(友達関係・教師との不和・学校の場所や登校経路など) |
| 性格的要因 | 本人の性格傾向や、自立心、社会性などが学校社会に不適応を起こしてしまっている |
1-2. 文部省が定める不登校支援は復学を目的としていないことを知る
文部科学省の通知では、「不登校児童生徒への支援は、『学校に登校する』という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要がある」としています。
国の方針としては、
- 不登校支援では、必ずしも「学校に登校する」という結果のみを目標としない
- 児童生徒が自ら主体性をもって進路に向き合い、自立することを目指す
- 児童生徒によっては、不登校という期間が重要な休息期間となる場合があるが、不登校によって生じる勉強の遅れ、進路選択の不自由などのリスクを念頭に置く必要がある
というものです。
引用元:文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」
つまり、不登校の子どもに対して、学校は積極的に登校を促さない場合があります。
そのため、不登校の子どもの復学を目指すのであれば、親御さんが積極的に行動し、現状の課題を解決する必要があります。
1-3. 正しい親子関係の構築と子どもの自己肯定感を育てることがカギ
お子さんが不登校になっている現状として次の状態が考えられます。
- 親からの愛情をうまく受け取れていない
- 子どもの自己肯定感が低い状況
親御さんが心からお子さんを大切に思っている愛情をうまく伝えるためには、正しい親子関係を構築していく必要があります。
正しい親子関係を構築するポイントは以下の通りです。
- 良いところに目を向けてたくさん褒める
- ダメなことはダメだと毅然とした態度で教える
- 子どもが取り組んだことの結果ではなく過程を見て褒める
信頼できる親からたくさん褒められることによって、子どもの自己肯定感が育っていきます。
そうすると、「自分なら問題も乗り越えられる」「信頼できる親がいるから前に進んで大丈夫」と、子ども自身で不登校を乗り越えられるようになります。
正しい親子関係の構築を目指しましょう。
2. 不登校から復学に向けた段階ごとの子どもの心境と対応方法
お子さんが不登校のとき、心境はつねに移り変わっていきます。
お子さんが今どんな心境なのかを探ることによって、適切な対応方法や声かけを探るヒントとなるでしょう。
ここでは、不登校になったお子さんの移り変わる心境を紐解きます。
2-1. 不登校の段階➀「初期」の特徴
不登校になってから1〜3週間ほどの初期の段階では、子どもは心理的に不安定になることが多いです。
具体的には次のような心理状態となっています。
- 病気でないのに学校を休んでしまう罪悪感
- 「どうして学校に行かないの?」と聞かれる恐怖
- いじめや仲間外れなど学校での嫌なことのフラッシュバック
- クラスで何と思われているだろうという不安
- 自分でもどうして学校にいけないのかがわからなく自己肯定感が著しく喪失 など
不登校になってしまった現実をうまく受け入れられずに、不安に襲われている状況です。
2-2. 不登校の段階➀「初期」の対応方法
不安定な心理状態の子どもに対して、親御さんには以下のような対応が求められます。
①子どもを受け入れてあげる
学校でつらいことがあった心境や、今の子どもの気持ちを受け入れて尊重してあげることが大切です。
「学校でつらいことがあったのに、頑張っていたんだよね」とお子さんが頑張ってきたことを褒めてあげてください。
子どもが頑張ってきたことを認めてあげましょう。
②不登校であることは積極的に肯定しない
一度は気持ちを受け入れて休ませてあげることも大切ですが、休むことを当たり前にするのはおすすめできません。
親御さんが学校を休むことを全肯定してしまうと、「学校なんて行かなくていいんだ」と子どもが認識して、復学が難しくなってしまいます。
「これから一緒に解決する方法を探そう!」とお子さんと同じ視点に立ちお子さんが前進できるような声かけをしましょう。
2-3. 不登校の段階②「中期」の特徴
不登校が長引きはじめると、お子さんは自分の状況を受け入れるようになり、「無理に学校に行かなくてもいい」と思っていることが多いです。
精神的に安定していて、学校に関わらないことであれば、親御さんのお手伝いなど普通の生活を送ることもできます。
この時期の子どもの心理状態は以下の通りです。
- 少しずつ学校や勉強、自宅外のことに興味が出てくる
- 家族のお手伝いなどを積極的に取り組むようになる
- 「そろそろ学校に行かないとまずいかな」と自分を客観的に見れるようになる
- 少し精神的に余裕が生まれ、自分以外の人のことが気になってくる など
精神的に安定してきているので、きっかけさえあれば、学校のことを考えることもできます。
2-4. 不登校の段階②「中期」の対応方法
精神的に安定し始めた時期には、親御さんの対応で復学まで導いてあげることも可能です。
具体的には以下のような対応が必要となってきます。
①家庭で取り組んでくれたことを褒める
手伝いなどに積極的に取り組んでいる際は、子どもが行動した過程をみてたくさん褒めてあげましょう。
自分がおこなったことの過程を褒められることでお子さんの自己肯定感が育ちます。
自己肯定感が育つと、「学校の問題も乗り越えられそうだな」とお子さんが前へ進むきっかけとなります。
②子どもをよく観察する
子どもが精神的に安定してくると、学校のことを気にするタイミングがあります。
学校のことを気にし始めたら、子どもの状態をみながら学校に行けなくなったきっかけや、これからどうしたいかなど子どもの気持ちをたくさん聞いてあげましょう。
「何があってもあなたが大切で味方だから大丈夫」と愛情を伝え子どもが安心して前へ進めるように声をかけてあげましょう。
2-5. 不登校の段階③「後期」の特徴
そのまま不登校が長引いていると、再度気持ちが不安定になり、停滞気味の状況となります。
学校に行けない自分を受け入れることができたけれど、漠然とした将来の不安や想像していた自分の将来との今のギャップに苦しむようになり、自己肯定感が下がってしまいます。
そのような時期の子どもの心理状態は以下の通りです。
- 「どうせ自分なんか」という自己嫌悪
- 「自分は必要な人間じゃない」という自己肯定感の低下
- 「生きていてもしょうがない」という自己否定
- 「こんな風になったのは親のせいだ」という責任転嫁など
再び、心理的に不安定になってしまい、自己肯定感が低くなってしまったことで、自分を否定するような状態が目立ってきてしまいます。
2-6. 不登校の段階③「後期」の対応方法
再び気持ちが不安定になってしまった子どもには以下のような対応が求められます。
①生活リズムの改善とデジタル端末への依存を克服
不登校が長引いている時、子どもは家庭で好きなことをして過ごすことが多くなります。
その際、ゲーム依存、スマホ依存に陥っているお子さんは非常に多いです。
ゲームを行うことで達成感を感じたり、また現状の問題を忘れようとしている傾向があります。
時間を忘れて夜中までデジタル端末を触る状況が続き、昼夜逆転してしまう子どもも少なくありません。
生活リズムを改善しないことには、復学が難しいだけでなく、健康的な生活を送ることができません。
まずは、生活リズムを整えることや、デジタル端末への依存を克服することから取り組む必要があります。
こちらもCHECK
-

-
中学生不登校のスマホゲーム依存に対して親ができる対処方法|スマホゲーム依存症になる原因と健康被害
この記事を読むのに必要な時間は約 24 分です。 「不登校の中学生が毎日スマホゲームばかりやっている…これは依存症?」 「スマホを手放すのを嫌がる…どのように対処したらいい?」 不登校の ...
続きを見る
②専門機関に相談して早めに対処をする
不登校が長引き、デジタル端末などの依存に陥っていると、そのまま引きこもりになってしまう恐れもあります。
親御さんのサポートだけでは、復学が難しいケースもあるため、専門機関の力を借り二人三脚で不登校を解決することが大切です。
スダチでは、不登校が長期化してデジタル依存に陥っていたり、ご家庭で暴れてしまったりするお子さんも再登校へ導いています。
お子さんと親御さんの信頼関係を今以上に深め、そしてお子さんの自己肯定感が育つ接し方や声かけをサポートしております。
お子さんの自己肯定感が育つと、お子さんは自然と主体的に再登校を果たします。
無料オンラインセミナー動画をご視聴いただいた方に、無料相談を実施中です。
オンライン相談であり、1対1で顔出しも不要です。ぜひ一度現状のお子さんの様子をお聞かせください。
\無料相談を申し込む/
3. 不登校からの復学や自立を目指せる相談機関
ここでは、不登校の子どもを復学や自立に導くための相談機関を紹介していきます。
親御さん一人で悩む必要はありませんので、専門機関の力を借りながらお子さんに最適な方法で不登校を解決していただけたら幸いです。
3-1. スダチなどの専門機関
スダチでは、お子さんが不登校になったきっかけがわからないときにも、子どもの心境を紐解き、不登校の根本原因から解決しております。
スダチの支援を受けた子どもの中には、不登校が長期化してしまった子どももいましたが、みなさん平均3週間で再登校しています。
スダチの支援では、そのときの子どもの状況に合わせた最適な声かけ方法や接し方を親御さんへ指導させていただいております。
親御さんが日々フィードバックに基づき行動してくださることで、お子さんの心の元気が回復しみなさん主体的に再登校しています。
無料オンラインセミナー動画をご視聴いただいた方に、無料相談を実施中です。
オンライン相談であり、1対1で顔出しも不要です。ぜひ一度現状のお子さんの様子をお聞かせください。
\無料相談を申し込む/
3-2. 学校
学校での問題や、登校していたときの様子を把握するためにも、学校との連携は必要です。
ただし、学校や教員によって対応や運営方針が異なる点は注意しておきましょう。
教員によっては、積極的な対応が期待できない場合も残念ながらあります。
「再登校を促してほしい」という相談ではなく、お子さんの学校での様子を探り心境を理解したい際に相談してみるとよいでしょう。
3-3. ひきこもり地域支援センター
専門家が在籍している施設です。
不登校やひきこもりの相談を無料でできるのが特徴です。
医療機関や民間の不登校支援施設とつないでくれることもあります。
3-4. 医療機関
不登校の原因が学校でのトラブルなどではなく、うつ病や発達障害、起立性調節障害などの場合、心身の症状を治療してもらえます。
しかし、体調不良が続いており不登校が長引いている状況にあると、ADHDや起立性調節障害という診断を受けやすい傾向があります。
ここで診断を受けてしまい「病気だから仕方ない」と再登校をあきらめてしまうのは、非常にもったいないことです。
本来ならば再登校を諦める必要がない場合や、投薬しなくても良い場合もあるため、医師の診断を鵜呑みにしすぎることはあまり推奨できません。
「お子さんが再登校を目指せる状況にあるのか?」は、ぜひ無料相談で現状の様子をお聞かせいただき、判断させていただけたら幸いです。
4. 不登校生徒の復学や自立に向けた支援成功事例
2年もの間不登校だった小学6年生の男子を再登校に導いた事例をご紹介します。
お子さんは、小学校4年生のときに病気になったことをきっかけにそのまま不登校が続いていました。
家庭でのお子さんの状況はあまりよくなく、次のような状況でした。
- ゲーム依存
- 昼夜逆転
- 親への暴言と暴力
- 食事をとらない
- お風呂に入らない
堂々と接することが苦手な親御さんで、親子関係の立場が逆転しているような状況です。
そこで、親御さんに向けてお子さんへの接し方や声かけ方法を日々フィードバックさせていただきました。
親御さんは、毎日子どもへの声かけを1時間も練習し、毅然とした態度でお子さんに接する努力をしてくださいました。
すると、2年間不登校だったお子さんが、支援開始から48日目で再登校!
受験勉強にも積極的に取り組みながら、現在は主体的に楽しんで学校へ通っているようです。
詳しい内容はこちらの記事で紹介しているので、参考にしてみてください。
こちらもCHECK
-
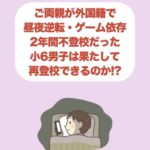
-
【事例紹介】ご両親が外国籍で、昼夜逆転・ゲーム依存にもなり2年間不登校だった小6男子は果たして再登校できるのか!?
この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。 スダチ(旧逸高等学院)の小川です。 今回は不登校のお子さんとの接し方についてお話しします! ↓以下台本です 今回はご両親が外国籍で、昼夜逆 ...
続きを見る
5. 不登校の復学に向かうきっかけ例
ここでは、不登校の子どもが復学に向かうきっかけ作りの例を紹介していきます。参考にしてみてください。
5-1. 親が子どもの話を聞くようになって好転
家庭内でのコミュニケーションがうまくいっていなかった場合、親御さんが落ち着いて話を聞ける状態を整えることで状況が好転した例があります。
- 子どもの話している内容や気持ちによく耳を傾ける
- 子どもの考えていることを尊重する
- 間違っていることがあれば、否定をするのではなく、教えてあげる
上記の取り組みをおこなうことにより、正しい親子の信頼関係を構築できます。
「信頼できる親がいるから、学校へ行っても大丈夫そうだな」と復学への一歩を踏み出せるでしょう。
お子さんが不登校になったときに親御さんが取り組むべきことについて、次の記事でお話ししています。
こちらもCHECK
-

-
不登校になったら親がやるべき3つのこと|不登校の7つのタイプと今の子どもの状態・解決法
この記事を読むのに必要な時間は約 87 分です。 「子どもが不登校になってしまった…子どもにどう接していけば良いのかわからない」 「子どもの今の状態に適した対処方法を知って、不登校を解決したい」 お子 ...
続きを見る
5-2. 前向きに考えられるカウンセリングで子どもの気持ちが整理できた
混乱して不安な気持ちが大きいときには、子どもが物事を前向きに捉えられるような声かけやカウンセリングも大切です。
学校で抱えている問題を多角面から捉えることができ「自分が今抱えている問題は、実は簡単に乗り越えられることなのかも」と前向きに考えられるようになります。
問題をポジティブに捉えられたことがきっかけとなり、再登校を果たしたケースも多いです。
カウンセラーや専門家の力を借りたり、以下の動画を参考にしていただき、お子さんが物事をポジティブに捉えられるような声かけを実施してみましょう。
6. 不登校の復学に関するよくある質問
ここでは、不登校の子どもが復学できるのか悩む際によくある質問をまとめました。今後の参考にしてみてください。
6-1. 不登校の回復率はどれくらい?
文部科学省の調査によると、小中学校で不登校だった子どものうち85.1.%は復帰して高校へ進学することができています。
なお、高校の中退率も14%と低いです。
以前の文部科学省の調査では不登校経験者の高校進学率は65.3%、高校中退率も37.9%と現在よりも悪い結果が出ていたので、復学する生徒は少しずつですが改善されていることがわかります。
6-2. 不登校の生徒が学校復帰する方法は?
不登校から学校復帰する方法は、正しい親子関係を築き、お子さんの自己肯定感を育てることにあります。
また、その状態を整えると同時に、以下のステップを踏み再登校を目指しましょう。
- 学校と同じ生活リズムにする
- 通常クラスに直接復帰する
まずは、生活リズムを学校に通うのと同様のリズムに整えることが大切です。
また、学校復帰を目指すのであれば、別室登校(保健室登校)は挟まず、通常クラスで復帰することを推奨します。
別室登校を挟んでしまうことにより、以下のとおり2つのハードルを乗り越える必要がでてくるためです。
- 別室に登校する
- 通常クラスに登校する
それならば、最初から通常クラスで復帰を果たした方がお子さんの負担も少ないでしょう。
6-3. 不登校の学校復帰のきっかけは?
不登校から学校に行けるようになるきっかけは、子どもによってさまざまですが、代表的なものを紹介します。
- 趣味に打ち込んで何かを成し遂げた
- 今まで以上に親子の信頼関係が深まった
- 習い事を通し家族以外の人との交流は深まった
お子さんの自己肯定感が育ち「自分なら大丈夫」と思えるきっかけがあると、学校復帰につながることが多いです。
7. まとめ
不登校の子どもが復学するためには、子どもだけでなく、親御さんがどのように対応してあげるかがポイントになってきます。
放任しすぎることもよくありませんし、過保護になりすぎるのもよくありません。
子どもが置かれている状況を的確に見極め、正しい対応ができるようにしましょう。
ただし、親御さんだけで頑張らなくて大丈夫です。
現状のお子さんを心配に思う気持ちはぜひスダチにご相談ください。
お子さんの状況を確認し、親御さんがお子さんへかけるべき言葉、そして行動方法をしっかりアドバイスいたします。
無料オンラインセミナー動画をご視聴いただいた方に、無料相談を実施中です。
オンライン相談で、1対1で顔出しも不要です。ぜひ一度現状のお子さんの様子をお聞かせください。
\無料相談を申し込む/







